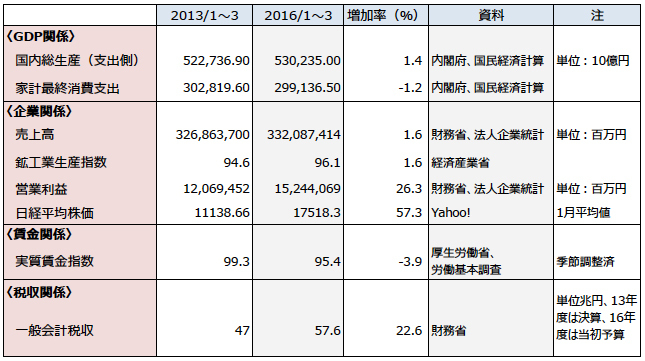◆ Blogで学ぶ思考力
読書ノート:清原達郎著『わが投資術』(KODANSHA刊)
清原氏とは何者か
清原氏はタワー投資顧問(株)のファンドマネージャーで、旗艦ファンドK1ファンドを運用して25年、2023年に引退したときには800億円の私財を蓄えるに至った。
もちろん私財構築はK1ファンドへの投資によるところが大きい。ファンドマネジャーは自己資金を自ら投資することで顧客の信用を勝ち得ることができるという哲学がこの成果を支えたと言える。
筆者の経験
私事にわたるが筆者は以前、企業年金基金の理事長を務めていたことがあった。2000年頃の話だ。その基金は設立して間もなかったが、バブル崩壊後もあって運用難が続き、毎年企業から運用不足を補ってもらう状況にあった。このときにK1ファンドに出会い、清原氏の運用術に魅力を感じてかなりの額をK1ファンドに注ぎ込んだ。
その頃はヘッジファンドに資金運用を任せる年金基金はほとんど存在せず、当該基金の運用主幹事であった信託銀行の担当者からは難色を示されたが、それを無視して運用を任せた。信託銀行の担当者には強気の姿勢で接したが、内心はヒヤヒヤだった。
筆者に天運がついてきたのか、その後K1ファンドはニトリへのロング投資が結実し、かなりの運用益を獲得することができた。ちょうどそのとき筆者は理事長を退任することになり、それをしおにK1ファンドを解約し、後任の理事長は極めて無難な投資方針へと回帰した。
結果として基金はかなりの余剰資金を得ることになり、その後成り行き的な運用をしてもびくともしない財務基盤を築くことができた。
K1ファンドとは
清原氏のK1ファンドは、中小型株をロングで運用して、大型株をショートで運用するヘッジファンドの部類に入る。しかしその運用の妙は中小割安株をロングで運用して思い切り利益を獲得するということにある。
清原氏によれば中小型株には次のような魅力があるという。
l 儲けやすく、一番儲かる
l 独自のリサーチがしやすい
l 機関投資家の投資対象ではない
l アナリストがカバーしていない、したがって推奨もしない
清原氏はこのように魅力的な中小型株の運用の極意を、この著作で手の内を洗いざらい出してくれている。個人投資家ならば清原氏の中小割安株をロングで運用する手法をマスターすることで確実に利益を得ることが可能になるはずだ。
数値による中小型割安株の見極め方
割安か否かの見極めで大事な指標はPERだ。しかし単なるPERだけでは見極めは困難だ。資産や負債の実態を勘案しないと判断は容易ではない。
そこで頼りの綱として登場するのが、清原氏が編み出したネットキャッシュ比率だ。ネットキャッシュとは、
ネットキャッシュ=流動資産-棚卸資産+投資有価証券X70%-負債
つまりすぐに換金できる資産から負債を差っ引いた金額ということだ。ここで投資有価証券について70%を乗じているのは売却時の税負担を考慮しているからだ。
次にネットキャッシュを時価総額で割った比率がネットキャッシュ比率ということになる。
ネットキャッシュ比率=(流動資産-棚卸資産+投資有価証券X70%-負債)時価総額
このネットキャッシュ比率が1ならば、タダでその会社を買うことができることを意味することになる。
そして少し込み入った話になるが、ネットキャッシュ全額で自社株買いをしたら、ネットキャッシュはゼロになるわけで、この時の((時価総額-ネットキャッシュ)/時価総額)の比率は時価総額がネットキャッシュをどれだけ上回っているかを表す指標になる。
さらにこの((時価総額-ネットキャッシュ)/時価総額)の比率にPERを乗じれば、財務状態を加味した上での、株価の相対的な割安指標として使えることになるわけだ。これを清原氏はキャッシュニュートラルPERと呼んで、中小型株の割安度を比較するための指標として使っている。
改めてキャッシュニュートラルPERを数式で表すと次のようになる。
キャッシュニュートラルPER=PERX(1-ネットキャッシュ比率)注1
定性的要因による割安株の見分け方
中小型株の成長性を定性的に見極めるための判断基準として、清原氏は次の諸点を挙げている。
Ø 経営者がその会社を成長させる強い意志を持っているか
Ø 社長と目標を共有する優秀な部下がいるか
Ø 同じ業界の同業に押し潰されないか
Ø 会社のコアコンピタンスは成長とともに拡大するか
Ø 成長によって将来のマーケットを先食いし、潜在的マーケットを縮小していないか
Ø 経営者の言動が一致しているか
これらの要点のうち、部下の優秀さとか、経営者の言動の一致などは外部情報で判断することは困難だ。清原氏は対象企業を訪問して社長や他の経営者にインタビューを繰り返すことで判断している。
個人投資家にはこれだけは真似できないが、他の要点は外部に開示された資料を読み解くことで判断が可能になる。
いざ中小型割安株の投資に向かおう
清原氏に依れば、「今の日本の長期金利を前提にすると、PERが10以下の株は総じて信じられないくらい割安。長期金利(10年国債の利回り)が3%まで上昇してもまだ割安」なのだ。
騙されたと思って割安中小型株の投資に余裕資金を振り向けてはいかがでしょうか。下手な副業をして神経をすり減らすよりは愉しい上に儲かるとあっては、一石二鳥ではないだろうか。
注1
キャッシュニュートラルPER
=PERX(1-ネットキャッシュ比率)
=(時価総額/純利益)x(1-ネットキャッシュ/時価総額)
=(時価総額/純利益)x(時価総額-ネットキャッシュ)/時価総額
=(時価総額-ネットキャッシュ)/純利益
注2
日本原子力発電株式会社は廃業すべきだ
原子力規制委員会は日本原電の敦賀2号炉の再稼働を認めない判断を正式に下した。敦賀原発が活断層の上に位置することが決め手となった。
「規制委は敦賀原発2号機について、原子炉の直下に活断層がある可能性を否定できず、新規制基準に適合しないと結論づけた。11年の東日本大震災後に決めた新規制基準では原子炉の真下に活断層がある場合、原発の稼働が認められない」。
この決定に対し原電は、あくまでも再稼働を目指して再申請する構えを示した。活断層の上に原子炉がある原発の再稼働など、今後とも一切認められることはないと考えるのが常識的な判断だ。つまり一刻も早い廃炉こそが正解なのだ。電源がなぜこのような非常識にこだわるのか理解に苦しむ。
そもそも原電とはどのような存在なのか。
「原電は発電された電力を買う契約を結ぶ大手電力会社5社が経営を支える。原電は稼働中の原発がない。現在は再稼働を前提に電力会社から『基本料金』を毎年受け取り、原発の維持費や人件費などに充てている。金融機関からの借入金も電力会社の債務保証を受ける」。
原電の発電した電気は電力会社5社が全量買取する。しかし東日本大震災以降は、原子炉を休止したため、発電しない電力会社になった。休止中の設備保全のためのコストは他の電力会社が「基本料金」を支払って賄ってきた。
「敦賀原発2号機は、関西電無駄力と中部電力、北陸電力の3社と契約を結んでいる。各社とも毎年100億円程度の基本料金を原電に払っているとみられる」。
さらに「11年から電力5社が原電に支払った基本料金の総額は約1兆4000億円に上る」。この膨大な金額が消費者と産業界が負担する電力料金に上乗せされている。
廃炉となれば716億円の解体費用が必要と試算されている。基本料金8年分でお釣りがくる額だ。可能性のない再稼働のためにムダ金を延々と浪費するより、早急に廃炉の決定をすることが最も経済合理性に則った意思決定になるはずだ。
さらに敦賀2号炉の廃炉だけでなく、今や所持するすべての原子炉が休止状態の原電そのものの存在意義を問い直して、原電の廃業を目指すべきではないか。リスクが大きくしかも発電コストが圧倒的に高い原発を少しでも減らすことにつながる。
何よりも毎年1000億円ほどの電力料金の値下げがこれで可能になる。
日経新聞11月14日朝刊に依拠
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20241114&ng=DGKKZO84769190T11C24A1EP0000
トランプは米国下層階級の救世主になれるのか?
トランプの経済政策は次の四本柱から構成されているように見える。
1. 移民の制限及び不法移民の強制送還
2. 輸入関税の引き上げ
3. 法人税、所得税の減税
4. ドル安に向けた為替政策そのための金利引き下げ
これらの政策を総合的に展開して達成すべき目的は次のとおりだ。
1. 米国製造業の復活
2. 労働者階級の賃金上昇による所得拡大
3. 消費拡大による継続的な経済成長
何よりも関税を武器に輸入品をシャットアウトして、国内の製造業を活性化して地消地産を推進する。中南米やアジアに移設した工場を呼び戻し国内供給力を拡充する。
法人税の減税は製造業のこうした米国内設備投資を助成し、工場の海外移転の歯車の逆転に拍車をかける。
また法人税減税は製造業のみならず全産業に納税地の本国回帰を推し進めるドライバーになる。他国企業の納税本社も米国に転居するかもしれない。
さらにドル安政策が輸入品の価格を押し上げ、競争力を弱め、米国製造業の復活を後押しする。
こうして慢性的な貿易赤字ばかりか経常収支そのものの赤字が解消され、米国内での資金供給と資金循環が充実する。
何よりも製造業の雇用が拡大する。これに加えて移民の制限によって労働力供給が絞られ、労働者の賃金の上昇と、所得拡大と、消費の拡大が確実に実現する。結果として継続的な経済成長が可能になる。
継続的な景気拡大は社会不安を取り去り、社会は安定化に向かい、MAGAの実現につながる。
盲点はないか
以上のシナリオ、全てうまく回り出しそうだが懸念点も見え隠れする。最大の問題は物価の上昇の危険性が潜んでいるということだ。
高率関税とドル安は物価の上昇要因になるし、労働者階級の賃金上昇も高物価の引き金になる。また減税による投資、消費の拡大は、需給ギャップを大きくして物価の上昇に拍車をかけインフレが加速する。
ただでさえ今の米国の労働者階級は高物価に悩まされ、生活水準を引き下げるしか対応できない状況に追い込まれている。そしてそれがトランプの復活をもたらした最大要因であったわけだ。
となると物価の上昇は労働者階級はこんなはずではなかったというトランプに対する幻滅感を助長し、一向に生活が楽にならない状況の中で社会不安が高まり、不安定化していくことが見えてくる。
インフレでも生活苦に直結しないかも
このリスクシナリオが外れる可能性がる。米国とロシアだけが唯一持っている地政学的な優位性によって、インフレは生活苦に直結しない可能性がある。
その地政学的優位性とは、食料とエネルギーの自給が可能だということだ。日本と違って米国は農業畜産業大国であり食糧の自給率は100%を超える。
エネルギーも化石エネルギーではあるが、シェールガスの発掘によって自給どころか、輸出さえ可能な状況だ。
食糧とエネルギーという二つの基本消費財が自給可能であることが、基本財の価格を安定化し、インフレ基調であっても生活苦に直結しない状況が可能になると考えられる。
少なくともこの基本消費財の価格安定を維持することが、トランプ政権が長期的に安定NI向かうための最重要課題ということができる。
年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます
元旦から能登半島を中心に北陸にて激甚災害が発生し、多くの方々が被災されました。
被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
一説によりますと日本列島は東日本大震災以降、地殻の大変動機に入ったと言われています
今回の北陸大震災も太平洋プレートの動きによって生じたと考えられています。
京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏は2038年に東海トラフ、南海トラフの巨大地震が起きると予言しています。また首都直下型大地震もいつ起きてもおかしくはないようです。そしてこれらの巨大地震と同時に富士山をはじめ火山の噴火が起きることも想定しなければならないようです。
いつ巨大地震が起きても身の安全を守るための訓練や、生活インフラが停止しても一ヶ月は生き延びることが可能な備えをしておかねばならないことを、今回の北陸大震災によって再確認を迫られているようです。
さて天変地異は別として本年は世界がどのような年になるのでしょうか。大きな転換が進むと考えられます。その転換とは米国の一極支配の体制が終焉して、多極化の体制が確立するという転換です。
米国の一極支配体制の終焉を促したのはBRICS諸国の台頭です。BRICSの盟主は他ならぬ中国です。中国は昨年サウジアラビアに急接近し、サウジからの石油調達に道筋をつけ、石油代金の決済を元建てで行うことで合意しました。
また2023年8月のBRICSサミットではサウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラン、エジプト、エチオピアのアラブ諸国の加盟が実現し、さらにアルゼンチンを加えてBRICS+6として連帯することになりました。
BRICS+6はこのサミットで独自通貨の発行を決定し、2024年にも実現に向けて道筋が付けられることになりました。独自通貨の発行によってBRICS+はドル通貨圏からの離脱が可能になり、これにグローバルサウスの諸国が加わることで、ドルの世界通貨としての影響力の希薄化が進むことが予想されます。
そしてBRICSで際立つ大国である中国とインドの動向から眼が離せない年になることは間違い無いでしょう。
こうして2024年はBRICS+6の存在感が強まる年になりそうです。同時にEUもアメリカとの同盟の絆が緩み、独自の路線を押し出してBRICS+6との融和を進めることになるでしょう。
この湯にして世界は多極化への転換が決定的になると考えられます。
そろそろ日本も米国への一辺倒の傾斜姿勢を矯正し、多極化する世界の転換を前提として、東アジア諸国との連帯を強める方向へと舵を切る季節を迎えたようです。
一人当たりGDP日本はG7で最下位
日経新聞12月26日朝刊が次のように報じている。
https://www.nikkei.com/paper/article/b=20231226&ng=DGKKZO77262690V21C23A2EA2000
「内閣府が25日発表した国民経済計算の年次推計によると、豊かさの目安となる日本の2022年の1人あたり名目国内総生産(GDP)は3万4064ドルとなった。イタリアに抜かれて主要7カ国(G7)で最下位だった。円安が大きく影響したが、長期的な成長力の低迷も映している」。
OECD加盟国の中では21年より順位を一つ落としての22位だった。
円安の影響が大きい。
「22年末にかけて急速に進んだ円安がドル換算の1人あたりGDPを押し下げた。内閣府の試算で前提においた為替レートは22年は1ドル=131.4円で、21年は1ドル=109.8円だった」。
名目GDPの総額ではどうか。
「名目GDPの総額では日本は22年に4兆2601億ドルだった。世界のGDPに占める比率は4.2%で、米中に次いで3位は維持した。シェアは比較できる1980年以降で最低で、2005年の10.1%から17年間で半減した。ドイツのドル換算の名目GDPは22年に4兆825億ドルでシェアが4.0%となっており、日本に肉薄する」。
名目GDPの総額は国力を表す指標だ。名目GDPのシェアの下降は日本の国力の衰退を物語っている。
GDPの減衰は消費支出の低迷によるところが大きい。円安による食料、エネルギー価格の上昇そして消費税増税政策が物価全体の底上げにつながって消費位支出の伸び悩みを招いている。それに加えて生産性が下降して賃金水準が頭打ちとなって、消費支出は三重苦に押しつぶされる形で減衰している。
この状況からどのようにしたら脱却できるだろうか。
まずは消費税の廃止だ。最もスピーディに実現できる着手点だ。
そして次は賃金を押し上げる政策を矢継ぎばやに打ち出すこと。最低賃金は思い切って1,800円程度に押し上げる。一日8時間、月20日勤務で約30万円弱の水準だ。同時に介護士、保育士、看護師、消防士、警察官、自衛隊員などのエッセンシャルワーカーの賃金水準を現状の1.5倍水準に押し上げるとよい。
この二つの政策で消費が増加傾向に向かい、GDPが押し上げられ、結果として円高に向かい、輸入物価が下降軌道に乗って、物価水準が下がり、消費の拡大をさらに刺激することになる。
政府がこれらの政策をとることで緊縮財政から積極財政への大転換をはかれば、日本の国力が拡充し、結果として一人当たりのGDPが回復基調に乗るようになるはずだ。
意思決定はChatGPTで上質化できる
HBRオンライン掲載に掲載されたトーマス・ランジ ,ビクター・マイヤー=ショーンベルガーの『チャットGPTで意思決定の質を向上させる方法』(https://cl.diamond.jp/c/aq7yac
意思決定のプロセスは次の3段階からなる。
1. 課題の定義と目標設定
2. 課題解決方法を複数案創出
3. 課題解決方法の最適案の選択
このプロセスの全てにわたってChatGPTは意思決定者に有効なサポートを可能にする。すぐにでも使えそうな回答が得られるわけではない。ChatGPTが人間の限界を超えて多数の有効な解決策を提案してくれることが重要なポイントなのだ。
意思決定の上記のプロセスをより効率的により効果的に体系的に進めることをサポートしてくれるということだ。
そしてさらにこれまで思いもつかなかった解決策をいくつも提案してくれることになればもはやAIなしに意思決定を行うことは考えられないことになりそうだ。
「現在のチャットGPTがさらに有用となるのは、まったく考えが及ばない選択肢や、簡単には思いつかない選択肢を追加で見つけ出すために使う場合だ。これにより意思決定の視野が広がり、自分が気づいているよりもはるかに多くの、広範囲にわたる選択肢があることがわかる」。
なぜChatGPTで意思決定の上質化が可能になるのか
なぜなら「チャットGPTがアクセスできる公開データの一部には、業界や企業の種類ごとに選択肢の宝庫があるからだ。ゆえにチャットGPTは、似た状況下にある企業によってインターネット上に記録された多くの戦略を提示でき、独創的なアイデアを思いつくかもしれないのだ」。
ChatGPTと対話を繰り返す中でAIは意思決定者の置かれた環境、経営状況についての情報を取得し、その状況に類似した他社の事例を参考にして複数の選択肢を提供してくれる。
適切なプロンプトが決め手になる
これを効率的に行うには有効なプロンプトを投げかけることができるかにかかっている。例えば次のようなプロンプトを投げかけてみることでChatGPTは質問を投げかけた意思決定者の状況を前提に類似の事例を検索して、いくつかの有効な解決策を提示してくれる。
「こんにちは、チャットGPT。私はオハイオ州コロンバス郊外にある中規模機械メーカーの社長で、経営は順調です。新しい人材、特にエンジニアの獲得に苦労しています。どのような原因が考えられますか。同じような製造企業は、人材不足に対処するためにどのような戦略を採用していますか」。
ChatGPTGAより有効になるには
ChatGPTが今後このような機能にさらに磨きをかけていくためにはケーススタディの情報蓄積とその活用の道を開くことが欠かせない。
「ビジネスケーススタディを独占的に保管しているハーバード・ビジネス・パブリッシング(HBRの親会社)や、非営利のケースセンターといった主要機関が大規模言語モデルの開発企業と協力すれば、チャットGPTは意思決定者にとって強力な意思決定アシスタントに変わるだろう」。
なぜなら「経営者らが直面する意思決定のうち、唯一無二のものはほとんどない。かつて何千人、時には何百万人もの経営者が、似たような選択を迫られてきたのだから。
彼らがどのように意思決定の枠組みを設定し、選択肢を比較検討し、決断をしたのかについて、人間の言葉でより巧みに説明されればされるほど、ディシジョンGPTはより多くの情報に基づく意思決定のための強力なツールとなるだろう」。
「TSCMは台湾にとどまる!」創業者モリス・チャン氏の宣言
ダイヤモンドオンライン2023/11/1「TSMCは「地元台湾の半導体サプライチェーン」を強化!」によるとTSCNは世界の半導体技術先進地に技術拠点を展開しつつも、台湾において半導体産業の集積地を構築するビジョンを掲げ、これを実現するために持続的に手を売ってきている。
そのエポックが台湾でのr&dセンターの稼働開始だ。
以下に本記事の主要な記述を抜書きしてみよう。
「7月28日、台湾の新竹県宝山郷。世界の半導体産業を左右する先端基地が誕生した。半導体受託製造世界最大手のTSMCが、グローバルR&Dセンターを開設したのだ。
延べ床面積は30万平方メートルと、サッカー場42個分の広さだ。将来的にはここで7000人のエンジニアが知恵を絞り、回路線幅が2nm以下の先端半導体や高速コンピューティング、人工知能(AI)サービス、自動運転、裸眼3D技術などに取り組む」。
「この日登壇したチャン氏は、TSMCは創業初日から技術的に独立する道を志しており、オランダ・フィリップスの特許を取得するために高額の手数料を支払ったことを振り返った。以来、TSMCは世界の大手メーカーの特許に干渉されないよう、技術面で自立することに注力してきた。
TSMCが技術の独立から技術のリーダーに至るまでには長い道のりがあった。世界をリードしていると自信を持って言える、7nmプロセスの半導体の量産までには30年かかった。
20年近くにわたり、TSMCは売上高の8%を研究開発費に投じてきた。現在の年間売上高は2.26兆台湾ドルに迫り、研究開発費は55億ドルに達した。これは米マサチューセッツ工科大学の年間予算20億ドルをはるかに上回る額だ」。
「TSMCの強みは、独立した技術や研究開発のリーダーシップ、グローバル人材に加えて、台湾の地元サプライチェーンとの継続的な協力関係がある。TSMCのウエハーコストが比較的低く、生産効率が高い理由であり、強力な競争力を守る“堀”になっている。
地政学的なリスクや米中の貿易摩擦、ESGの観点などにより、各国は半導体サプライチェーンの現地化を求めている。
TSMCも2019年から現地調達の比率を高めており、地元サプライヤーへの助言も積極的に行ってきた。
現在の地元の原材料サプライヤーは9社だが、30年までに38社へと大幅に増加させる計画だ。また原材料の現地調達比率も10年以内に50%に、補修部品の現地調達比率も68%まで高める方針である。
独自技術を持つTSMCが現地地元サプライヤーの技術および生産能力の向上を支援するだけでなく現地調達を進めることは、輸送時間の短縮や省エネなど生産効率の向上につながる」。
「TSMCは地元メーカーへの助言や技術サポート、検証を支援する専門チームを3年前に立ち上げた。TSMCのサプライチェーンに食い込むことができれば、まるでスズメが不死鳥に化けるかのように業績と市場価値は飛躍的に高まる。その代表が家登精密工業だ」。
「現在、TSMCの年間支出320億ドルの50%近くが台湾に投じられている。TSMCと取引する台湾の小さなテクノロジーの巨人は、主に3分野に分けることができる。
一つ目は「CoWoS」と呼ばれる先進的な半導体パッケージングのサプライチェーン企業、二つ目は工場の建設や設備機器、材料のサプライヤー、三つ目は半導体用の特殊な化学品や産業ガスのサプライヤーである。
米エヌビディアの新しいAI半導体は全てTSMCのCoWoSプロセスを使用しており、関連生産能力の不足が深刻化している。TSMCはCoWoSの生産拡大を加速しており、ここに参入する台湾企業は勢いに乗るだろう」。
謎の日米株価の連動
Wall Street Journalは直近の2年間、日米株価が謎の連動をしていると報じている。図1は現地通貨建ての直近2年間の株価の推移だ。日本の株価は23年に入って急上昇している。それに対して米国株価はほぼ低迷状況にある。
日本では日米金利差が拡大することで円安が継続し、輸出企業を中心に業績が伸長したことが株価上昇のエンジンになっている。さらにこの金利差が円キャリー取引を生み外国投資マネーが日本株市場に流入して株価を押し上げている。
しかし日本株の動きをドル建で見たときに様相は一変する。図2に見られるようになんとまるで申し合わせたかのように一心同体の動きをしているではないか。
図1 現地通貨建ての株価推移
図2 ドル建ての株価推移
なぜこのような不思議な状況が生じ、しかもそれが2年も連続しているのか。
WSJの解説では二つの理由が挙げられている。
「もしかすると、インデックス取引のトレーダーや先物トレーダーが個別銘柄を無視して大金を投じていることが原因であり、ストックピッカー(銘柄選別者)に絶好の機会がもたらされているのかもしれない。しかし、これを証明することは不可能だ。もう一つの説は『全くの偶然』というもので、投資の根拠としては厳しい」。
偶然説はおくとして、トレーダーが個別銘柄を無視して大金を投じているとしても、それが日本株価と米国株価との連動要因になるには、日本株価が米国株インデックスに準拠して連動することが前提になる。つまりトレーダーは米国株インデックスに連動して日本株も動くと考えて取引しているということになる。
ということは日本の株価は日本の経済ファンダメンタルズにかかわらず、米国の経済ファンダメンタルズを反映した動きをするという前提が日米のトレーダーに共有されているということだ
つまり日本経済はもはや自律的な主体ではなく限りなく米国経済に包摂されてしまっているという実態が日米株価の同体化によって可視化されているのかもしれない。
テスラの戦略ストーリー(最終回)
テスラの瀬延暦ストーリーは第4図で示されるとおりだ。
テスラのビジョンを実現するための第3番目の目標は「絶えざるコストダウン」だ。
テスラは持続的にコストダウンを追求することで販売価格を引き下げ、EVの普及のスピードを加速することを狙っている。テスラのコストダウンは次の4つの柱で推進されている。
1. 無店舗販売・広告費ゼロ
2. 主要部品の自社開発、製造
3. ギガファクトリー
4. ハード、ソフトの全モデル共通化
無店舗販売
テスラは販売店舗を持たない。代理店も使わない。広告費も使わない。オンラインで顧客と直結して最短の流通経路で販売を完結する。
顧客は例えばYouTubeからテスラのサイトに入り、車種を選択し、ボディーカラーと自動運転ソフトを選択するだけで購入が終わる。1分もかからない超短時間で購入契約が完結する。
顧客が試乗を望む場合には、試乗したい場所を指定すれば試乗車が届けられる。おそらく自動車が発売されて初めての画期的な販売システムのイノベーションが実現されている。
テスラはまた広告費を使わない。SNSを活用してテスラの情報を開示し、広報している。そいて熱狂的なテスラファンがテスラの素晴らしさについてYouTubeやX(旧Twitter)を使って夢中になってアップしてくれる。
主要部品の自社開発、自社製造
テスラは主要部品を自社で製造することで持続的なコストダウンを実現してきた。
その第一歩はバッテリーの自社製造だった。テスラはEVに参入してすぐにバッテリーの供給能力が世界的規模で圧倒的に少ないことに気づいた。急増する需要に応えるには自社でバッテリーを製造するほかないと決断し、2014年にネバタ州に年間50万ユニットのバッテリー・セルを製造するギガファクトリーを建設した。自社製造することでバッテリーの技術開発の道が拓け、バッテリーの自社開発に繋がっていった。
バッテリー・セルの製造が始まると次にバッテリー冷却機能を付加してバッテリー・パックの製造も乗り出し、更にはモーターと結合してドライブ・ユニットをも製造するまでに至った。
このように部品の製造から始めて、モジュールの製造に至る進化が次々に起き主要部品の自社開発・製造が軌道に乗り、拡大している。
EVの要となる部品に半導体チップがある。テスラはこの半導体チップをも自社設計・開発し、2021年に自社開発のAI用コンピューターDOJO用の半導体チップD1を設計・開発した。
テスラは半導体素材のリチウムの精製工程の内製化にも取り組んでいる。近い将来にはリチウムの資源開発にもアプローチするかもしれない。
半導体の自社設計・開発を進化させてきたおかげでテスラは他の自動車メーカーが操業停止や減産に追い込まれた2021年の半導体不足危機において、減産を免れることができた。
ハードウエア部品の自社製造だけでなく、ソフトウエアの開発もテスラはもっぱら自社開発にこだわっている。その究極のソフトがDOJOを駆使して開発する完全自動運転のソフトウエアだ。
テスラはなぜ部品の自社製造にこだわるのだろうか。その理由の一つは自社製造によって次のアドバンテージを獲得できると考えているからだ。
1. 自社開発・製造によって部品の改善スピードが高速化する。
2. 自社開発・製造によって部品の製造コストが下がり、また自社工場の内部あるいは近隣で製造可能になるので、部品の物流コストが低減する。
3. 何よりも全体最適のビジネス展開が可能になる。
ギガファクトリー
既存の自動車メーカーの工場は数万点に及ぶ部品の供給を受けて、それらを組み立てる最終工程を担ってきた。部品メーカーは自動車メーカーの系列に組み入れられ巨大なピラミッド構造の一部として機能してきた。
多数の協力工場が必要なときに必要なだけ部品を自動車メーカーに供給するJITシステムが自動車製造システムの神経系統として機能してきた。
テスラはこの多階層ピラミッド構造を破壊し、主要部品を内製化することを基軸にした工場を建設してきた。勢い工場の規模は巨大化せざるを得なかった。2014年のネバダのバッテリー工場を皮切りに次々と建設された工場はギガファクトリーと称せられるに相応しい規模(2023年稼働したテキサス工場は93万㎡)になった。
このギガファクトリーでのイノベーションの最たるものはギガプレスであった。70以上もの部品から構成されるモジュールをたった3点の部品を一体化して一つのモジュールに鍛造成型するのがギガプレスだ。まさに飛躍的な工程短縮とシンプル化が実現した。これで日本の製造業のお家芸であった「すり合わせ技術」は完全に過去の遺物になったというわけだ。
ギガファクトリーのもう一つの特徴はサプライヤーの工場を近接して建設することだ。これによって部品の供給に伴う物流コストが激減した。同時にサプライヤーとの原価底辺に向けての協業がより効率的に進められることになった。
製造と設計についてはマスクの徹底したこだわりがある。それは設計技術者を製造現場の側に常駐させることだ。設計技術者が現場から遠いところで仕事をすることを辞めさせて、設計者が現場を常に観察し、現場の声を受け止めて次々と工程改善をしていくことを求めている。まさに終わりのない原価低減がスピーディに進行する仕掛けが出来上がっている。
ハード・ソフトの全モデル共通化
テスラの製品モデルはいくつかあるが、全てのモデルでできる限りの共通化を実現している。ハード、ソフトの共通プラットホームの上でモデルごとに異なる仕様だけが付加されることで、設計、開発、製造の全プロセスにわたって圧倒的な原価低減が可能になっている。
テスラの戦略ストーリー(その3) 完全自動運転の実現
テスラの戦略ストーリーは第4図で示されるとおりだ。
完全自動運転の実現
テスラのビジョン実現のための2番目の目標は、「完全自動運転の実現」だ。
なぜ「完全自動運転」なのか。
1. 完全自動化によって自動車はようやく完成形を迎えることができるからだ。ヒトが操縦するクルマは「走る凶器」であり、操縦するヒトの能力は不完全であるがゆえに、絶え間なく事故が発生し、多くのヒトが犠牲になっている。
2. 自動化によって各車の走行経路の最適化が行われ、渋滞が回避され、走行に要するエネルギーの効率的な消費が自動的に実現する。
3. ほとんどのヒトにとって運転はストレスを伴い、できれば回避したい苦行だ。閉所に閉じ込められ、視神経と脳をフルに働かせることによるストレス。長時間の移動ともなればそのストレスは耐え難いものになる。自動運転はこのストレスからヒトを解放する。
イーロン・マスクの掲げる完全自動運転のEVのイメージは、ハンドル、アクセル、ブレーキのない車だ。もはやそれは既存の自動車のイメージとはかけ離れた、「走るリビング」、「走るオフィス」、「走る寝室」のようなものだ。あるべき姿のイメージはいくらでも拡がる。
テスラの自動運転の特徴
「米国自動車技術会(SAE)の自動運転のレベル定義をベースに国土交通省が示した自動運転のレベル分けは第5図で示される。
第5図自動運転のレベル分け
テスラの自動運転は「エンハンスト・オートパオロット(EOP)」および「フル・セルフ・ドライビング・ケイパビリティ(FSD)」の二つのグレードのアプリの選択ができるようになっている。
EOPは自動で高速道の走行を可能にしている。FSDはEOPの機能に加えて市街地でのオートステアリングも可能にしている。これらの仕組みでレベル3をクリアしていると言える。
テスラの自動運転の特徴は次のとおりだ。
1. 地図情報は使わずセンサーとAIが自動運転をサポートしている。
2. EOP、FSDのインストールで自動運転を可能にするハードウエアを全車種で標準装備している。
3. ソフトウエアアップデートで継続的に機能進化が可能になるように設計されている。
地図情報を使用しないというのはグーグルに対して徹底した差別化をしようとするイーロン・マスクのこだわりから来ているようだ。マスク曰く「人は眼と脳だけで車を操っている」。
そしてこのマスクのこだわりは自動運転ソフト開発をグーグルとのコラボレーションによって実現しようとして、ラリー・ペイジに声をかけたところ、ペイジはそれをすげなく断わり、Googleは自動運転ソフトを独自開発する道を選択したという経緯に端を発しているようだ。
徹底したソフトウエア・ドリブンでの価値提供
テスラにとってEVはもはや自動車の概念から大きく離脱してしまっている。例えて言えば「走るコンピューター」、「走るスマホ」ともいうべき価値の提供を目指している。EVの制御はほとんどがソフトウエアによって実現されている。その究極の姿こそ完全自動運転(FSD)ソフトの開発・提供だ。
こうしたソフトウエア・ドリブンを可能にするためにはモジュール化によって統合されたハードをセンサーからの情報によって制御するためのECU(電子制御ユニット)を管理するOSの開発・進化が必要だ。テスラのハード制御のOSは高度な学習能力を持つAIによってサポートされている。
このAI開発・進化の機能はカリフォルニアに集約されている。そしてAI開発・進化のためのスーパーコンピューター(DOJO)をも自社開発している。
またソフトのインストールはオンラインで自動的に実行されるが、そのためにはテスラ車は常時接続状態にあることが求められ、前回で紹介したスターリンクがそれを可能にしている。
次の回ではテスラのビジョンの実現につながる第3の目標、「耐えざる生産性向上そしてコスト・ダウン」について見て行こう。
テスラの戦略ストーリー(その2)顧客体験による提供価値の進化
テスラの戦略ストーリーは第4図で示されるとおりだ。
テスラの掲げるビジョン
テスラの掲げるビジョンは「EV への世界的な転換を最も効果的に実現する」ということだ。
地球環境の持続可能性が損なわれつつある中でEVの普及は再生エネルギーの普及とともに世界的な課題になっている。この課題にこれまで自動車産業を牽引してきた既存自動車メーカーが及び腰になっている中で、テスラは自動車産業に新規参入した当初から、内燃機関エンジン車からEVへの大転換の先頭に躍り出て、この転換を牽引している。
まさに既存自動車産業がイノベーションのジレンマを抱えて呻吟するのを尻目に、そうしたジレンマからは全く無縁な地点に立ってスタートしたがゆえに、テスラがこの大転換の先頭に立っているのだ。つまりテスラはEVを推進する上で失うものを何一つ持たない自由な、そして身軽な環境から出発したということが絶対的な競争優位の状況を創出してきた。そしてそうであるがゆえにテスラはEVへの世界的な転換を最も効果的に成し遂げられる位置から自動車産業への参入を遂げたということになる。
テスラはこのビジョンを実現するために次の三つの目標を設定したと考えられる。
1. 顧客体験による提供価値の進化
2. 完全自動運転の実現
3. 絶えざる生産性向上、コストダウン
以下にこれらの目標の一つ一つを見ていこう。
顧客体験による提供価値の進化
ある意味でゼロからEV事業を立ち上げ展開するテスラにとって、顧客がテスラを運転する体験から生ずる様々な情報を現場から収集し、それを課題化しそれに対してスピーディーにそして確実に対応することは提供価値を進化していくうえで必要不可欠なことであった。
そのためにはまず走るテスラが抱える改善点や不具合の実態が把握できなければならない。そのためにテスラは走行する全てのテスラ車から常時データを収集することを目指した。これによって顧客が体験する状況を現場から生リアルのデータとして把握し、異常値や不具合状態や顧客の動作分析から浮かび上がる改善点などが収集され、課題化されそして優先順位をつけられて改善が進んでゆく。
この流れはアプリケーションの提供価値の進化を実現するプロセスとほぼ同じであるといえる。その意味でテスラはハードではなくソフトウエアとして価値提供されていると考えた方がその実態をより良く理解できるということだ。
こうしたデータ収集のためにはそのための仕掛けが必要になる。それは走行する全てのテスラ車とのリアルタイムでのネットワーキングだ。そしてこの常時連携のための通信インフラとして開発運用されているのがリンクスターだ。
スペースX社が運営するスターリンクは衛星インターネットアクセスサービスだ。スペースXは2014年以降2021年までに33回の宇宙ロケットの打ち上げを成功させてきた。一度に30機の人工衛星を軌道に乗せ、2021年末現在3000機の人工衛星が数珠つなぎに連なって、緯度60度以下の全地球をカバーするインターネットアクセスを可能にしている。
このインフラを活用してテスラ車の常時ネット接続が可能になっている。そしてこのネット常時接続インフラはテスラ車の全自動運転(FDS)にとって不可欠なシステムとしても活用されることになる。
充電ステーションの普及
EVの顧客価値の進化にとってもう一つ大事なファクターがある。それは充電ステーションの普及だ。このためにテスラは15分で257km走行可能な急速充電器スーパーチャージャーを開発し、これをネットワーキングして、充電にまとわる顧客のストレスを解消する充電インフラ作りを推進している。
テスラはこのスーパーチャージャーによる充電ステーションの普及を他社に先駆けて一気に推進する意欲を見せている。そのことによって将来的に充電方式がテスラ方式に統一されテスラの充電ステーションが充電ステーションのデファクトスタンダードになることを意図している。
これによって他社のEVもテスラの充電ステーションを使うことで利便性が増加し、それは同時にテスラ社の充電サービスによる収益拡大に寄与し、またテスラ車も他社の充電ステーションが利用可能になることで顧客価値が一気に拡大することになる。
次回は2番目の目標である「完全自動運転の実現」について解説しよう。
テスラの戦略ストーリー(その1)
テスラの快進撃が止まらない。
図―1によって販売台数の推移を見てみよう。
2022年度の販売台数は131万台。前年対比で40%増加して百万台の大台を軽くクリアした。
販売台数は2018年度、2021年度に大幅増加を達成している。
2018年では高級車セグメントのModelX,ModelSに大衆車セグメントのModel3が加わり、それが台数シェアで60%を占める販売構成が確立した。それ以降.売上高が順調に進展している。
販売台数の拡大とともにテスラの業績も飛躍的な伸長をみせている。その様子は図-2によって確認できる。
売上高の前年対比増加率は、2021年度は170%、2022年度は152%、2023年度は122%の予想だ。23年度は値下げの影響で営業利益が前期比で減少が見込まれている。
営業利益の推移は図-3によって確認できる。
テスラは温暖化ガス排出権の取引で巨額の収益を上げている。その額は22年4Qで15億ドルに達しているほどだ。販売した車のCO2排出量はEVの場合ゼロであり、従って排出基準量そのものがガソリン車を製造するメーカに対して排出権(クレジット)が売却可能な取引量になるわけだ。
このクレジット販売による収益が2020年度までは実質営業赤字をカバーして営業利益はやっとのことでプラスになるという状況が続いてきた。21年2Q以後は収益構造が大転換して、実質営業利益が順調に積み上がるようになった。21年3Q以後は営業利益率15%の高水準を継続的に叩き出せるようになった。19年の上海ギガファクトリーの稼働、21年のベルリンギガファクトリーの稼働が高収益構造を生み出す牽引力になったと言える。
つまりEV先進地域である中国と欧州という二大マーケットで強力な供給基盤を構築したことが収益力の改革につながったということだ。
このように順調な成長の軌跡を描いてきたテスラの戦略の秘密を次回明らかにしてみたい。
読書ノート 山本康正著『アフター ChatGPT』PHPビジネス新書
本書はChatGPTの超入門書と言えるでしょう。本書によって、次の疑問に対する回答を得ることができます。
l そもそも生成AIとは?
l これまでの識別系AIとは何が違うのか?
l 生成AIの誕生は何が契機だったのか?
l 生成AIで何が可能になるのか?
l 生成AIに限界はあるのか?
l 生成AIの得意分野と不得意分野は何か?
l 生成AIを使うには何から始めればよいのか?
l 生成AIによって駆逐される仕事は何か?
l 企業は生成AIをどのように使いこなせばよいのか?
l After ChatGPTの世界はどう変わるか?
以上の問題意識に対して、著者が用意してくれた回答を以下に拾い出してみましょう。
l 「(生成AIについて学ぶために)お勧めのものを一つだけ紹介すると、『AI for Everyone』というコースがあり、日本語でも受講できます。それらで学びながら、実際にStable Diffusionの微調整などをしてみたりすれば、費用をあまりかけずに学習できます」
l 「Chat GPTのような画期的なテクノロジーの登場は、いつの時代でも、それまでの価値観に揺さぶりをかけます。勤続年数や肩書と有能さが比例しないように、創業してからの歴史が長いからといって、その企業の価値観がこれからも通じ続けるとは限りません。積み重ねてきた信頼や伝統は確かに大切なアセット(資産)ですが、そこに固執してしまうと、ビジネスの存亡がかかった変曲点を見極められず、多くのものを失ってしまうリスクがあります。 歴史や伝統、従来の手法が、アセットではなく、負債や重荷になっていないか? 多くの企業が、一度立ち止まって見直すべき局面に来ているのかもしれません」。
l 「では、AIがどれだけ進化しようとも、生き残る可能性が高い仕事や業界は、一体どこにあるのでしょう? 答えはシンプルです。 日進月歩で進化するAIをうまく活用して、自ら価値を生み出せる人や組織が生き残るのです」。
l 「生成AIの解答や判断が100%正解であることはありえません。それどころか意外と大きなミスや、全く根拠不明な事実誤認も多いのです。 AIの性能が高くなれば誤った回答は減るでしょう。しかしどれだけ性能が高くなろうとも、大量のデータから確率に基づいて回答を生成する仕組みである限り、解答が100%正しいということは、なかなか難しいものです。 相当に高いレベルで「賢い」けれども、ある部分で未熟でもある。 このアンバランスさが、生成AIと向き合う際の今後の課題と言えるでしょう」。
l 「今後、生成AIがどのような進化を遂げていくのかはまだ誰にも分かりませんが、(『副操縦士』としての)生成AIを活用する『機長』であるために重要なポイントは次の2点です」。
Ø 最終チェックは、現時点では人間の役割
Ø 常に『差分』を問うスタンスを持つ (この点には解説が必要です。「差分を問うスタンス」というのは、これまでの進歩の軌跡を踏まえて、現在登場した技術がどのように位置づけられるのか、それが持続しないファッションであったり、一過性のファドに過ぎないのかという判断を下せる鑑定能力を養っておくことが必要だと思います)。
l 「(日本の強みが生きるのは『遊び』のサービスです)。日本におけるテクノロジーの歴史を振り返ると、効率性や合理主義が重視されるアメリカとは異なる、独自のユニークさがあることに気づきます。それは『遊び』の領域から技術が発展していく点です。 2023年5月、LINEはChatGPTとのコラボレーションで、好きなAIキャラクターを作成し、会話ができるサービス『ドリームフレンド』をリリースしました。AIで作ったオリジナルキャラクターと会話し、育成できるというユニークなサービスです。こうした発想は、漫画やアニメが多い日本に生まれやすいでしょう」。
いずれにしても、ChatGPTは企業にとっても、個人にとっても活用を迫られている技術であることは間違いないようです。であるならまずは大胆に活用モードに踏み込んでみるしかないでしょう。 「習うより、慣れろ」の教訓がここでも活きてきます。
なおこの文章はChatGPTに校正を依頼しました。
「いずれにしろ」の表記をChatGPTは「いづれにしろ」と書き換えて返信してきましたが、元の通りのままとしました。
キーエンスの戦略ストーリー(最終回)
キーエンスの戦略ストーリーの分析もいよいよ佳境に入ってきた。最終回の今回の目標はキーエンスの並外れた営業力の姿を深掘りすることだ。キーエンスの並外れた営業力は下記の第5図に示される。
並外れた営業力にとって必要とされるのはまずもって顧客の期待を超える提案が継続的に提供されるということだ。
そうなれば顧客はキーエンスが来訪してくるたびに何か面白い提案がありそうだというワクワク感で満たされるはずだ。
こうした状況はキーエンスが代理店を使わずキーエンスの営業が直接顧客を訪問するから可能になる。そして直販で常に顧客の期待を超える提案をするためにさらに重要なことは、営業担当者が並外れたコンサルティング能力を持つことだ。
営業担当者が並外れたコンサルティング能力を持つことができるには次の五つの条件を備えることが前提となる。
1. 提案による改善効果を顧客にとっての利益額で測定し提示することができること
2. デモ機を活用し顧客の目の前で実現性をアピールすることができること
3. 他社事例を熟知し他社での成功事例を横展開できること
4. 営業の生産性が並外れて高く、期待以上のスピードで課題解決が可能になること
ひとつひとつ見ていこう。
提案による改善効果を顧客にとっての利益額で測定し提示する
キーエンスの営業担当者が顧客の製造部門、開発部門、研究部門の現場を熟知していれば、現場の抱える課題解決が利益額としてどの程度になるかを推計することが可能になる。
例えば提案するソリューションが顧客にとってどれだけの歩留まり向上につながるか、稼働率の向上につながるか、人員削減につながるかが推計できれば、その結果から利益額をシミュレートできる。これが可能になるほどにキーエンスの営業担当者は顧客の現場を熟知しているということだ。
キーエンスの営業はなぜこれが可能なのか。まずは営業が顧客の現場にしょっちゅうといっていいほど入り込み、観察し、実態を知り尽くしているから可能なのだ。加えて現場課題に関する膨大な他社顧客の事例がいつでも利用可能な状態で収集・蓄積されているからだ。
デモ機を活用し顧客の目の前で実現性をアピールすることができること
ソリューション提供の手段となる自社商品の価値を顧客にアピールするために最も効果的な方法はデモ機を持参して、商談の場で実際に動かして見せて、その価値を体験してもらうことだ。
カタログや動画視聴とは比べものにならないインパクトがあるはずだ。思わずその場で購入を即決してくれるかもしれない。
そしてキーエンスの営業がデモ機を顧客にとって魅力的に魅せることができるのは、自社商品の魅力、特徴、能力、技術的背景を確実に知悉し、しかもこれを顧客がどのように活用してもらえばデモ機が最も効果を生むのか、を熟慮した上でデモ機のデモンストレーションを実行するからなのだ。
他社事例を熟知し他社での成功事例を横展開できること
顧客は他社の内部事情について詳細に知る機会は持っていない。キーエンスの営業は同業の現場に入りこんで実態を熟知している。自分が見てはいなくても同僚が観察した知見をデータベース化しているから、あたかも自分が見てきたかのように語ることができる。
さらに大事なことは営業を支援する販促スタッフの存在があることだ。営業が最適なソリューションを提案できない状況で困っているときに、営業に寄り添い一緒になってソリューションを考えてくれるスタッフの存在が営業のソリューション提案力を大きく拡張してくれるというわけだ。この販促スタッフこそ他社事例の横展開を実行する上で不可欠なのだ。
営業の生産性が並外れて高く、期待以上のスピードで課題解決が可能になること
営業は顧客の課題に何よりもスピード優先でソリューション提案を実行することが求められる。この業務スピードが並外れた生産性を実現している。
1日に5〜10の訪問件数という営業の生産性の高さは営業活動の標準の徹底によって支えられている。
営業の行動基準は分刻みでの日次活動計画の策定、活動計画に対する上司のアドバイス、必要に応じてのロープレ実施、そして帰社してからの顧客訪問報告、さらには上司による訪問した顧客に対するフォローの電話(「ハッピーコール」と呼ばれている)を骨格として組み立てられている。
またこの行動基準を効果的、効率的に実施するための使いやすいツールも備わっている。
営業支援ツールとしては以下のものがある。
・外出計画所
・外出報告書
・工程ハンドブック
・お役立ち事例集
・ニーズカード
・会員制サイト
また他社事例の横展開のところで見たように、営業の活動標準とともに営業をサポートする販促スタッフの存在も営業の並外れた生産性に貢献していることは言うまでもない。
そして顧客訪問報告はデータベースに記録され、社員全員で共有され、これまで見てきたように新商品企画、ソリューション事例の横展開など新たな付加価値を産み続ける情報資源として縦横に活用されることになる。
以上でキーエンスの並外れた業績の秘密のすべてが明らかにされた。
その根幹を一言で言えば、「徹底した従業員満足の追求」、そして従業員満足をとことん追求するための「徹底した顧客満足の追求」ということになる。
つまりはまさに「日本的経営」の徹底に尽きるということであった。
キーエンスの戦略ストーリー(その4)
キーエンスの並外れた新商品企画開発能力について見ていこう。
キーエンスの並外れた新製品企画開発能力を実現する戦略ストーリーは第4図のように表現される。
世界初、業界初のヒット商品
キーエンスの新商品企画開発部門においては「世界初、業界初のヒット商品の開発」が行動規範としてわきまえられている。
だから顧客が欲しいという商品には見向きもしない。顧客が欲しいという場合それは顕在化したニーズであって、それに応えても圧倒的な付加価値は産まれない。
なぜなら顧客が欲しいと言葉に出した途端に競合メーカーがそれを受けて企画開発の行動を起こしているかもしれない。そのようなところにノコノコ出て行ってもレッドオーシャンの中で溺れるだけだ。
また顧客が欲しいという商品は特定の領域にある顧客にだけニーズが限られていて、大きな需要創造には結びつかないかもしれない。
ゆえにキーエンスが企画開発を目指すのは、顧客がまだ気づいていない潜在ニーズに根差す課題であって、しかも先端技術を活用することで解決がようやく可能となる課題、さらにはそのニーズが多くの顧客が同時に抱えている困難の解決に役立つ課題の解決ということになる。
こうした要件定義を満足した課題だけがはじめて企画開発の俎上にのることになる。
顧客の潜在ニーズの先鋭化
さて最先端技術と潜在ニーズの結合によって初めて解決可能な課題解決が世界初、業界初の新商品の前提であるとした上で、まずもって行うべきことは顧客の潜在ニーズをより鋭く尖らせるということだ。潜在ニーズを先鋭化は顧客の現場の困りごとを深く掘り下げて理解することで可能になる。
現場の困りごとの深掘りを実施するためには、顧客現場の深い理解が前提になる。そのためには顧客の現場情報が広範囲にしかも詳細に収集され蓄積されていて、それがいつでも必要なときに必要な形で取り出せる仕掛けが情報システムによって完備されていなければならない。
また潜在ニーズの先鋭化のためには優れた経験と知識を持つ企画担当者に活躍してもらわなければならない。
新商品企画の成功の鍵は専任企画担当者
企画担当者はソリューション提案のための課題についてのより深い理解を得るために、顧客を頻繁に訪問し、仮説検証を現場に根ざして実行することが求められる。
ここでの仮説検証は具体的には次の点を解明することだ。
• 課題、困りごとの実態はどのようなものか
• それは提案したコンセプトで解決可能か
• 提案ソリューションは買ってもらえるか
• いくらで買ってもらえるか
• なぜその値段なのか→効果の金額評価
またこうした企画担当者が大きな成果を獲得することを保障するには次のことが不可欠となる。
• 社長の仕事にしない
• 継続して担当する
• 一人で推進する
• 同じ人が続けない
• 兼任にしない
そして開発実施が意思決定されたのちの開発体制の要件は、
第一に企画担当者が開発プロジェクトのリーダーを務めること、
第二に開発プロジェクトチームには営業、開発、製造のメンバーを含めて全社横断的なプロジェクトにすることである。
マスカスタマイゼーション
ところで最先端技術と潜在ニーズの結合によって初めて解決可能なソリューションは、多くの顧客が抱える潜在ニーズに対する解決策提案でなくてはならない。つまり新商品は多くの需要を満たす標準品であることで、提供する付加価値を拡大し、同時に提供コストを削減する商品ということになる。
キーエンスではこうしたソリューション提案システムを「マスカスタマイゼーション」と名付けている。
「大量」生産品でありながら「個別」のニーズを満たすという絶妙のネーミングだ。
多くの顧客にとってまさに「うち」が欲しかった製品だと満足していただきながら、キーエンスにとっては「標準品」=「大量生産品」を提供するに過ぎないという、キーエンスの商品の並外れて優れたコンセプトを表現している。
多種類のマスカスタマイゼーション商品を開発し、製造するためにキーエンスは協力工場に全商品の90%を製造委託している。そしてこれらのOEM工場の品質、コスト、生産性、納期の完璧な保証を期すために、キーエンス自身が製造技術、設備技術に磨きをかけて、OEM工場を指導し、支援する体制を維持する必要がある。
そのためにキーエンスは自社工場を、マザー工場として位置付け運営している。
マザー工場ではカタログ掲載商品を大量生産する傍ら、製造技術開発、製造設備開発、試作品試作、量産化ライン開発などの機能を受け持っている。
こうした備えがあってはじめてキーエンスの「マスかスタマイゼーション」が完璧なものになっているといえるのだ。
キーエンスの戦略ストーリー(その3) 並外れたSCM能力
キーエンスの並外れたSCMについて見ていこう。
キーエンスの並外れたSCM能力を実現する戦略ストーリーは第3図のように表現される。
第3図
顧客の設備停止時間短縮への貢献
キーエンスでは「顧客の設備故障停止時間短縮への貢献」を可能にすることが、並外れたSCM能力を獲得することに繋がると考えられている。
納入した機器やセンサーが故障によって万が一にも設備を停止することがあってはならない。
故障の発生を事前に予知できれば、故障停止以前に代替機やセンサー部品を即納してことなきを得ることに備えることが可能だ。
万が一故障大使が起きてしまった後でも、いかにスピーディに代替機やセンサー部品を納入することが顧客の付加価値額を削ることに繋がらない決め手となるはずだ。
つまり機器であれば代替機を即納する、センサーであれば代替センサーを即納することが顧客の損失をゼロにしたり、最低限に抑えるために必要な要件になる。
顧客での製品の使用状況のデータベース化
また代替機であれセンサーであれそれがどのような環境で、どのような使われ方をされているのかが分かれば、代替機の設定や付加機能の追加が短時間で容易になり、しかも納品してすぐにラインに投入され使用できる状態が作れる。
このためには機器やセンサーを納入した顧客に対する顧客情報が完璧な形で収集、蓄積されていなければならない。
全品在庫だから即納
また即納体制のためには機器やセンサーが全て在庫として保有されていることが求められる。この要件を満たすためには自社工場だけでは到底賄いきれない。
全商品の在庫を保持するためには協力工場に製造を委託し、製品の全品在庫をしてもらうことが合理的だ。
いやむしろ製造プロセスは協力工場への委託に任せて、自社は商品企画と開発に専念する体制が並外れたSCM能力を獲得する上で最も合理的なあるべき姿になる。
こうしてキーエンスはファブレス企業としてのビジネスモデルを整えることになった。
ただキーエンスは製造機能を完全に外部に委ねるのではなく、自社工場も構えて全商品の10%程度を製造している。自社工場では新商品の試作や、品質保証と製造コストの低減のための製造プロセスの持続的進化への取り組みが行われ、自社工場はマザー工場として位置付けられている。
キーエンスの戦略ストーリー その2
キーエンスの高業績の理由はその優れた戦略ストーリーにある。
キーエンスの戦略ストーリーは下の図のように表現できる。
「戦略ストーリー」とは
筆者の考える戦略ストーリーの構成は、
Mission→Vision→Objectives→KFS(Key Factor for Success)であり、
それぞれは因果関係(結果→原因)で結ばれている。
上の図はこの型によって作成されている。
この戦略ストーリーの型は筆者が一橋大学教授の楠木建氏著『ストーリーとしての競争戦略』に触発されて独自に構想したメソッドである。
また以下に述べるキーエンスの戦略ストーリーはこれまた筆者の独断で構想したものであり、キーエンス社の見解を解説するものでないことを予めお断りしておく。
なお本稿を作成するにあたって参考にした資料は下記のとおり。
延岡健太郎著『キーエンス高付加価値経営の論理』日本経済新聞出版
西丘杏著『キーエンス解剖』日経BP
キーエンスの「ミッション」
ミッションは企業の存在理由を定義する。企業が最終的にどのような形で社会貢献するかを表現しているのがミッションだ。
キーエンス社のミッションは「日本一給与の高い会社にする」ということだ。
とてもシンプルでわかりやすい。従業員の仕事に最高の形で応える会社を作るという創業者の意思が簡潔に表現されている。
このミッションを実現するための具体的な方法、あるいは中期的なあるべき姿を示すのがビジョンだ。
キーエンスの「ビジョン」
キーエンスのビジョンは「モノではなく、課題解決を売る」と定義されている。
給与の高い業種の筆頭はコンサルタント会社会社だ。彼らはモノではなく課題解決を売っている。したがって製造業ではなくコンサルタント業を目指せば給与の高い会社になることが可能だ。モノは課題解決のための手段の一つということになる。
ビジョンの実現のための具体的目標がオブジェクティブズだ。
キーエンスの「オブジェクティブズ」
キーエンスの場合オブジェクティブズとして「粗利率の目標を80%と設定する」ということを掲げた。
では「粗利率を80%にする」には何が必要なのだろうか。この目標実現に向けての具体的な打ち手を示すのがKFSだ。ここから戦略ストーリーがいよいよ本格的に展開される。
キーエンスのKFS
キーエンスでは粗利率80%の実現のためには、何よりも「顧客の付加価値の最大化に貢献する」ことが最も大事なことだということに気づいた。
自分本位に粗利率を80%にすることを求めても、顧客が納得するソリューションでなければ見向きもされない。提案したソリューションが顧客にとって、原材料コストの削減や、生産性の向上に繋がり、結果として付加価値の拡大を実現してはじめて受け入れてもらえる。
そのためには何が必要か。
「顧客の潜在ニーズ対応のソリューション提案」をすることにほかならない。
顧客が気づいている顕在化したニーズに応えるのはあたりまえの対応でしかない。そのような対応は気の利いたメーカーならどこでも可能だ。
顧客さえもが気づいていない潜在的なニーズを掘り起こして、このニーズを満たすソリューションに対してなら、顧客は喜んで言いなりの対価を払っても惜しくはない。
それができれば自社の粗利率80%が自然と実現するというわけだ。
さらに続けて「潜在ニーズ対応の課題解決提案」はいかにして可能になるか。大きくは三つの並外れた能力を獲得することが求められる。
その三つの能力とは、
「並外れたSCM」
「並外れた商品(付加価値)開発力」
「並外れた営業力」だ。
それぞれについて次回以降、順次解説していこう。
キーエンスの戦略ストーリー(その1)
キーエンスの業績は相変わらず桁外れに優れている。
2023年3月期の業績数字を確認してみよう。
|
第1表 キーエンス業績指標 |
|
|
売上高 |
9,224億円 |
|
売上総利益 |
7,547億円 |
|
営業利益 |
4,989億円 |
|
経常利益 |
5,128億円 |
|
当期純利益 |
3,830億円 |
|
総資産 |
2兆6,504億円 |
|
純資産 |
2兆4,916億円 |
|
第2表 キーエンス業績指標 |
|
|
粗利率 |
81.8% |
|
営業利益率 |
54.1% |
|
経常利益率 |
55.6% |
|
純利益率 |
41.5% |
|
自己資本比率 |
94.0% |
輝かしい数字ばかりが並ぶ。
この業績の結果は高株価をもたらし、キーエンスの株式時価総額は23年7月24日時点で、国内上場企業の第3位にランキングされて、今やソニーに迫る勢いだ。
|
第3表 時価総額ランキング |
||
|
|
時価総額 |
売上高 |
|
トヨタ自動車 |
37兆4,205億円 |
37兆1,543億円 |
|
ソニーグループ |
16兆5,391億円 |
11兆5,398億円 |
|
キーエンス |
16兆1,222億円 |
9,224億円 |
また各社の時価総額と売上高を比較してみよう。
トヨタとソニーの時価総額は売上高にほぼ準ずる規模感である。しかしキーエンスの時価総額は売上高の規模に比較して約16倍の規模に達している。つまりキーエンスンの時価総額は並外れた水準に達しており、それが株主からの評価に繋がっているということができる。
キーエンスの高業績は従業員の給与にも反映されている。
|
第4表従業員平均年収ランキング |
|
|
M&Aキャピタル・パートナーズ |
3,161万円 |
|
キーエンス |
2,279万円 |
|
三菱商事 |
1,939万円 |
|
ヒューリック |
1,904万円 |
|
伊藤忠商事 |
1,730万円 |
|
東京エレクトロン |
1,299万円 |
キーエンスには営業利益の15%相当を業績賞与として従業員に配分するという報酬制度がある。高業績が継続した結果として従業員の平均年収は2,279万円という上場大企業では並外れた高水準に達している。
従業員の報酬が高いとされる三菱商事でさえ平均年収は1,939万円でキーセンスはこれをはるかに超えている。製造業の中で最も年収の高い東京エレクトロンの平均年収は1,229万円であるので、国内製造業の中ではキーエンスの給与水準はとびきり高い水準にあると言える。
このようなキーエンスの高業績がどのような戦略ストーリーによって実現できたのだろうか。次回以降で考えてみたい。
世界競争力ランキングで日本はなんと35位
スイス・ローザンヌに拠点を置くビジネススクール・国際経営開発研究所 (IMD) が2023年の「世界競争力ランキング」を発表した。
「世界競争力ランキング」は2022年の63カ国に新たにクウェートを加えた世界64カ国を対象に、「企業がビジネスでどれだけ競争力を発揮しやすい環境が整っているか」を順位付けした調査だ。
この調査は、IMDが57の提携機関とともに収集した164の統計データと、6400人の世界の上級経営陣から寄せられた92の質問に対する回答をもとに、『経済状況(パフォーマンス)』『政府の効率性』『ビジネスの効率性』『インフラ』の4つの指標について、合計336の項目に基づき評価されている」。
以下に『株式会社やまとごころ』のwebページ(https://yamatogokoro.jp/inbound_data/50650/)に掲載された記事を参考にして「世界競争力ランキング」の実態を確認してみたい。
さて20位までのランキングは次の通りだ。
1位から3位に入った上位3カ国の詳細
「1位のデンマークは、「ビジネスの効率性」で1位、「インフラ」で2位を獲得。「政府の効率性」の順位も、6位から5位へとわずかながら上昇した。
2位のアイルランドは、「経済状況」の指標で、昨年の7位から1位へと大きく順位を上げたことや、「政府の効率性」「ビジネスの効率性」が昨年の11位から3位へと上昇したことで、全体の順位も11位から2位へと急躍進した。
スイスが3位を維持したのも、デンマークと同様、すべての指標についてよい結果を出しているためだ。なかでも「政府の効率性」と「インフラ」で、昨年に引き続き1位を堅持。「ビジネスの効率性」は昨年の4位から7位へと低下、「経済状況」は昨年の30位から18位へと上昇している」。
上位3カ国は共通して「政府の効率性」「インフラ」「企業の効率性」が際立った優位性を保持している。その背景としてDXの進展が圧倒的な効率性の要因として浮かび上がっている。
日本は35位
ところで日本は65カ国中の35位。しかも昨年よりワンランク落としている。この調査の開始から96年まではずっと5位以内を維持してきたが、97年以降順位が下がり続けての35位だ。
指標別の順位では、「経済状況」が26位(前年は20位)、「政府の効率性」が42位(同39位)、「ビジネスの効率性」が47位(同51位)、「インフラ」が23位(同22位)という結果だった。
30年続く不況が競争力低下の背景として作用し、それに輪をかける形でDX化の遅れが競争力の足を引っ張る形が浮かび上がる。
30年競争力の低下の要因は円安政策
一橋大学名誉教授の野口悠紀雄氏によれば日本の競争力の対価の根本要因は円安政策に求められる(https://diamond.jp/articles/-/326703)。
円安政策の端緒が96年であり、その後一貫として円安政策が続いたことと、競争力の低下が96年以降顕著に進行したということが符合することからもこの因果関係は納得できる。
円安政策の目的は戦後の高度経済成長を支えた輸出立国政策の延長上で理解できる。92年のバブル崩壊後のデフレ局面からの離脱を輸出の拡大によって実現しようとする意図のもとで円安誘導が現実化したのだ。
しかしこの円安政策は日本の輸出産業にとってはさしたる企業努力をしないでも売上高が拡大し、利益が増加するというぬるま湯環境を用意してしまった。この輸出企業にとって「最適」な湯加減の中で輸出企業は本来的な競争力の源泉となるイノベーションを怠るという致命的なリスクを犯し続けることになった。
競争力低下に輪をかけたDXの遅れ
円安政策による競争力の低下に輪をかけたのがDXの遅れであった。ビジネス領域でのDXの遅れはビジネスの効率性を阻害するとともにデジタル技術を活用しての新基軸の価値創造というイノベーションの阻害要因ともなった。
また中央政府ならびに自治体領域でのDXの遅れはより顕著であって、それがビジネス領域の効率化を加速的に阻害する要因ともなった、
今後競争力の増大に加速度をつけることが要請されている。そのためにはまず持って円安政策からの離脱が不可欠となる。円安政策からの離脱が企業環境をぬるま湯状況から、厳しい競争世界へと転換させることになる。いわば茹でガエル状況からの離脱だ。
厳しい環境の中で企業は必死になってデジタル技術を活用し、新規製品、新サービス、新素材、新市場、新技術を生み出すイノベーションエを次々に創生する道を拓いていくようになるはずだ。
在宅勤務日は従業員に選ばせず、マネジャーが指定すべき
コロナ禍は在宅勤務を日常的なものにした。
この大転換は世界中で一気に浸透した。
そしてコロナ禍が沈静化した後も在宅勤務は継続している。
とはいえ在宅勤務のやり方には多様性が生まれている。
週に何日を在宅勤務日とするか、在宅勤務日は出勤が強制されるか否か、
という点についての多様性が生まれている。
一般的な傾向としては、
・在宅勤務日を週に2日とか3日とかを決める
・在宅勤務日は従業員が自ら決める
・在宅勤務日に出勤するかしないかも従業員が決める
となっているようだ。
ところで、
スタンフォード大学ニコラス・ブルーム教授は在宅勤務日はマネジャーが指定すべきだと主張している。
(https://dhbr.diamond.jp/articles/-/7808)
「在宅勤務をする日は従業員が選ぶのではなく、むしろ選ばないほうがよいと助言している」。
在役勤務日を従業員の自由に任すと二つの懸念事項が生まれるという。
「第1の懸念事項は、在宅勤務とオフィス勤務が混在するハイブリッドチームを管理する難しさである。
オフィスにいるイン・グループと在宅のアウト・グループの2グループに分かれることへの不安は尽きることがない」。
オフィスに出る人が固定化し、その人たちの間での情報共有が進み、
他のメンバーとの隔絶が大きくなるという懸念だ。
「第2の懸念事項として、ダイバーシティに対するリスクがある。
パンデミック後に在宅勤務したいと考えているのはランダムではなく、
特定グループの従業員であることが明らかになっている。
たとえば、筆者らの共同研究では、小さな子どもを持つ大卒者のうち、
フルタイムで在宅勤務をしたいと考えている女性は男性よりも50%近く多い。
同僚がオフィスで勤務している時に在宅勤務をするのは、
キャリアに深刻なダメージをもたらしかねないというエビデンスがあることを考えれば、
これは憂慮すべき事態である」。
つまりマネジャーは往々にして、
在宅勤務を取る日数が多い従業員の評価に不利な判断をしがち、
という現実がある。
これは在宅勤務をより多く取ることを希望する女性にとっては、
在宅勤務の取得が自由な環境はキャリア形成に不利に作用するということだ。
この二つの懸念を取り除くには、以下のルールが必要になる。
・在宅勤務日はマネジャーが指定する
・在宅勤務日には必ずオフィスに出勤する
このやり方によって在宅勤務の採用によってオフィスが縮小し、
全員の出勤に耐えられなくなった場合の出勤人数の調整が
可能にもなるという副次効果も期待できる。
人的資本はどのようなKPIで表現されるか
働く人をコストではなく、価値を生み出す源泉ととらえる「人的資本」の開示が、2023年3月期の有価証券報告書から上場企業に義務化される。
日経新聞の2023/03/06「オピニオン」では人的資本の開示のユニークな事例を紹介している。
(「人的資本、ユニーク開示続々」上級論説委員 西條 都夫)
この記事では次の事例が紹介されている。
l 職場の推奨率
Ø 北国フィナンシャルホールディングス(FHD)が採用している。「あなたの職場で働くことを、親しい友人や知人にどの程度お薦めしますか」と従業員に質問し、「とてもお薦め」という前向きの答えから、「絶対に薦めたくない」といったネガティブな答えを引き算した値で測定している
l エンゲイジメント
Ø 「仕事にやりがいを感じる」「この会社で働けてよかった」などの質問で仕事や仕事に関わる環境に対する満足度を従業員に問いかけ測定する。ダスキン、京セラ、出光興産は世代別の開示も行っている
l 出生率
Ø 伊藤忠商事は22年4月に働き方改革の成果として、同社の女性社員の合計特殊出生率の推移を公表した
l 新卒離職率
Ø 若年離職率の低い企業は、建前と実態の隔たりの小さい、嘘のない会社といえる。会社の人事部の言葉が信用に足るのか、迷う学生にとっても、意味ある指針になろう。
以上の例示に触発されて筆者も人的資本指標をいくつか考えて見た。
l 付加価値生産性 従業員一人当たりの付加価値額を測定する。ただし従業員数は変動するので工夫が必要になる
l 従業員提案件数
Ø 仕事、職場環境、人事制度、提供する価値などに対する改善提案の件数を測定する。提案制度が導入されている企業では当たり前に測定されている。提案がどれだけ課題化され、実行されたかの追跡データがあればなお良い指標になる
l 有給休暇取得率
Ø ワークライフバランスに対する配慮が行き届いてはじめて人的資本の活用が実効性をあげるという観点で有効ではないか
l スキルアップ・トレーニング時間
Ø スキルアップのために勤務時間のうちどれだけの時間を割いたかを測定する これも一人当たりの時間が測定できると良い
どのような指標を開示するかは、経営者が人的資本の活用をどのような形で実現しようとしているかを端的に表現することになる。
つまり人的資本の開示によって経営者は人材に期待する価値観が問われることに他ならない。
米国では製造業が復活しつつある
フィナンシャル・タイムスのグローバル・ビジネス・コラムニスト、ラナ・フォルーハー氏が日経新聞10月7日に「米国で復権する製造業」と題するコラムを執筆している。
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221007&ng=DGKKZO64938650W2A001C2TCR000
新型コロナウイルス禍後の米国では、製造業の復活が大きく広がっている。
米自動車メーカーはコロナ下で136万人の労働者を解雇したが、8月の統計によるとそれ以降143万人が新たに雇用されており、雇用者数はコロナ前に比べ6万7000人増えた。こうした雇用増は地域や業界を問わず全米に広くみられる。
製造業の健闘を支えるのは次のような環境変化だ。
・ バイデン政権の「バイ・アメリカーナ」政策の浸透
・ 海外からの輸送費の高騰
・ 中国とのデカップリング政策の進行
・ 中国はじめとした発展途上国での賃金上昇
これらの一般的要因とは別に、ラナ・フォルーハー氏が注目しているのは米国の「家族経営を中心とする非公開の米中堅メーカーの秘められた底力だ」。
「コンサルティング大手、米マッキンゼー・アンド・カンパニーの北米マネージングパートナー、アストシュ・パディ氏らが執筆した著書「The Titanium Economy(チタン経済、米国で近日刊行予定)」はこれまで過小評価されてきたにもかかわらず力強い業績を上げてきた米国の中堅メーカーに焦点を当てている。
同書によるとこうした中堅メーカーのプロフィールは以下の通り。
・ 80%が非公開企業
・ 年間売上高が10億~100億ドル(約1400億~1兆4000億円)程度
・ 従業員は2000人から2万人
・ 2013~18年の売上高の年平均成長率は4.2%で同期間のS&P500種株価指数の伸び率を1.3ポイント上回る
・ 自動車や携帯電話、宝飾品、スポーツ用品、医療器具など見渡せば目にするあらゆるものを製造する
・ ベンチャーキャピタルによる資金調達の割合は1%に満たない
・ 給与はサービス部門に比べ2倍以上に上る(中堅製造業の年間6万3000ドルに対しサービスは3万ドル)
・ あらゆる職種で採用募集件数が最も多く、その範囲は米国全土に広がっている。
では、なぜ見過ごされがちなこうした企業はこれだけの成長を遂げているのか。
・ 長期的な視野に基づく経営ができる。非公開企業による研究開発(R&D)や研修など長期的な生産的設備投資の額は似たような上場企業の2倍にのぼる
・ 最新の製造技術に投資し、製造工程で無駄を省く「リーン生産方式」を導入して品質と生産性を向上させ、迅速な技術革新と的確なリスク管理のため地元のサプライチェーンを活用し同業で最も優秀な企業になっている
・ 世界に冠たるドイツや日本の手法を熟知し、技術者や研究者、労働者、管理職などが緊密に協働する結束力の強いチームをつくることで最良の結果を得ている
・ エネルギーコストが低い利点やロシアのウクライナ侵攻による混乱を避けるためを狙って米国に事業拠点を移す欧州の企業との協業関係を構築しつつある
米国の製造業が従業員第一、顧客第二の日本的経営のエッセンスに学んで独自の変身を遂げて今復活しつつある反面、日本の製造業は往年の輝きを喪失している。
その要因は次の二つだ。
・ 株主資本主義の洗礼を受け、過剰な適応を迫られ、あるいは積極的にそれを受容して往年の輝きを喪失した
・ アベノミクスによる円安と法人税減税政策に依存していたずらにあぶく銭を積み上げた
この結果として日本の製造業は次のような悪手を積み上げて、惨状を晒すことになった。
・ 円安による水膨れがもたらした売上高と営業利益の増加に安住した
・ 従業員に対する成長のための投資を怠った
・ 持続的な成長のための研究開発、技術革新投資を怠った
・ 内需に対する供給責任を放棄し、海外へ製造拠点を移した
・ 結果として新規の顧客価値創造が滞り持続的な成長の要因を喪失した
この惨状からの起死回生の道は製造プロセスの国内回帰を実行するほかはない。
その道筋は次のようなものになるはずだ。
・ 国内設備投資が拡大
Ø もちろん粋を極めた新規技術が追求される
・ 求人が増加
Ø 新技術に適応するスキル更新のための人材投資が前提になる
・ 給与が上昇し
Ø 労働生産性の向上が前提となる
・ 内需が拡大する
Ø 輸入品から国産品への置換が乗数効果をもたらす
以上の経路で好循環が生まれ、日本製造業に復活の兆しが現れるに違いない。
リスキリングの成功要因を考える
学び直しによって人材価値を拡大し、業務の生産性を上げるリスキリングに
政府は5年で1兆円の投資を実行するという。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65088890T11C22A0MM8000/
リスキリングの中心技術はデジタル技術になるであろうが、
リスキリングの効果は企業がデジタル技術をどのように活用するかの戦略によって大きく左右される。
企業のデジタル技術の活用の分野はほぼ次の3類型に集約される。
・デジタル技術を活用する新規事業を開発する
・既存事業のビジネスモデルをデジタル技術を活用して革新する
・既存事業の運営やマネジメントをデジタル技術を活用して革新する
デジタル技術の活用によるこうした企業革新の目的を明確に設定し、
加えてその目的の実現のゴールにあるあるべき姿を描くことが
何よりも先に求められる
こうした戦略の策定を行なってはじめてリスキリングのニーズが具体的に明らかになるはずだ。
こうした手順によらず政府が主導するリスキリングの流行に悪ノリするだけでは
大きな成果は望むべくもない。
「カテナX」はオープン・イノベーションのプラットフォームでもある
欧州はデータ収集や企業間連携の世界でGAFAMに対抗するプラットフォームを構築する独自の動きが進んでいるようだ。(日経新聞10月4日「ドイツカテナに勝てるか」https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221004&ng=DGKKZO64826870T01C22A0TCR000)
ドイツで一部稼働した自動車産業の官民プラットフォーム「カテナX」がその典型例だ。
「部品の受発注から設計、デザイン、決済まで現実世界でやってきた工程をサイバー空間に段階的に移転し、産業構造を一変させるという。
カテナはラテン語で『鎖』。その名の通り、世界中のサプライヤーやIT企業、金融機関などをつなぐ一方、モノの動きをデジタルツインで連携して、車1台1台が材料の段階から廃棄される瞬間までを記録してもいく。
最終形は『万能工場』だという。『顧客にほしい車を届ける』を起点にして、最も早く生産し、届けられる完成車工場に、価格と技術面で最も適したサプライヤーが部品やシステムを納める。
特徴は競争領域、協調領域、ルール領域の3層に企業活動を再編する点だ。日本勢の得意なすり合わせや系列取引が持つ強みを協調領域にしてしまう可能性もある」。
EVが自動車産業の主流になれば、精密なすり合わせの必要性は下がり、協調領域の自由度は拡大し、自動車企業は自社の競争優位を確保するための企画、開発に鎬を削ることになるだろう。
「欧州の伝統的に得意なルール形成の力、すなわちデジュール(政策的な標準化)戦略とも一体で動いており、二酸化炭素(CO2)排出や経済安全保障に関する情報開示をカテナXとひもづけていく可能性もある」。
こうした欧州の自動車産業の動きはテスラ社の戦略と比較するとまさに正反対の方向を示している。テスラはソフト、ハード両面で自社開発を基本方針としている。EVを制御するOS
をはじめとして電池や半導体すら自前で開発し、自社工場で生産している。
テスラは自前主義に固執することで、製品の継続的な進化そしてイノベーションを加速させることを目論んでいるように見える。
EVは個車のデータを常時収集し、このデータを活用して製品の改善、進化を常態化し、その累積がイノベーションに繋がる。テスラはこれまでの自動車には考えられなかったEVのこの特徴を完璧にそしてアジャイルに実現することを目指して完全自前主義にこだわっているように思える。
これに対してドイツのカテナは製品の改善、進化をオープン・イノベーション方式で実現する道を選択したと言えるだろう。「三人寄れば文殊の知恵」がカテナによって生まれるのだ。もちろん改善、進化のニーズは消費者との接点を持つ完成車メーカーが提出し、それに部品メーカー、ソフト開発社が答えることになるだろう。
さらには部品やソフトの製造企業自身も自らの生産物のコストダウンや品質改善に独自の改善、進化を目指すことになり、ここでも文殊の知恵が生まれることになるはずだ。
いずれの方式がより大きな付加価値を生み出すだろうか。
人類の文明は分業によって進化してきたとするなら、カテナ方式に軍配が上がると見るべきかもしれない。
日本はここでもまた周回遅れの惨状を呈している。
少なくとも「カテナX」に積極的に参加して、個社では実現できないオープン・イノベーションの一翼を担う取り組みを一刻も早く進めるべきだ。

リモートワークで働き方の自律性と秩序を両立する方法
COVID-19によるパンデミックは働き方を大きく変えた。リモート勤務が常態化したことだ。
従業員はリモート勤務を経験して、その時間と場所の制約から自由な働き方に魅了され、もはや手放しがたい勤務形態になっている。
しかしパンデミックが収束を迎えて、企業は規律と協働を求める観点からリモート勤務に制限を求め始めている。従来の在社勤務に全面的に戻ることは無理としても、リモートと在社の両立を目指しつつある。
このハイブリッド型の勤務形態こそがこれからの主流となって行くだろう。
ではハイブリッド型勤務形態の成功要因(Key Success Factor)は何だろう。
Harvard Business Review Online 6月30日号に掲載された
がこの疑問に答えている。
ハイブリッド型勤務はなぜ求められるのか
従業員はリモート勤務によって働く時間と場所の制約から自由な働き方を手に入れた。リモートであれば在宅に限らず好きな時間に好きな場所での働くことができる。
企業にとってもリモート勤務は従業員の仕事に向かう自律性を拡充し、しかもそのことが生産性を高めることに気づき始めている。
一方リモートワークによって希薄化されてしまうのが組織に対する帰属意識とそれに基づく協働の効果だ。
この二つのコンフリクトを解消するために企業はハイブリッド型の勤務形態を求め、それが今や大きな流れになろうとしている。
しかし企業はオフィスワークに従業員をやみくもに引き戻すだけでは従業員が積極的にハイブリッド型に帰還する状況を作ることはできない。
その前にやることが三つある。
ハイブリッド型勤務形態の成功要因
しかしハイブリッド型勤務形態を成功に導く要因があるはずだ。HBRの論文では三つ提示されている。基本的には何よりも従業員がオッフィスワークを積極的に選択したくなるように、オフィスのリモートワーク環境を整える投資を実行することだ。
1. いかなる場所でも音と視覚のプライバシーを考慮することだ。
「筆者らのデータでは、従業員が好むのは視覚のプライバシー(39%)よりも、音のプライバシー(61%)がある場所だ。つまり、仕事場の外にいる人が見える、または外から見られる場所よりも、外の声が聞こえない、または外から聞かれない場所での仕事を好む」。
2. プロフェッショナル用オーディオ機器の提供
「筆者らのデータでは、一般消費者向けのオーディオ機器や、ノートPC内蔵のマイクとスピーカーを使う人に比べ、プロフェッショナル用のオーディオ機器を使う人は、バーチャル会議で自分が受け入れられている感覚がより強いと答えている。
実際にプロ用ヘッドセットの使用者は、一般向けの機器や内臓オーディオの使用者に比べ、バーチャル会議の会話で疎外感を感じる割合が11%低い。さらに、会議中に言葉が聞き取れない人の割合は、プロ用ヘッドセットの使用者は内臓オーディオの使用者より14%低く、一般向け機器の使用者より12%低い」。
3. 企業の従業員に対する職務遂行能力への信頼
「企業は、従業員に働く場所と時間を選ぶ自由を与えることで、彼らの職務遂行能力を信頼しているというメッセージを送ることになる。その信頼は、かなりの高確率でリーダーとチームに還元され、インクルージョンと帰属感に富む、結束の固い企業文化の構築につながることをデータが示している」。
リモート勤務形態の魅力を知ってしまった従業員を再びオフィスに迎え入れるには、オフィス環境をハイブリッド型へと高度化する必要があるということだ。
ハイブリッド型オフィスはここで述べたことは最低条件であるだろう。
さらなる進化が始まりつつあるということのようだ。
ビッグテックの市場独占によって揺らぐ資本主義
トマ・フィリポン ニューヨーク大学教授が3月22日付け日経新聞に寄稿し、GAFAMに代表するテック大企業の市場独占が資本主義を揺さぶっている。と警鐘を鳴らしている。
以下にその要旨を掲載する。
1. 筆者の推計では米国の物価は本来あるべき水準より8%高い。これを米国の標準的な世帯の支出でみると、毎月300ドル(約3.5万円)以上の税金を独占企業に払っているようなものだ。全世帯の12カ月分を足し合わせれば、独占企業の超過利潤は年間6千億ドルに達する計算になる。
2. 独占は価格を引き上げ、企業利益を膨らませている。第2次世界大戦後から現在までの米国の非金融企業における税引き後利益の国内総生産(GDP)比をみると、長く6%前後で推移していたが、ここ20年ほどは9%前後に上昇している(図参照)。
3. 利益は拡大し、自己株買いや高配当など株主への配分は増加したが、労働者には配分されず、労働分配率は下がり、物価水準の上昇と相まって実質賃金は目減りしている。資本所得は労働所得より格段に集中しやすいから、世帯から独占企業の株主への富の移転は不平等を拡大する。
4. ビッグテック企業にはもう一つ問題点がある。前の世代の巨大企業と比べ、富の集中の度合いが甚だしいことだ。従業員数もサプライヤー(部品会社など)の数も比較的少ないし、大きなリターンを提供する相手は株主であり、経済に広く恩恵は行き渡らない。
5. 競争衰退により民間部門のGDPは1兆ドル以上縮小したと推定される。逆にいえば、米国の市場に1990年代後半の競争が復活したら、実質労働所得は1兆ドル以上増えるはずだ。
6. 規制当局はビックテック企業の独占を排除しようと動いている。反トラスト法の適用を試みようとするがうまくいかない。ビックテックは有望な市場を開拓しているベンチャー企業を成長初期段階で買収するから、買収段階での規制は事実上不可能だ。
7. しかも規制当局はプライバシーを保護したいし、有害なコンテンツや偽情報の拡散を防ぎたい。GAFAMの市場支配力の一部は膨大なデータを掌握していることに由来するため、規制するとなればデータの保護とプライバシー法が関わってくる。ビッグテック規制問題は一筋縄ではいかない。
かくしてビッグテック企業による市場独占は資本主義の根本原理である自由競争を制限し、過剰な利益を独占し、その利益の分配は富裕層に偏り、超過利潤の源泉である高価格と相まって所得格差の拡大を加速させている。
しかしこの事態に対処する当局の反トラスト法の適用による規制は、決定的な有効性を欠いている。ビックテック企業の利益源泉は膨大なデータにあるからだ。仮にビッグテックの所有する膨大なデータの分割を実行させることができたとしても、ビッグテックの提供する検索エンジンの機能が減衰し、検索エンジンのユーザーの困惑が広がることになるだけだ。
ビッグテック企業の抱える膨大なビッグデーターに基づく様々なサービス水準の質が低下することはほぼ考えにくいだろう。つまりデータの分割をしてもビッグテックにとっては痛くも痒くもないということだ。
むしろビッグテックの保有するデータについて所有権を持つのはデータを提供しているユーザーではないのかということの方が問題としては大きい。ユーザーは無償で提供される検索エンジンサービスを使い込むうちに、せっせとビッグテック企業に利益源泉をせっせと無償で提供してきたという理不尽な状況にメスを入れることが必要だということだ。
つまりビッグテック企業の利益独占を排除するためには、データの所有者であるユーザーにビッグテックの利益を配分する仕組みを導入することが極めて有効であることは間違いない。
こうすることでビッグテック企業が拡大した貧富の格差の拡大に歯止めがかけられることになる。
ビックテック企業の市場独占は反トラスト法によっては決して対抗できないということだ。
セブンはヨーカ堂を守れるか
日経新聞2月28日に「セブン、ヨーカ堂を守れるか」と題する中村編集委員によるコラムが掲載されている。
「セブン&アイ・ホールディングスが投資ファンドから、百貨店のそごう・西武に続き、イトーヨーカ堂の売却を求められている。セブン&アイは約2兆3千億円を投じた米国でのM&A(合併・買収)を実施し、コンビニ優先戦略にかじを切った。果たして20年以上の停滞が続く総合スーパーを防衛できるのか」。
7&iホールディングスの首脳陣は、次のような論拠で物言う株主の意向に抵抗しているように見える。
「約8万品の品ぞろえを持ち、1日当たり140万~150万人が来店する顧客資産を生かし、成長力が見込める食とデジタル戦略の相乗効果に最後の期待を寄せることが可能だ」。
中村氏はヨーカ堂の売却に反対の立場に立つ。そして法政大学の矢作敏行名誉教授の説を引用して、売却反対の自説を補強している。
「矢作氏は『世界の小売業の趨勢を見ても、店舗とデジタルを一体化した企業に変身することが不可欠。今後は店舗の価値が高まる』と指摘する。店は売り場という役割だけでなく、商品の注文受け付けや物流などを手がける拠点として不可欠と見るからだ」。
矢作氏の説は流通業の将来は店舗とECの融合によるバーチャル&リアル・ストアへの大転換にかかっていると見ている。
とはいえヨーカ堂を現状のままにして大転換がはかれるとも思えない。
バーチャル&リアル・ストアへの大転換はどのように可能か?
むしろ店舗とECの一体化はセブンイレブンの店舗群を活用することによって可能になるのではないか。ECの競争優位は物流力によって決まる。それもラスト・ワンマイルと言われる顧客への最終配送力だ。
ラスト・ワンマイルに店舗を構えるコンビニはこの点においてもヨーカ堂に比して強力な優位性を持つ。しかもその拠点数の圧倒的な多さがモノを言う形になる。
となるとヨーカ堂はEC業態にあっての競争力は集客力とマーチャンダイジングの優位性に頼るほかはない。
ヨーカ堂はこれまでなんども業革の嵐による再建のメスが入れられてきた。セブンイレブンの成功体験を引っさげて鈴木敏文氏が先頭に立っての改革も、ヨーカ堂の再建を実現できなかった。
むしろ成功体験が赫赫たるものであったが故に失敗に終わったのだとも言える。
つまりセブンイレブンが好調を維持する限り、ヨーカ堂の再建は不可能だと言うことなのだ。
とすればヨーカ堂を抱え続けるとするならば、重い切った業態転換が必要となる。
ヨーカ堂を総合スーパーから食品スーパーへと業態転換する道だ。
食品領域でセブンイレブンが構築し、成果をあげ続けているビジネスモデルは、ユニクロやニトリと同様の製造小売業と言う業態に近い。おにぎり、弁当、焼きたてパン、惣菜などを製造する専業ベンダーと運命共同体の関係をつくりあげ、一体となってマーチャンダイジングとSCMを運営する形での製造小売業だ。
食品スーパーではセブンイレブンのこの製造小売りのビジネスモデルは活かされるはずだ。
食品以外の領域はそれこそ場所貸し業に専念し、ユニクロ、ニトリ、イケア、東急ハンズ、MUJIなどを誘致すれば良い。
そしてこれらの分野でのこれまでのマーチャンダイジングの知財はECで活用することができるはずだ。
ヨーカ堂をグループ内に残して活用するのならこうした活用法が唯一残された道ではないだようか。
原発は脱炭素メニューから外そう
2月24日の日経新聞「経済教室」で長崎大学の鈴木教授(元内閣府原子力委員会委員長代理)は「原発の依存度を低減へ国民的議論を」提唱している。
論旨をまとめると次のようになる。
1. 世界の電力供給における役割が現状程度か低下するのは明らかだ。世界の総発電量に占める原子力発電のシェアは、最近は10%前後で推移する。発電量も2020年は12年以来の減少(前年比3.9%減)となり、95年以来の低水準となった。であれば脱炭素電源としての役割も限定的なものと考えざるを得ない。
2. 停滞傾向の最大の要因として考えられるのが、原子力発電の競争力低下だ。脱炭素電源としての原子力発電コストは、再生可能エネルギーの発電コストの急速な低下に追いつかないとみられる。
3. 日本の20年の原子力発電比率は4%にすぎない。日本の電源構成で原発は「主役の座」を既に降りている。政府は30年度の原発比率を20~22%とする目標を掲げるが、とても実現できそうにない。NHK世論調査(20年11~12月)によると、7割近い国民が原発依存低減を望んでおり、再稼働についても賛成が16%に対し反対は39%にのぼる。
4. 高速増殖炉「もんじゅ」の廃止が決定した後も、核燃料サイクルについては議論もされていない。
5. 高速炉と核燃料サイクルの推進を大きな目標としてきた原子力研究開発も、廃炉や廃棄物処理・処分を最大の柱とする方向に転換すべきだろう。使用済み燃料の最終処分の見通しもない現状を考えれば、50年代から維持してきた「全量再処理路線」の見直しも不可避だ。
6. 原発事故が残した負の遺産はいまだに重く、国民の負担となっている。何よりも事故炉の廃止措置は、技術的に最も困難な課題であるとともに、経済的にも社会的にも今後40年以上にわたり取り組んでいかなければならない問題だ。
7. 福島の復興と避難した被災者の健康、生活、環境回復なども、負の遺産として東京電力のみならず政府が責任を持って取り組まなければいけない課題だ。
8. こうした負の遺産への取り組みが、本来は原子力政策の最優先課題であるべきだ。
9. 原子力の将来にかかわらず最優先で取り組まなければいけない課題(福島第1原発の廃炉、福島の復興、放射性廃棄物問題、人材確保など)が山積みだ。
日本の原子力政策の課題を整理してみよう
以上の鈴木氏の論考をベースに日本の原子力政策の重要課題を整理してみよう。
1. まず50年を目標年度とするゼロエミッションのエネルギー構成比において原子力の占める比率はゼロとする。
2. 原発は全て即時廃炉にする道を選択する。
3. 今後の原子力政策は以下の課題を重点として取り組むこととする。
① 福島原発の廃炉とこれに伴う汚染物質(デブリ、汚染土、汚染水)の完全処理。
② 福島原発の事故に伴う被災者の完全救済。
③ 使用済み核燃料の処理法の研究開発。
④ 原発の安全な廃炉の方法の研究開発。
⑤ 福島原発廃炉ならびに使用済み核燃料処理に関わる人材の養成。
ところで、福島原発の事故原因はいまだに明らかになっていない。二つの仮説がある。
1. 津波によって全電源が喪失し、核燃料の冷却が不可能になった。
2. 地震によって核燃料冷却システムが破壊され、冷却が不邪脳になった。
最近では二番目の仮説が有力視されてきている。
地震国日本において活断層を避けて原発を建設することは不可能に近い。
とすると巨大地震によっても破壊されない冷却システムの組み込みが必須になる。
そのための建設費、あるいは既存原発の補修費には天文学的なコストが必要になる。
またそのような補修がなされるまでの原発の稼働にあたっては、
1. 万が一のための住民の避難経路の確保、
2. 損害が起きたときの損害保険の付保
が前提となされなければならない。
これらの課題は先に述べた重点課題に加えて、今稼働している10基の原発について、早急に講じられるべき処置になる。
福島原発の事故を経験した日本は世界の原発の廃炉に向けて、戦略的な経路の研究開発の先頭に立って推進する機会と責務とが与えられたと識るべきである。

円安の重荷家計を直撃
1月30日付け日経新聞は「円安の重圧 暮らしに」と題する記事で、円安が「安い日本」を加速させていると警鐘を鳴らしている。
日銀は円安について「基本的にプラスの効果が大きい」(黒田東彦総裁)との立場を崩していない。
しかし円安で輸出が拡大し輸出セクターの収益増加が経済成長のエンジンとなるという構造はもはや失われつつある。
経済のグローバル化の進展とドル危機以降の円高の持続で輸出企業は人件費と物流費の削減を求めて工場を海外に展開してきた。輸出セクターにとって円安はさほどの収益増加を生み出さなくなった。
12年以降の大規模金融緩和による円安の進行は輸入品の価格上昇をもたらした。
加えて、「ほぼすべてを輸入に依存する原油など資源価格の上昇で、21年7~9月の企業間取引の輸入物価指数は前年比で3割上昇。同期間の輸出物価指数の上昇率(1割)を大きく上回った」。
こうして輸出価格と輸入価格を比べて貿易での稼ぎやすさを示す交易条件の悪化が進行した。21年7~9月の交易条件の悪化幅は遡れる05年以降で最大だった。
円安の進行は家計を直撃している。
「幅広い生活品目で輸入依存が進んでいる。国内消費に占める輸入品の比率をみると、家電・家具などの耐久消費財は34%となり、10年ほど前の1.7倍に高まった。食品・衣料品などの消費財も同1.4倍の25%に上昇した。
国内経済は低成長で賃金が上がらない。その中での身近な品目の上昇は家計の重圧となる。一端が家計の消費に占める食費の割合を示すエンゲル係数の上昇だ。21年1~11月は25%超と、1980年代半ば以来の水準に高まった」。
「アップルの「iPhone13」を手に入れるのに必要な労働時間からも日本の買う力の衰えがわかる。英マネースーパーマーケットが各国の月給をもとに計算したところ日本では72時間働く必要があるが、端末価格が日本より高いはずのオーストラリアやデンマークは60時間程度ですむ」。
経済のグローバル化は日本の産業構造を大きく変えてきた。
結果として現れたのは資源から消費財に至るあらゆる物品の輸入依存度の拡大だ。
つまり製造業の空洞化であり、自給率の低下だ。
こうした構造の中での円安は生活者の所得の収縮を伴うインフレの進行と、海外の供給が不安定になることによる経済基盤の不安定化を拡大する。
金融緩和が続く限り生活者は今後貧困と不安定な物資の供給による不安に脅かされることになるかもしれない。


「経済安全保障推進法案」の問題点
1月17日付け日経新聞は一面で、「経済安全保障推進法案」について報じている。
「政府は社会・経済活動に不可欠な物品の国内調達を維持するため、サプライチェーン(供給網)の構築を財政支援する仕組みを新設する。半導体や医薬品を支援対象に指定し、事業者の研究開発を後押しする」。
「政府は緊急時に物品を調達できなくなる事態を防ぐための手立てが要ると判断した。17日召集の通常国会に提出する『経済安全保障推進法案』に支援の仕組みを明記する。2023年度中の運用開始を目指す。
「安定確保へ支援が必要と判断した物品を『特定重要物資』に指定する。現時点で半導体、医薬品、大容量電池、希土類(レアアース)といった重要鉱物を想定する」。
この政策は、TSMCの工場を熊本に誘致し、政府が総投資額8000億円のうち5000億円規模の補助金を支出する方針決定を後付けで正当化するために策定された感が否めない。
このTSMCへの補助金はいくつかの問題点がすでに指摘されている。
なぜ、株式投資ではなく、補助金なのか。
なぜ、最先端の技術の半導体製造設備ではないのか。
なぜ、サムソン電子ではなくTSMCなのか。
疑念は晴れないまま事態は進行している。
中でもこうした補助金の意思決定が恣意的に行われないための仕組みづくりの必要性が取りざたされていた。
このような疑念に応えるための法案整備がとって付けたように後付けで出てきた感じだ。
補助金制度に正当性はあるか?
さらに問題とすべきはこうした補助金制度についてのそもそも論的な議論だ。
論点は二つ。
一つは今回の補助金対象の半導体、医薬品、大容量電池などは、そもそも日本企業が競争力を失って、もはや挽回の手立てを失っている産業であり、これに補助金をつけて振興を支援しても結局は無駄金の散財に終わるという点だ。
無駄金に終わらないためには。TSMCのように海外から先端企業の工場を誘致する他に手立てはない。
しかしその場合は出資側の判断でいつ撤退するかもしれないというリスクを排除することはできない。
となると本来の目的である危機管理のための供給能力の持続的確保の保障が担保されないことになる。
半導体や電池より食料の自給が先では?
二つ目の論点は、半導体や電池などの産業用部品よりもっと切実な物品の供給力の維持が必要なものがあるということだ。
国民の生活の基盤である、食料とエネルギーだ。
食料もエネルギーも自給率は極めて低く心もとない状態にある。
食料の中でも小麦、大豆、飼料用とうもろこし、畜肉、植物性油脂などの自給率は20%を切っている。
食料とエネルギーの自給率の高度化こそ官民一体となって取り組むべき課題だ。
畑作農業、畜産業、そして再生可能エネルギーの分野への重点的な金銭的、技術的な支援こそが求められている。
リーマンショックの再来は回避できるか
FRBがテーパリングの開始を方針として掲げた。
これをきっかけにして金融市場の大波乱が起きてもおかしくはない。
日経新聞の11日付けの「オピニオン」でコメンテーターの梶原誠氏が興味深いデータを示している。
|
|
2017年 |
現在 |
|
株価(前年までの全世界の上昇率) |
44% |
66% |
|
ジャンク債の発行 |
2083本(06年) |
2543本(21年) |
|
運用会社の資産 |
44兆ドル(06年) |
103兆ドル(20年) |
|
主要4中銀の資産 |
3兆ドル(06年末) |
26兆ドル(21年11月) |
|
話題の金融商品 |
サブプライムローン |
SPAC |
|
FRB |
06年まで利上げ |
22年から利上げへ |
|
その後 |
バリバショック リーマンショック |
? |
先進国の大規模な金融緩和策によって生まれた過剰流動性がリスクの大きいジャンク債やSPACへと流れ込んでいる。この風景は15年前と変わらない。
ここには表示されていないが不動産価格の上昇も15年前に相当する状況にあるはずだ。
大きく違う点は中銀の資産が異常な膨張を示している点だ。
資産の中身は国債や民間金融機関への貸付、そしてETFを経由しての株式だ。
日銀以外の先進国の中銀にとって金融緩和の行き過ぎの是正策が今年の課題になっている。
すでにFRBは年4回の利上げの実行を宣言している。
利上げが実行されれば国債をはじめとする債券の価格が下落する。
これが引き金になって、ほとんどの金融資産、不動産の価格崩壊が生じる。
そして金融資産や不動産価格のバブルが崩壊した時に生じる今回の惨状は、
リーマンショックの時の4倍に相当する規模で世界を襲う。
これが常識的な現状理解なのだが、FRBをはじめとする先進国の中銀がこのリスクをまるでないかの如く利上げに向かうのはなぜなのか。
彼らは利上げしてもこうしたバブル崩壊のリスクが生じない、あるいは生じさせない施策を講じることを前提としているのだろうか。
物価上昇の範囲内での金利上昇はリスクを回避できるということなら、その根拠を明確に示すことが望まれる。
脱炭素時代の半導体に日本の勝機あり
名古屋大学教授天野浩氏へのインタビューが日経新聞1月10日付に掲載された。
台湾、韓国に席巻されて見る影のない日本の半導体産業。
この状況を一変する技術開発が天野氏のリードのもと進行中だ。
大電流、高電圧のもとで活用されるシリコンに変わる素材「Gan(窒化ガリウム)」だ。
EV、携帯電話基地、データセンター、再生可能エネルギーの蓄電・送配電システムで使われる、電力供給半導体や電圧、周波数を変える半導体(パアワーデヴァイス)の素材がシリコンに変わってGanに置き換わる。
欧米も取り組んでいるが、日本には何年も追いつけないノウハウがある。
すでに天野氏はGan半導体の製造技術を確立している。
30年停滞を続ける日本の産業構造の高度化の突破口がGanによって開ける。
それを担う企業家精神に溢れる企業家の出現が待たれている。
「半導体の素材といえばシリコンというのが常識かもしれない。だが、シリコンにも向いている用途とそうでない用途があって、これからは向いていない用途が増える。引き金を引くのが世界的なカーボンニュートラル(温暖化ガスの排出実質ゼロ)の動きだ。そうした分野で注目されるのが化合物半導体だ。中でも、窒素とガリウムが結合したGaNに大きな市場ができる」
「簡単に言えば、シリコンは低い電圧、小さい電流のもとで効率的に働く性質がある。ロジックやメモリーという形でパソコン、スマートフォンの演算処理に使うのはそのためだ」
「一方、これから需要が広がるのは高電圧・大電流での用途だ。電気自動車(EV)、携帯電話基地局、データセンター、再生可能エネルギーの蓄電・送配電システムがそうだ。それらに使う電力供給半導体や電圧、周波数を変える半導体はパワーデバイスと呼ばれ、GaNが材料に適している。シリコンでは電気抵抗による電力喪失が大きく、効率が悪い」
「米欧も取り組んでいる。それらが何年も追いつけないほどのノウハウが日本にはあると思う。日本は材料分野に強みがある。シリコンでは台湾や韓国、中国との競争が激しく、今から巻き返すのは難しい。後追いをするより、GaNの新市場で先行したらどうか。GaNを含め、化合物系の半導体はシリコンを使う半導体の1000分の1程度しか市場規模がない。せっかくの好機でもあり、国内企業の手で世界に広げてもらえたらありがたい。昔のようなアニマルスピリッツに期待している」
「基地局やデータセンターの電源装置はおそらくGaNに置き換わっていく。データセンターについて言えば、通信に遅延が起きないよう、利用者の多い都市部に置くケースが増えているが、寒冷地でないことが多く冷却装置が要る。その点、GaNだと空調がなくても動く。シリコンが生み出した経済圏があるとしたら、それを動かすのがGaNだと考えればわかりやすい。5G(第5世代移動通信システム)も『ビヨンド5G』もGaNがあればこそ、能力を発揮できるわけだ」
「技術的には安心して使ってもらえるところまで来た。製造技術もあるが、残った課題が事業化の担い手を見つけることだ」
ソニーカーの衝撃
日経新聞は1月7日「EV大競走 ソニー難敵アップルに先手を打つ」と題する記事を掲載した。
ソニー会長兼社長の吉田氏はCESに登壇し、ソニーカーのコンセプトをプレゼンした。
日経新聞の伝える吉田氏のプレゼン内容からソニーカーのコンセプトを確認してみよう。
「車の価値を『移動』から『エンタメ』に変える」
ソニーの強みである画像センサー、映像・音響技術、コンテンツを結集して、車を移動の道具から進化させ、エンタメを楽しむ空間へと変貌させるのだという。
「リビングのような車」
サスペンションを制御して、路面から受ける車体の振動を打ち消す。
ノイズキャンセルの技術を使って、周囲の騒音を遮断する。
こうしてリビングで映画やゲームを楽しんでいるような環境を提供する。
自動運転につながる安全の追求
40個に及ぶ画像センサーを車内外に搭載し、人間では察知できないリスクを感知する。
リカーリング(継続課金)型の事業モデル
ハードウエアを売って終わりではなく、ソフトを通じて5~10年にわたって車を進化させられる環境をつくる
基本的に(多くの)アセット(資産)を持たない
ハードの製造。組み立ては協力会社に委託する。ファブレス型の企画開発に専念し、スマイルカーブの左端と右端に特化する事業モデルを追求する。
日経新聞はウオークマン以後iPod、iPhone、iPadによってAppleによって完膚なきまでに席巻された、オーディオ、エンタメ、通信分野で、ソニーはEVの事業領域に参入してリベンジを果たそうと触れ込んでいる。
そして今回の吉田氏のCESでのプレゼンがその号砲になるとまで持ち上げている。
果たしてそうか?
TESLAの戦略
すでにEV事業で最先端を疾駆しているテスラの戦略を見てみよう。
ソフト・ウエアドリブンによる価値創造
テスラはすでに車を走るスマホに見立てて、OS、電子制御ユニット、マンマシンインターフェース、そしてエンタメ系のアプリもほとんど自社開発している。
またソフトはオプションごとに価格が設定され、その提供はサブスクで行われる。
これらのソフトは継続的にアップデートされ、通信経由でダウンロードされる。
主要部品の自社開発
テスラは電池、半導体などの中核部品を自社開発している。
顧客体験からNO提供価値の進化
テスラは販売した全車の走行データを収集し、その膨大なビッグデータを解析して車の継続的な進化につなげている。
その改善点は以下のように多岐にわたっている。
・バグフィックス
・セキュリティ
・自動運転関連
・利便性の向上
・パフォーマンス向上
・エンターテインメント
・コンフォート
Appleはさらに手強い
テスラが目指すように車が「走るスマホ」であるなら、iPhoneで世界を席巻したAppleこそEVにおいても覇者になりうるポジションにいる。この点でソニーはすでに太刀打ちできないポジションではないだろうか。
AppleはiPhoneでApple Carの制御を完璧に行うこと程度の目標は設定しているだろう。
またiPhoneの調達システムに倣って、ファブレスによるSCMを構築するに違いない。
この点はテスラと一線を画すことになるだろう。
このように見ると、ソニーカーのコンセプトはテスラにもAppleにも見劣りする。
唯一優位点があるとしたら、車をリビングに見立てているところだ。
これを突き詰めると、もはや車の形状は現状のセダン対応とは全くかけ離れたものになるはずだ。
さらに先を見て自動運転を前提とした時、車はもはや運転席、助手席のないボックスタイプのリビングやカラオケボックスのようになるまでの想像をしなければならない。
ここまでのコンセプト拡張を突き詰めるならばソニーにもリベンジのチャンスがあるかもしれない。
日産リーフはなぜテスラに敗北したのか
日産は2010年に世界に先駆けてEV・リーフを販売した。しかしリーフはその後の10年でテスラに大きく遅れをとり、今では世界の販売台数ランキングで第7位。テスラはリーフの約7倍の販売台数を誇示する圧倒的首位の座を獲得している。
日産リーフの敗北の要因はどこにあったのだろう。
日経新聞2021年11月30日に掲載された中山淳史氏は「早すぎた日産『リーフ』」と題して日産「リーフ」のテスラに対する敗北の理由を論考している。
中山氏の論点を整理すると敗北要因は以下の通りになる。
1. 世界の急速なEV化の到来を予測して10年で1000万台の市場規模を想定した。手っ取り早くシェアを取りに行くために。利幅が小さいコンパクトカーのセグメントに集中したしかし市場規模はそれほど伸びず実際には200万台にとどまった。結果的に薄利のまま台数も伸びず利益額で遅れをとった。
2. 政府のEV化促進の環境整備も本腰が入るまでには至らなかった。中山氏は遠慮気味に次のようなコメントをしている。「自動車産業が求めないのか、政府が気づかないのか。いずれにしても世界の趨勢に対し、日本だけがEVや再生エネルギーのうねりに気づかぬフリをしているように見えるのは、一つの事実だ」。実はトヨタとそれをサポートする経産省がEVに乗り気でなく、燃料電池車に中途半端な未練を寄せながら結果的に世界から遅れを取ってしまっている。
3. しかし決定的なリーフの失敗の要因日本のお家芸であるものづくりの発想による開発から脱却できなかったことだった。中山氏は次のように指摘する。EVによって「データを使った新産業が誕生する余地が大きい。各種調査機関によれば、将来はハードと同規模の『まだ見ぬ産業』が現在の自動車産業に乗っかるイメージだ。立教大学ビジネススクールの田中道昭教授は自動車新時代のバリューチェーンを10階層に分け、『10の選択肢』(下図参照)としてまとめる。ハードの支配とともに重要なのはOS(基本ソフト)やプラットフォーム、エコシステムの支配だが、今の日本車メーカーはEVをいつまでに何車種発売するか、の段階に議論はとどまる」。
テスラの戦略
EVで世界を圧倒するテスラの戦略を見てみよう。そこには従来の製造業の世界では想像もできなかった情景が広がる。まずは戦略が導かれるテスラの掲げるビジョンに触れておこう。テスラのビジョンは何と「スマホ型EVの開発」だ。
スマホを進化させてどこでも移動可能な車にするということだ。
このビジョンを実現するために必要な具体的な目標を三つ設定している。
1. ソフトウエアドリブンで顧客価値を提供する。ハードはソフトによってコントロールされるというアーキテクチャーが大前提だ。従って顧客に対する提供価値はソフトの価値の高質化によって決定的なものになる。そしてソフトは継続的に進化し、それをシームレスに利用するためにオンラインでアップデートされる。そのためにサブスクでの提供が前提になる。
2. 顧客体験による提供価値の進化。ソフトの進化は顧客体験に基づく期待や要望やクレームによって実現する。車は常時オンラインで繋がり、全ての人データが収集され、データの解析から改善点が抽出される。また販売も全てオンラインで実施され、ユーザーの要求地点で試乗が可能になる。
3. 主要部品は自社開発を原則としている。最も大切なエンドユーザーコンピューティングは当然自社開発であり、ここに競争優位の原点が集約されている。さらにバッテリーや半導体も自社開発することで顧客価値の継続的な進化が保証されている。
テスラの戦略ストーリーを図解すると下図のようになる。ここに示されたテスラの戦略ストーリーはこれからのものづくりの基本テンプレートになるに違いない。


円の価値は下がり50年前に戻ってしまった
日経新聞11月18日によると、円の総合的な実力を示す実質実効為替レート(以下「円実質レート」)は約50年ぶりの低水準に近づきつつある。
円実質レートは85年のプラザ合意以降80の水準から上昇を続け95年に頂点に達し150を記録した。
95年の日米合同の円売り協調介入以後は円安政策が継続的に行われて、継続的に低下傾向が続いた。
更にアベノミクスによって円安志向が強化され、日銀の異次元金融緩和策が実効レートの低下を加速させた。しかし
円高とグローバル化の進展は、円安が輸出企業にとって、すなわち日本経済にとってプラスの効果をもたらすという事実は消滅傾向に転換した。
この事実を軽視ないし無視して継続した円安政策は日本経済の25年に及ぶ衰退傾向をもたらしたのだ。
「かつては円安が製造業の輸出競争力を後押しし、経済成長に寄与した。多くの企業が海外に拠点を移すなどして経済構造が変わり、円安による日本経済の押し上げ効果は弱まった。国内総生産(GDP)に占める製造業の比率は1970年代の35%から、2010年代には20%に低下した」。
更に円安が企業の交易条件を改善する効果は今になって無くなるどころか、輸入原材料およびエルギー価格の上昇をもたらして、むしろ交易条件を悪化させる要因になっている。
企業の交易条件の悪化は企業収益の減少に繋がり、給与収入の抑制を結果する。
また円の購買力の減衰はほとんど海外からの輸入に依存する食料やエネルギーなどの消費財の価格上昇につながる。
輸入消費財の価格上昇は勤労者の所得の減少との相乗効果によって消費の低迷をもたらすことになる。
つまり円安が続く限り日本経済は更なる縮減傾向に陥いることになる。
このジレンマからの脱出の道はあるのか。
一つだけある。
25年続く経済の低迷状況からの離脱の道は個人消費の二大柱である食料とエネルギーの自給率を改善することをおいてほかはない。
またエネルギーの自給率向上は再生エネルギーへの依存によってのみ可能であり、食料自給率の向上は休耕地や耕作放棄地の活用によってのみ可能になる。
したがってこの二大カテゴリーの自給率の向上は奇しくも気候変動対策と軌を一にするという意味で起死回生の奇手になるのだ。

一般的な為替レートは日本と米国など2国間の通貨の関係を示す。実質実効為替レートは様々な国の通貨の価値を計算し、さらに各国の物価変動を考慮して調整する。
自国通貨の実質実効レートが高いほど海外製品を割安に購入でき、逆に輸出には不利となる。BISは2010年を100として実質実効為替レートを算出している。

日本は低賃金と円安で一層貧しくなる
低賃金だから物価が上がらない
日経新聞は11月12日に「値上げできない日本 鈍い賃上げ、円安で貧しく」と題する記事が掲載された。
企業の出荷価格は上昇しているのに、消費者物価に転嫁できず、企業の収益構造が脆弱化しているのだ。
根本原因は何か?
賃金が上がらない→需要が弱い→企業物価上昇を最終消費者価格に転嫁できない→利益が伸びない→賃金も上げられない、という悪循環が続いている、これが根本原因だ。
実態を見てみよう。
企業物価指数は10月に前年同月比8.0%と40年ぶりの上昇率に達した。
ところが消費者物価の上昇率は0%台。
そして4~6月期の個人消費は2年前より5%減少した。
また過去30年の名目賃金は日本ではわずか4%増加でしかなかった。
可処分所得で見ても、世帯人数2人以上の勤労者世帯で20年間に5%(月額2万4000円強)しか増えていない。
同じ期間に社会保険料は35%(月額約1万7000円)増えた。膨らみ続ける社会保障費が家計を圧迫している。
米国は物価上昇→金融緩和から離脱へ
米国の動向と比較してみよう?
米国では企業物価を追いかけるように消費者物価が30年ぶりの6%台になった。
そして過去30年の名目賃金は米国では2.6倍に達した。
結果的に7~9月の個人消費はコロナ禍前の19年7~9月と比べて10%増えた。
消費者物価の上昇を前提に米国は金融緩和政策の見直しに梶を切りつつある、
この先にあるのは低金利政策からの離脱だ。
日本は円安でさらなる消費減少へ
ところが消費者物価の上がらない日本は低金利政策を継続せざるを得ない。
そして彼我の金利差は円安を導く。
そして円安は輸入物価の上昇に直結する。
コロナ禍にあって輸入物価指数はすでに前年比で4割高い。
これに円安が加わると、輸入物価はさらなる上昇をもたらす。
エネルギーと食料を輸入に依存している日本にとって円安は個人消費にさらに大きくマイナスの影響を及ぼす。
当面の日本のデフレ脱却は低賃金と円安がの高い障壁となって立ちふさがり、出口は一層困難を増すことになる

脱原発こそ脱炭素の切り札
日経新聞(11月2日)は「仏先頭に原発に回帰するEU」と題するThe Economistの記事を紹介している。
l EU加盟27カ国で今も原発を維持するのは13カ国だけだ。原発を禁じている国もある。そしてEUの政策決定に大きな力を持つ独仏2カ国は現在、原発を巡り真っ向から対立している。
l フランスが電力の7割強を原発で賄っているのに対し、ドイツは2022年までにすべての原発を閉鎖すると決めている。ベルギーからブルガリアまで様々な国がドイツに追随し、原発の新規建設計画を白紙に戻し、既に稼働中の原発は停止すると約束した。
l だがその後、世論は様変わりした。今回の原発を巡る論争では、ドイツが敗北する可能性が高い。ドイツは原発をクリーンエネルギーに分類することに反対しても、他の加盟国から十分な賛同を得られないことを承知している。オーストリアとルクセンブルクは恐らくドイツに追随するが、他に加勢しそうな国はない。ドイツはEUで最も力を持つと考えられているが、必ずしもそうではない。
l 一方、フランスはEU内での影響力をますます強めている。今やEUの多くの政策を巡る議論は仏の望む方向に進んでおり、EU各国が原発重視に再び回帰しつつあるのも、その一例だ。EU各国は、今や統制経済の色彩を強めつつある産業政策から、世界にEUの影響力を拡大させようとする外交政策まで、あらゆる面でフランスに同調するようになっている。
原発をめぐってのEU内での独仏の対立は仏が優位に立ち、EU各国は再び原発重視に回帰しつつあるというのだ。
原発路線への回帰の要因はこの記事からは読みとれない。
しかし50年までにカーボンニュートラルを実現する上で原発に依存せざるを得ないという現実的な状況が各国のエネルギー政策を転換しつつあると考えられる。
日本でも同様の認識が支配的だ。
しかしながら、日本の脱炭素政策は脱原発を前提に構築せざるを得ない宿命にあることを忘れてはならない。
なぜなら日本は世界でも稀に見る地震大国であるからだ。
東日本大震災の福島原発のメルトダウンは、津波による全電源喪失によって核燃料の冷却が不可能になったことが要因と理解されている。しかし実は福島原発は、全電源喪失以前に地震によって原子炉の冷却システムの配管、配線が破壊されていたことが主たる原因でメルトダウンしたことが明らかになっているのだ。
そして現在保有している全ての原発が耐震性において福島原発同様に重大な欠陥を有している。
いつ起きるかもしれない地震に備えて原発の耐震性を万全なものにしておくことは事実上不可能とさえ言えるのだ。
日本は従って原発に依存することなく50年までにカーボンニュートラルの課題を解決しなければならない。そして脱原発を前提とすることによって、エネルギー源を100%再生エネルギーに依存せざるを得ず、それゆえに再生エネルギーへの徹底した技術開発、投資そして運用システムの構築のプレッシャーが高まり、結果的に世界に先駆けて脱炭素世界を実現することが可能になるのだ。
つまり日本にとっては脱原発こそ脱炭素の切り札となるということだ。
COP26の論点
以下は10月1日「脱炭素 深掘りめざす石炭火力の縮小が争点」と題する日経新聞記事に基づきます。
第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)が英国グラスゴーで31日に開幕される。
石炭火力発電の廃止が論点に浮上している。
欧州には時期を明示して石炭火力を廃止する意向を示す国もある。
COP26の議長国の英国のジョンソン首相は、先進国は30年まで、途上国は40年までの廃止を求めている。
日本は30年度の発電の2割弱を賄う計画で、先進国としては消極的と批判の的になりそう。
カーボンプライシングの導入も論点の一つとなる。
炭素に価格をつけて企業の排出削減を促す排出量取引制度の導入も日本は遅れている。
途上国は最新技術や資金面でさらに途上国を支援するよう先進国に迫っている。
途上国の要求に先進国がどう応えるかも論点の一つになる。
気候変動対策において日本は大きく遅れをとっている。
10年前の福島原発事故を契機に日本中の原発が停止した。
この時点で原発を電源から外し、以後は再生エネルギーに依拠する電源構成を目指す意思決定ができていれば、再生エネルギー活用の技術革新が大きく前進して、今頃は気候変動対策において世界を牽引する立場に立っていたに違いない。
あの時点で原発ゼロの意思決定をせず、原発再稼働を前提に当面石炭火力やLNG火力に依拠して凌ごうとした姑息な決断が、今日の気候変動対策の周回遅れという困難の根本原因になっているのだ。
今からでも遅くはない。
原発ゼロの方針を明確に示し、50年の電源構成には原発はゼロとする計画をCOP26にて提示すべきだ。
それによって再生エネルギーの活用に向けて日本を挙げて全集中の取り組みが前進し、再生エネルギー立国の道が開けることになるはずだ。
さらに再生エネルギーは基本的に地産地消を前提にするので、再生エネルギー中心の電源構成は日本の貿易収支の改善に大きく寄与し、国富の面においても大きな貢献をするに違いない。
いつでも、どこでも、何度でも無料でPCR検査を
日経新聞の記事(10月1日)で初めてPCR検査の全面普及の必要性がはっきりとした形で表明された。
「『多数の感染者が潜在している可能性がある』。
東京都では第5波のピーク時、検査が必要な人が受けられない実態が問題視された。保健所の業務逼迫でスムーズに検査を広げることができなかった。
一方で安くても1回数千円を払う民間自費検査のニーズは高まっている。
厚労省によると、7月以降の自費検査は計500万回近い。公費による行政検査の6割超の水準に達した。
大規模な無料化を進める海外と、検査を受けるだけで苦労する日本とでは差が広がるばかりだ」。
日本の検査数の海外との格差は極めて大きい。
「英オックスフォード大の研究者らが運営するアワー・ワールド・イン・データによると、9月の1日あたりの検査数(7日移動平均)は人口1000人あたりオーストリアは40件前後、英国は15件前後、シンガポールは10件前後で推移する。日本は0.8件ほどにとどまる」。
異常を感じたら、あるいは感染者との濃厚接触がわかったらすぐに検査を受け、
その結果感染が確認されたら、即医療機関にて治療が始められることが、コロナ対策の基本であることは世界標準になっている。
それは以下の理由に基づく。
1. 感染初期に抗体カクテルなどの治療が始められれば重症化が防げる。
2. 無症状の感染者による感染を予防できる。
しかし検査の拡充のためには以下の条件が不可欠となる。
1. 検査が無料であるいは保険適用で何度でもできる体制が整えられなければならない。
2. 検査で感染が確認された時にすぐに受け入れてもらえる医療体制が整えられなければならない。。
こうした二つの要件が新型コロナ感染の初期から既に2年を経過しようとしているのに、いまだに明確な方向づけさえもできていない。
記事によれば、
「次期政権を率いる岸田文雄氏は自民党総裁選で無料のPCR検査所の拡大や、家庭での抗原検査普及を掲げた」ようだ。
第6波が来るまでに検査体制と医療体制の整備を今度こそ実現しなければならない。
残されている時間は2ヶ月だ。

スタグフレーション下のスクリューフレーション
以下のブログは日経新聞9月21日の「オピニオン」をもとにした論考となります。
格差是正を求めて失業率を下げることを目指した米国FRBの金融政策が、予想を上回る物価上昇を招いている。
結果として皮肉にも中間層以下の貧困化に繋がり格差は是正されるどころか拡大しつつある。
この現象を「スクリューフレーション」という。
「中間層の貧困化を指す『スクリューイング(Screwing)』と『インフレーション(Inflation)』を組み合わせた造語だ」。
「失業率は5%台に低下したものの、コロナ禍前の3%台半ばはまだ遠い。一方でインフレ率は1%から5%台に跳ね上がり、インフレ制御の是非を問われる事態になった」。
物価上昇が実質賃金の低下につながり中間層以下の購買力を損ね、格差をより拡大している。
「高い伸びが続く米消費者物価指数の内訳をみると、中古車やガソリンの押し上げが目立つ。車社会の米国では中低所得層の懐を直撃する。値上げの動きは食料品や家具・寝具など、生活に身近な品目で広がりをみせる。多くは新型コロナウイルス禍での供給制約や国際商品相場の上昇が背景にあるが、そうした理由では説明しにくい家賃や授業料の上昇率が再び高まり始めているのも気がかりだ」。
物価上昇の要因はこればかりでなく、FRBの金融引き締めの動きが金利の上昇を招き、これが引き金になって物価上昇の傾向が促されていることも考慮に入れなければならない。
ところで日銀もデフレ脱却を旗印にこの10年低金利政策による超金融緩和策を継続して来た。
しかし物価は一向に上向きに向かわず、賃金も全く据え置かれたままだ。
緩和マネーは株式と不動産に流れ込み資産家だけが雪だるま式に資産を傍聴させ、格差の拡大が進行した。
結果として消費は拡大せず、経済成長は停滞を続けた。
このような状況に加え新型コロナウイルス禍が新たな局面を開きつつある。
米国同様、国際商品の価格上昇と供給制約による物価上昇の兆しが見え始めているのだ。
しかも日銀は金融緩和策の解除の方向を探ることもしていないので、すでに金利引き上げの時期を探り始めているFRBとの政策ギャップから、今後は一層の円安に向かうことが想定される。
となると輸入に依存するエネルギー資源、食品など消費財は円安によってさらなる価格上昇をまぬがれ得ることはできない。
輸入消費財の価格上昇によるインフレが日本の中間層以下を襲う。
賃金の上昇も望めない状況で実質賃金が大きく引き下げられ、格差の拡大が進行する。
かくして日本経済はスタグフレーションの中でのスクリューフレーションで中間層の崩壊現象に一気に加速することになりそうだ。
習近平こそ中国のリスクだ
以下は日経新聞9月17日に掲載されたギデオン・ラックマン氏(チーフ・フォーリン・アフェアーズ・コメンテーター )のコラムに基づくブログです。
習近平個人崇拝の中国人民への急激な浸透が進行する中で、
中国の国家的なリスクがマグマのようにたまり続けていく。
「習氏への個人崇拝は、中国の教育を受けた中間層や政府高官らにとっては本質的に屈辱でもある。
彼らは習氏の思想を毎日、特別なアプリを使って学ぶことを義務付けられている。
習氏の思索に対し尊敬の念を表明し、
『澄んだ水と緑の山は金山銀山にほかならない』
といった習氏の好む言葉を唱えることが求められる。
これをとんでもないとか失笑に値すると思う者は、
賢明にもその考えを口にすることはないだろう。
つまり、習氏の個人崇拝が進む中で中国の体制には今、
偽善と恐怖がどんどん染み込みつつあるということだ」。
中国の抱えるリスクとは何か。
それは習近平思想を絶対化するドグマと13億人の個々人の思想信条との相克だ。
習近平思想には中国社会が目指すべきビジョンが欠落している。
ビジョンが大多数の人民に共有されてはじめて権力は正当性を持つ。
ビジョン無き権力は恫喝と欺瞞と隠蔽とによる専制に向かわざるを得ない。
この時権力は恐怖によって人民を支配する。
恐怖が個々人の思想信条の自由を簒奪し、独裁制が完成する。
同時に10%の支配者層と90%の非支配者層との絶望的なほどの格差社会も完成する。
このような社会で多少の経済的な豊かさを得ることができたとして、
果たしてそれは人民の幸福を実現するであろうか。
少なくとも1億人だけでなく、12億人が自由闊達に生きることのできる社会こそ、
真に豊かな社会の実現につながるはずなのだ。
耐震新基準でも福島原発の安全は護れない
原子力規制委員会は8日、東京電力福島第1原子力発電所の廃炉設備の耐震設計で想定する最大の地震の揺れを引き上げた。(日経新聞9月9日)
しかしこの新基準でも原発を地震から護ることはできない。
「2月の福島県沖を震源とする地震を受けた措置で、900ガル(ガルは加速度の単位)の地震でも機能を維持できる耐震性を求める。廃炉作業の安全性を高める一方で、コスト上昇や作業の遅れにつながる可能性がある。
今後設ける使用済み燃料や溶融燃料(デブリ)を貯蔵する設備に適用する。従来の想定は最大600ガルだった」。
900ガルの新基準も原発設備を地震から護るには程遠い基準ということだ。
ところでガルとは、地震の大きさを表す指標の1つである加速度を示す単位。
2008年の岩手・宮城内陸地震では最大で4,022ガル、
07年の新潟県中越沖地震では柏崎刈羽原発の1号機タービン建屋1階で1,862ガル、
同3号機タービン建屋1階で2,058ガル、
同6号機原子炉建屋の屋根トラスで1,541ガルの揺れが観測された。
全国の原発でも、約600~1,000ガルの揺れを超える地震に見舞われることが十分にあり得ると言える。
また、これらの原発の耐震基準は原子炉本体や格納容器などの主要な部分のみに適用され、
緊急時に炉心を冷却する非常用炉心冷却装置や配管などの設備は別扱いだ。
つまり原子炉本体や格納容器が地震に耐えても、
原子炉を冷却する冷却水用の配管や電気系統が被害を受ければ核燃料のメルトダウンに繋がる。
ちなみに三井ホームの住宅の耐震設計は5115ガル、住友林業は3406ガル。
つまり原発に関わる耐震基準は住宅の基準に比べて著しく低い基準に設定されている。
なお1996年以降に起きた600ガル以上の大地震は以下の通りだ。
(気象庁調べ、最大震度6弱以上を掲載 ※1…K-NET(防災科学技術研究所)調べ) …計測震度5.5以上の観測地点が複数あった地震
https://www.homelabo.co.jp/select/history01.html
|
年 度 |
地 震 |
マグニ |
最大震度 |
最大加速度(gal) ※1 |
|
1997年 |
鹿児島県薩摩地方 |
6.4 |
6弱 |
977gal(鹿児島県薩摩郡宮之城) |
|
鳥取県西部地震 |
7.3 |
6強 |
1135gal(鳥取県日野町) |
|
|
2001年 |
芸予地震 |
6.7 |
6弱 |
852gal(広島県湯来町) |
|
2003年 |
宮城県沖 |
7.1 |
6弱 |
1571gal(宮城県石巻市牡鹿) |
|
十勝沖地震 |
8.0 |
6弱 |
989gal(北海道広尾郡) |
|
|
2004年 |
新潟県中越地震 |
6.8 |
7 |
1750gal(新潟県十日町市) |
|
2007年 |
能登半島地震 |
6.9 |
6強 |
945gal(石川県富来町) |
|
新潟県中越沖地震 |
6.8 |
6強 |
813gal(新潟県柏崎市) |
|
|
2008年 |
岩手・宮城内陸地震 |
7.2 |
6強 |
4022gal(岩手県一関市) |
|
岩手県沿岸北部 |
6.8 |
6弱 |
1186gal(岩手県盛岡市玉山) |
|
|
2011年 |
東北地方太平洋沖地震 |
9.0 |
7 |
2933gal(宮城県築館長) |
|
茨城県北部 |
7.7 |
6強 |
957gal(茨城県 鉾田市) |
|
|
長野県・新潟県県境付近 |
6.7 |
6強 |
804gal(新潟県中魚沼郡津南) |
|
|
静岡県東部 |
6.4 |
6強 |
1076gal(静岡県富士宮市) |
|
|
茨城県北部 |
7.2 |
6強 |
1084gal(茨城県高萩市) |
|
|
宮城県沖 |
7.2 |
6強 |
1496gal(宮城県石巻市牡鹿) |
|
|
福島県浜通り |
7.0 |
6弱 |
746gal(茨城県北茨城市) |
|
|
福島県中通り |
6.4 |
6弱 |
847gal(茨城県北茨城市) |
|
|
2013年 |
栃木県北部 |
6.3 |
6強 |
1300gal(栃木県日光市栗山) |
|
2016年 |
熊本地震 |
7.3 |
7 |
1362gal(熊本県益城町) |
|
内浦湾 |
5.3 |
6弱 |
976gal(北海道茅部郡南茅部町) |
|
|
鳥取県中部 |
6.6 |
6弱 |
1494gal(鳥取県倉吉市) |
|
|
茨城県北部 |
6.3 |
6弱 |
887gal(茨城県高萩市) |
|
|
2018年 |
大阪府北部 |
6.1 |
6弱 |
806gal(大阪府高槻市) |
|
北海道胆振東部地震 |
6.7 |
7 |
1796gal(北海道勇払郡追分町) |
|
|
2019年 |
山形県沖 |
6.7 |
6弱 |
653gal(山形県鶴岡市温海) |
コロナ病床の管理システムが使い物にならない
新型コロナウイルス用の病床状況把握システムが機能不全だ。(日経新聞9月7日)
地域全体の病床の稼働状況を行政も医療関係者もリアルタイムに正確につかめないので、
感染者の入院調整に使えないというお粗末な状況が放置され続けている。
「病床の空き状況を把握する仕組みとしては厚生労働省の『医療機関等情報支援システム』(G-MIS)がある。
2020年春の第1波の際、神奈川県のシステムを参考に急きょ稼働させた。
21年7月時点で国内のほぼすべてにあたる約8300の病院、約3万の診療所が登録している。
医療機関がコロナ対応の全空床数や集中治療室(ICU)の空床数のほか、
受け入れ可能な患者数や回復後の患者数などを打ち込んでいる。
内容は保健所や都道府県の担当者が確認できる」。
せっかくシステムがあり、病院の担当者が必死に入力しているが、
何と現場はアナログの電話対応に追われる。
前日のデータを入力する仕組みのため、喫緊の入院調整に使いにくいのだ。
感染が拡大して刻々と変化する状況に追いつかず、
リアルタイムで実際に空いている病床を探すのは難しい。
国のG-MISとは別に自治体が固有のシステムを開発して、
相互の連携もなしに二重に運用されているという問題も混乱に輪をかけている。
「東京の医療機関は都が運営する別のシステムでの空床報告や保健所への連絡も求められている。担当者は『一日の半分以上は入力作業に関する業務に追われている』という。
都のシステムも防災対応が主目的で、入院調整には活用されていないのが現実だ。『苦労して入力しても何のために使われているのか分からない』との声が漏れる」。
使い物にならないシステムのために、
現場は重複する入力作業やデータ管理作業に翻弄されている。
せめて二重入力だけでも無くせないのか。
このような状況から二つの問題が浮かび上がる。
1. デジタルシステムの開発の最上流でシステムの目的が明確に定義されていなかった。
つまりこのシステムは何のために開発されるのかが明確でないまま開発が始まった。
「コロナ病床の空き状況をリアルタイムに把握して、感染者の入院調整、入院予約を実現する」という要件定義が明確にされていれば、
現状の惨状は起きていないはずだ。
2. こうした状況が1年以上も継続し、改善の兆しが見えない。
開発されたシステムは常時その不具合を監視し、
スピーディに改善することが必要だ。
このフィードバックループが存在しなければ、
システムは使われずに無用の長物になるか、
無理に運用することで現場に多大な負担と混乱を持ち込むことになる。
デジタルシステムが機能不全に陥る要因は上記の二つに絞られる。
日本の作業現場ではデジタル化しても生産性が上がらず、
逆に現場に重荷を負わせることになる風景は枚挙にいとまがない。
上記の日本のデジタル化につきまとうシステム「機能不全症候群」の病根を絶やさない限り、
日本の労働生産性はいつまでも低位のまま、
現場は「ブルシット・ジョブ(クソ面白くない仕事)」で溢れかえる状況が続く。
地球温暖化が病原体を多様化する
地球温暖化がヒトの対病原体抵抗力を無力化する
地球温暖化による気温上昇は気候変動だけでなく、ヒトに対する病原体の多様化というリスクをもたらす。(9月5日日経新聞)
「ヒトをはじめとする哺乳類や鳥類などは、一定の体温を維持して自然界にいる病原体から身を守っている。
体温は皮膚や免疫反応と並ぶ防御の盾だ」。
つまりヒトにとって害をなす微生物やウイルスの増殖温度帯は、ヒトの体温より低い。
ところが地球温暖化が進むにつれて、ヒトの体温を超える温度帯で増殖する能力をもつ病原体が出現し始めている。
つまり温暖化で暑い日々が当たり前になれば体温による対病原体防御機能は弱体化していく。
「最悪のシナリオはこうだ。
高温で生き残った『耐熱性』の病原体は、苦手としていたヒトの体温をやりすごせる。
今はヒトの体温よりも低い温度の爬虫(はちゅう)類や昆虫などの体にいる病原体も、
ヒトの体にやすやすと乗り移れるようになる」。
米ジョンズ・ホプキンス大学のアルトゥーロ・カサデバル博士はいう。
「このままでは人類が危うい。
微生物やウイルスは世代交代が速く、温暖化とともに高温に合うように進化しやすい。
同じようにヒトの体温が急速に上がるとは思えない」
地球温暖化による病原体の多様化は、高温に対応する病原体の増加だけではない。
シベリアの永久凍土の溶解によって、凍結していた未知の病原体が活性化してヒトを襲うことが危惧されている。
COVID-19によるパンデミックだけでも人類は世界中で大きな被害を蒙っている。
地球温暖化によって同様の破壊力を持った病原体が多数出現するとしたら、人類の持続可能性は今考えられているより速いスピードで失われることになるかもしれない。
経産省が脱カーボンの行く手を阻む
日経新聞は「脱炭素を阻む省庁縦割り不毛な綱引き」(8月26日)と題して、日本のカーボンニュートラル戦略推進の停滞を批判する記事を掲載した。
「菅政権は2050年の炭素排出実質ゼロを掲げ、日本のエネルギー政策は脱炭素にカジを切った。実現に向けたエネルギー基本計画や、炭素に価格をつけるカーボンプライシングの議論では省庁間の縦割りや不毛な綱引きばかりが目立つ。国全体の視点で、脱炭素を本気で成長戦略の柱に据える覚悟は見えない」。
日本のグリーン政策に関係する省庁は、経産省(エネルギー全般)と環境省(気候変動対策全般)が主体となっている。
これに加えて、文科省(科学技術、研究開発)、国交省(航空、船舶)、農水省(森林保全、農地活用)なども主導権をめぐって足並みは揃わない。
他国ではどうか?
「エネルギー政策は、英国では独立した政府諮問機関の気候変動委員会が司令塔を担い、スペインは省庁を一元化した」。
日本では、気候変動対策推進室が内閣官房に新設されたが、省庁間の綱引きの調整では十分に機能していない。
根本原因は縦割り行政か?
この記事で見落としている重要な事実がある。
それはグリーン政策の停滞の要因は司令塔が存在しないということではないということだ。
最大の要因は経産省が原発依存の政策を頑なに保持したまま、エネルギー政策の主導権を握って手放さないばかりか、強力な不協和音を発してグリーン政策推進を撹乱していることだ。
福島原発事故を経験した地震大国日本にとって、原発の即時停止は、リスク回避の観点からエネルギー政策の前提としなければならないのは自明のはずだ。
そればかりか、再生エネルギーのコスト構造が30年には、原発のオペレーションコストを大幅に下回るようになることも、50年を見据えたエネルギー政策において原発の立ち位置はないことを明らかにしている。
このような原発をいまだにエネルギー政策の中心から外す意思を捨てない経産省が存在することが、「脱炭素を阻む」根本原因だと言わざるを得ない。
経産省を解体すればグリーン政策は快進撃を始める
そもそも経産省の役割は90年始めのバブル崩壊後に終焉を迎えているのだ。
この30年の経産省の産業政策は、半導体産業再生、液晶ディスプレイ産業再生、原発推進政策、クールジャパン構想などなど、すでに韓国の遥か後塵を拝する死屍累々の光景を呈していることからも自明のように失敗の連続だ。唯一生き残ったかに見える自動車産業もEV化に乗り遅れて、10年後には衰退に向かっているかもしれない。
つまり経産省は今やいわばゾンビ省庁として生き延びているにすぎない。その有害無益の経産省がいまだに産業、エネルギー政策の「司令塔」のような立場で邪魔をしていることが、カーボンニュートラル推進がいまだに軌道に乗らない諸悪の根源なのだ。
今こそ経産省を解体して環境省を中心とするグリーンエネルギー政策の推進体制を再構築するべきなのだ。
経産省解体はグリーン政策推進に拍車をかけることだけではなく、日本の産業構造をソフト化する産業政策を大きく前進させる契機になるに違いない。
芋虫と蜂をめぐるウイルスのしたたかな戦略
8月22日の日経新聞に、ウイルスに関する興味深い記事が掲載されていた。
以下はその記事の紹介。
芋虫がハチの寄生から身を守る「蜂殺し遺伝子」の働きが解明された。
突き止めたのは東京農工大学の仲井まどか教授らとスペインやカナダの大学などの国際チーム。
この蜂殺し遺伝子を芋虫にもたらしたのが、
芋虫に感染するウイルスだったことから驚きが広がっている。
あるウイルスが芋虫と寄生バチ同士の争いに介入していたのだ。
発見の端緒は、
このウイルスがいる芋虫にはなぜか寄生バチの卵や幼虫が育たない、
という事実だった。
ところでこのウイルスは芋虫に感染し自らを増殖する。
一方、寄生バチは芋虫に卵を産みつける。
卵からかえった幼虫は芋虫を食べて育ち、やがて巣立っていく。
ゆえにこのウイルスは芋虫を死に追いやるハチと敵対関係にある。
そこでウイルスは、寄生バチを敵とする芋虫に肩入れする戦略を立てた。
ハチの卵や幼虫を死滅させる毒をつくる遺伝子を芋虫に組み込む戦略だ。
感染した芋虫の体液から見つかった毒となるたんぱく質は、
「アポトーシス」と呼ぶ作用で寄生バチの卵や幼虫を死滅させていた。
この毒をつくるのが蜂殺し遺伝子だ。
芋虫とウイルスは双方の利害対立を越えて手を組んだ。
「ウイルスにとって免疫を備えた芋虫は敵だ」。
「芋虫にとって命を奪う寄生バチよりも体調不良で済むウイルスの方がマシだ」。
結果的には、ウイルスは助け舟を出しながら、芋虫を増殖に利用することが可能になった。
ウイルスの戦略はしたたかと言わざるを得ない。
ところで変異を繰り返しながら猛威を奮うCOVID19は、
人類を敵とみなして人類を死滅に追いやろうとしているようにも見える。
とするなら人類はこのウイルスの生存を脅かし、
その反撃を受けているのかもしれない。
つまりウイルスと芋虫と寄生蜂に擬えるなら、
寄生蜂が人類で、その人類が芋虫に相当する何かに危害を加えることで、
ウイルスを窮地に追い込んできたということだ。
そしてウイルスからその反撃を今受けているのではないか?
果たしてそのウイルスを窮地に追い込んだ何かとは?
例えば地球環境の破壊を続ける人類の所業が、
これまでウイルスの増殖の培養地であったある生物を死滅に追いやり、
その結果ウイルスは生存を脅かされており、
ウイルスはその危機を脱するために、
人類に猛威をふるっているのかもしれないのだ。
したたかなるかな、ウイルスの生存戦略。
野戦病院こそが新型コロナに対する有効な防護策だ
インド型(デルタ型)の猛威で新型コロナの感染者は急増した。
8月20日現在、全国の新型コロナ療養者の実態は以下の通りだ。
療養者数 167,588人
入院者数 21,590人
内重症者数 2,591人
宿泊療養者数 18,030人
自宅療養者数 96,857人
療養先調整中 31,111人
内入院先調整中 1,858人
発症している人のうち入院できている療養者はわずかに13%でしかない。
約13万人の方が自宅で不安と恐怖に向き合っている状況なのだ。
この状況を生じている要因はコロナ対応可能な病床数が圧倒的に少ないことにある。
発症者を受け入れる病床数の実態は以下の通りだ。
即応病床数 36,314床
内即応重症病床 5,157床
8月20日時点での発症者が13万人に対して即受け入れ可能な病床数は3万8千床しかない。
1月上旬の約2万8千床から上積みできたのは8千床のみだった。
ところで厚生労働省によると4月末時点の一般病床約89万床の使用率は66.5%。
約30万床もの空き病床が存在しているのにコロナ対応には役に立っていない。
全病床に占めるコロナ病床の割合は、ワクチン接種が進む前の段階で英国では2割、米国では1割を超えたが、日本では最大4%弱にとどまる。
これにはいくつかの理由がある。
一つは1病院当たり10床未満の病院が少なくないということだ。
欧米諸国では、100床単位でコロナ対応病床を集約して医療資源を有効に使っている。
日本では大規模病院の数が圧倒的に少ないということだ。
もう一つはコロナ即応病院が積極的にコロナ患者を受け入れていないという状況があるのだ。
「7月29日時点、コロナで入院している患者は都内に約3000人。
確保病床の半分にすぎないのに、
一部病院からは『ほぼ満床状態』『退院直後に新規入院がある』と悲鳴が上がる。
ある病院関係者は『政府の補助金を受けて病床を確保しながら、
積極的に患者を受けない病院がある』と明かす」(7月22日日経新聞)。
新型コロナ対応病床の増加がこれ以上期待できない状況を踏まえて、
医師会が野戦病院方式の導入を提案している。
体育館や公会堂などの大規模施設に病床を可能なかぎり並べて、
専門の医療スタッフが先端的な医療機器と投薬で対応しようという方式だ。
現在自宅療中の発症者をここで受け入れて、発症初期に治療を行い、
万が一重症化したら即時に重症者対応病院へと移送することが可能になる。
軽症者を重症化させないための初期対応がもっとも大事なことだと言われている。
重症者を増加させないことが新型コロナとの闘いで最も大事なことだ。
そして何よりも医療スタッフからのケアもなしに、
自宅で不安に苛まれる療養者がゼロになる状況を一刻も早く作ることが政治の役割だ。。
河川の氾濫や大地震などの緊急時に、住民が公民館や体育館に避難するように、
新型コロナも緊急事態であるとすれば大規模な「避難先」を設けて、
住民の安全を確保することは至極当然のことに他ならない。
政府が一刻も早くこの方式の導入を宣言し、自治体に対してこの方式の早期実現に向けて予算を十分に付けて指示を出すことが望まれる。
まだ30兆円ものコロナ対策用補正予算が執行されずに待っている。
原発に依存しない電源計画を
経産省は2030年時点での電源別のコスト試算を公開した。
これによると太陽光発電のコストが原子力発電のコストを下回り最低コストになる。
今回の試算は電気を安定して届けるためのコストを含んでいない。
天候による電力供給の不安定を別電源で吸収したり、夜間の供給のために蓄電するなどの調整コストは含まれていない。
経産省はこうした調整コストを含めた発電コストを「限界コスト」と定義。
参考値として示した。
「それによると、事業用太陽光は30年時点で18.9円、陸上風力は18.5円だった。
一方、原子力は14.4円、
LNG火力は11.2円、
石炭火力は13.9円で、
いずれも太陽光と風力を下回った」。
50年までにカーボンニュートラルを実現する目標を政府は掲げている。
今回の試算はこの目標達成のための電源構成を作成するための前提データになる。
この試算には二つの問題が含まれている。
1. 再生エネルギーによる発電コストの世界標準に比して日本のコストは異常に高い。
「エネルギー白書2021」によると2019年における再生エネルギーによる発電コストは、以下の通りだ。
洋上風力 0,12¢
太陽光 0.07¢
陸上風力 0.05¢
水力 0.05¢
2. 原子力発電の「限界コスト」には、使用済み核燃料の廃棄コスト、原発事故による被害補償のための損害保険料などは含まれていない。
経産省は「限界コスト」などという曖昧な概念を持ち出して、
30年においても原発のコストが太陽光を下回ると主張している。
その背景には原発に依存する電源計画を策定する意図がありありと透けて見える。
しかし原発は一刻も早く停止し、全てを廃炉に持ち込むことが最善策だ。
福島の事故ではいくつもの奇跡的な偶然が重なって、
東日本の壊滅的な被害を回避できた。
原発事故は発生すれば取り返しのつかない被害を及ぼし、
また激甚な災害をもたらすリスクを予めヘッジすることも不可能なのだ。
原発を即時停止し、原発に依存しない電源計画を持つことは、再生エネルギーの急速な普及とコストダウンの劇的な進展を促す。
福島事故を受けてドイツのとった原発脱却政策がこのことを雄弁に物語る。
先に見たように日本の再生エネルギーの普及の著しい遅れとコストの高止まりは、いまだに原発を主力電源として温存する政策が最大の障壁になっているのだ。
原発に見切りをつけることが日本にとっても、再生エネルギーの普及と大幅なコストダウンのための突破口になることは間違いない。
東日本大震災からの日本の復興はここから本当の意味で始まる。
円安が日本安を生んだ
日経新聞は4日付け朝刊で、「円安が安い日本を生む」と題する記事を掲載した。
「日本経済にとって円安はプラスなのか。
日本経済研究センターが15年の産業連関表などから分析したところ、
デメリットの方が大きい。
『外貨建てで輸出する商品の円換算額が増え、売上高が膨らむプラス効果』と、
『輸入品が値上がりしコストが増えるマイナス効果』を比べると、
対ドルで10%の円安になった場合、
国内生産額比で0.5%デメリットが上回る」。
これまでは円高は輸出企業に打撃を与えることから、
円高=株安という図式が信じられてきた。
しかも輸出で稼ぐ日本企業はより安い人件費を求めて、
あるいは為替変動の影響を最小化するために、
さらには物流費の極小化を求めて海外に工場を移転してきた。
工場の海外移転は、
円安による売上高の嵩上げ効果を更に奪うことになっている。
しかしアベノミクス以降の政府の経済政策は、
円安=株高を一途に追い求め、
「異次元の金融緩和」を演出してきた。
ひたすら円安に固執した結果何が生じたか。
1. 企業による競争優位の創出策が、提供価値の継続的革新ではなく、円安による低価格に依拠することになった
2. 低価格依存の競争優位策は人件費の削減を求めることにもなり、非正規雇用の拡大とベースアップの終焉を迎えることになった。
(1) 「経済協力開発機構(OECD)によると、
主要国の平均年収は00年以降1~4割上昇し、
日本だけが横ばい。
(2) ドル建ての賃金水準は韓国より1割近く低い」。
もはや賃金水準は新興国並みに。
(3) 賃金の伸び悩みに社会保険料の増額、
消費税増税、さらには円安による輸入食品、
エネルギー価格の上昇が加わり、
日本人の購買力は落ちて、貧しくなった。
かくして「貿易量や物価水準を基に総合力を算出する円の『実質実効レート』は、
ニクソン・ショックからピークの95年まで2.6倍になった。
その後は5割低下し、
73年の水準に逆戻りしてしまった。
円の弱体化は世界の中での日本経済の地盤沈下をそのまま映し出している」。
日本をひたすら貧しい国に引きずり込んでしまった、
アベノミクスの罪は極めて大きい。
日本は20年間も賃金が上がらない国になってしまった
ダイヤモンド・オンラインの編集委員竹田氏は、
日本が20年間もの間賃金の上がらない国になってしまったと報告している。
https://diamond.jp/articles/-/278127?page=2
「OECD(経済協力開発機構)の調査によると、日本の平均賃金(年間)は2000年時点、3万8364ドル(約422万円)で加盟35カ国中17位だった。20年には3万8514ドル(約423万円)と金額はわずかに上がったものの、22位にまで順位を下げた。過去20年間の上昇率は0.4%にすぎず、ほとんど『昇給ゼロ』状態。これでは『給料が上がらない』と悩む日本人が多いのも当然だろう」。
トップの米国の平均賃金は6万9391ドル(約763万円)で、日本は率にして44%の大差が開いている。OECD加盟35カ国の平均額の4万9165ドル(約540万円)に対しても22%低い。
なんと日本の平均賃金は19位の韓国に比べてさえ、3445ドル(約37万9000円)低い。
下図は、日米欧主要7カ国と韓国の平均賃金の推移を過去20年間で見たものだ。韓国だけでなく、米国やカナダ、ドイツなども賃金は顕著な右肩上がりで伸びている。「昇給ゼロ」状態なのは日本とイタリア(マイナス0.4%)だけである。
日本はなぜ賃金の安い国になってしまったのか?
竹田氏の分析によれば原因は以下の4つ。
1. 景気後退期に賃金調整に比べて雇用調整のタイミングを遅らせる日本の労使のビヘイビアが景気回復期にも継続した
2. 労働組合の弱体化によって経営者に対する賃金の継続的引き上げのプレッシャーが弱くなった
3. 雇用の流動性が進展せず労働市場での労働価格の決定力が今だに弱い
4. 賃金伸び悩み→個人消費伸び悩み→企業業績伸び悩み→賃金伸び悩みの悪循環
賃金上昇の伸び悩みをこれだけで説明するには十分ではない。
さらに追加すれば以下の要因も考慮に入れなければならない。
1. 不況期の雇用調整の圧力弁として非正規労働の雇用が急拡大した
2. 株主第一を求めるガバナンス改革によって配当の増加などの株主への分配額が拡大した
3. 経済のグローバル化による成長途上国からの低価格輸入品との競争に引きづられて賃金が据え置かれた
4. 消費税の増加と継続的円安傾向が購買力を押し下げ実質賃金の低下に繋がった
20年間日本のGDPもほぼ横ばいのままだ。つまり国民経済規模で付加価値額は増加していない。
しかし付加価値の配分において金融資産に関わる所得と企業の内部留保が拡大し、賃金所得の縮小が進行した。
つまりは付加価値額が増大しないまま富裕層と大企業への配分が継続的に増加し、
実質賃金所得への配分が抑制されてきたことに根本要因を見ることができる。
しかも大企業に蓄積された内部留保は有効に投資に向かうことなくいたずらに蓄積されたままだ。
二つの打開策が講じられるべきだ。
1. 消費税を廃止し、法人税と富裕層向けの増税を実行すること。消費税の廃止は実質賃金の増加を実現し、個人消費拡大→企業収益拡大→賃金上昇→消費拡大の好循環を生み出す
2. 企業の内部留保をグリーンとデジタルのとタンスフォーメーションのための積極的な投資に向かわせる。これによって衰退する日本の経済構造の大転換を起動させるトリガーが引かれることになる。
EV製造工場のCO2排出量ゼロは素材メーカーの新素材開発が決め手
自動車メーカーはEVへの転換と同時に、
工場でのCO2排出量ゼロを目指して鎬を削っている。
工場でのCO2排出量ゼロは熱源を再生エネルギーに変えるだけでは達成時期を短縮できない。
加工工程での熱消費量の削減が不可欠だ。
こうした流れを受け、自動車会社が素材メーカーと連携する動きが広がっている。
7月23日の日経新聞朝刊は、
「車部品、新素材でCO2減」と題する記事を掲載した。
「化学や鉄鋼各社が自動車生産時の二酸化炭素(CO2)を減らす素材技術の開発に力を入れている。
旭化成はCO2を最大で1割減らせる塗料材料を2026年にも量産する。
JFEスチールは車体成型時のCO2を抑える鋼材の加工技術を実用化した。
自動車産業の課題である脱炭素を素材の面から後押しする」。
いずれのケースも塗装や鋼材のプレスなどの加工工程での高熱による処理をより低い温度で可能にする技術開発を実現した。
旭化成の新素材塗料は塗装工程の温度を140℃から80℃へと下げられる。
JFEの新素材鋼板はプレス工程の温度を900℃から常温に引き下げることに成功した。
低温で加工することが可能になったことで、エネルギー消費を大幅に削減することが可能になった。
ところでEUは2035年に内燃機関車の販売を禁止する方針を決定した。
これに対応して自動車メーカーのEVシフトと、
工場のCO2排出量ゼロへの動きが本格化している。
独フォルクスワーゲン(VW)傘下のポルシェは、
ドイツの工場でCO2排出量の実質ゼロを達成した。
独ダイムラーも高級車メルセデス・ベンツの工場の排出量を、
22年から実質ゼロにする目標を掲げる。
これに比べて日本の対応は遅れている。
トヨタ自動車は全世界の工場でCO2排出量を実質ゼロとする時期を、
50年から35年に前倒しする。
日本の自動車メーカーのEV化はまだ周回遅れを脱していないようだ。
JOCは「オリンピック憲章」を蔑ろにしている
7月23日日経新聞朝刊は、「五輪組織委、止まらぬ迷走」と題して、
東京五輪をめぐる混乱を批判した。
「東京五輪の運営を担う大会組織委員会の混乱が収まらない。
開会式を翌日に控えた22日、
ショーディレクターを務める元お笑い芸人の小林賢太郎氏を過去のコント内容を巡って解任した。
かねて不祥事は相次ぎ、
19日には開会式の楽曲担当者が辞任したばかり。
根底にある人権意識の希薄さや「密室体質」を払拭できず、
東京五輪そのもののイメージを損なった」。
東京五輪組織委員会の幹部は、
「五輪憲章」に一度でも目を通したことがあるのだろうか。
五輪に関わる以上は「五輪憲章」が全てに優先する理念であり、
価値基準であって、全ての意思決定において、
判断基準に据えられなければならないはずだ。
「五輪憲章」に高らかに謳われている価値基準は、
「普遍的で、根本的な倫理規範の尊重を基盤として」、
「生き方の創造を探究することである」。
そのためには「あらゆる差別を排除しなければならない」ということだ。
そしてこの理念を追求する五輪に関わるスポーツ団体は、
あらゆる外部からの影響を排除するために、
自らの自律性を絶対的に維持するガバナンスを、
実現しなければならないとされている。
この憲章に照らしてみたとき、
IOC、JOCの意思決定は、
人種差別やジェンダー差別に無頓着であるという意味で、
五輪憲章が掲げる理念を尊重せず、これを基盤としていないことは明白だ。
またJOCは国民の過半がオリパラ開催の中止や延期を求めていることを一顧だにせず、
日本の政権及びIOCの「何がなんでも開催する」,という意思に,
直接間接の影響を受けるという意味で、
自らの自律性を失っている。
このような意味でJOCのガバナンスはすでに崩壊していると言わざるを得ない。
そもそもIOC幹部が五つ星ホテルのスイートルームに連泊することも、
開催式のチケットが30万円であることも、
あらゆる差別の排除を嘔う五輪憲章に照らして妥当性を欠くと言わざるを得ない。
オリンピックの開会式を迎えた今ここに至っては、
晴海の選手村がコロナ感染の集積地とならないことだけを切に祈るばかりだ。
参考までに「五輪憲章」の一部を下記に掲載しておく。
1. オリンピズムは肉体と意志と精神のすべての資質を高め、バランスよく結合させる生き方の哲学である。オリンピズムはスポーツを文化、教育と融合させ、生き方の創造を探求するものである。その生き方は努力する喜び、良い模範であることの教育的価値、社会的な責任、さらに普遍的で根本的な倫理規範の尊重を基盤とする。
4. スポーツをすることは人権の1 つである。すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。 オリンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が求められる。
5. オリンピック・ムーブメントにおけるスポーツ団体は、スポーツが社会の枠組みの中で営まれることを理解し、政治的に中立でなければならない。スポーツ団体は自律の権利と義務を持つ。自律には競技規則を自由に定め管理すること、自身の組織の構成とガバナンスについて決定すること、外部からのいかなる影響も受けずに選挙を実施する権利、および良好なガバナンスの原則を確実に適用する責任が含まれる。
6. このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。
デジタル庁を機能させるには
デジタル庁の前身組織IT室によるVRSの開発
デジタル庁が9月に発足する。500人の規模の組織になるようだ。
その母体となる内閣官房IT総合戦略室(IT室)が50人のメンバーを投入して先行開発したのが新型コロナウイルスのワクチン接種記録システム(VRS)だ。
VRSは次のような機能を持つ。
l ワクチン接種予約の個人情報の記録
l ワクチン接種実施の個人情報の記録
l ワクチン接種の個人情報の提供
l ワクチン予約および接種の統計情報の提供
l ワクチンパスポートの提供を可能にする
VRSのシステム要件は次の通りだ。
l VRSの個人情報はマイナンバーと紐つけされる
l VRSの個人情報はIT室が管理するクラウドサーバーに蓄積される
l 個人が自治体を超えて移動しても情報の提供が可能
l ワクチン接種に関わる情報は、自治体、クリニック、大規模接種会場等ワクチン接種に関わるすべての機関で入力可能
開発期間2ヶ月は短期間と言えるか
VRSはほぼ2カ月という異例の短期間で開発したと言われる。
これまでの政府のシステム開発の先例からすれば異常な早さと言えようが、世界標準の効率からすれば普通とも言える水準でしかない。
本来ならばワクチンのSCMの実態を記録して管理する機能が付加されるべきなのだが、その機能を含めてのことならば、異常に早いスピードだと評価することもできよう。
しかも問題なのはワクチンSCMの機能についての方針が未だに全く示されていないことだ。
最近になってワクチンの自治体間の偏在や、そもそものワクチン供給の実態が極めて不透明なことが国民の不信、不安を招いていることからすれば、ワクチンSCMのIT化はそれこそ異例の迅速さで開発されてしかるべきだろう。
そもそもワクチン接種の課題は1年以上も前から呈示されていたことからすれば、ワクチン接種が開始される間際になって初めて開発が俎上に乗ること自体、政権の課題設定の優先順位付の不具合というIT開発以前の問題が露呈されたと言わざるを得ない。
この一事からも中央政府の機能不全が極まっていることが一目瞭然なのだ。
デジタル庁が機能するためには何が必要か
デジタル庁は担当大臣のもとに事務次官相当の「デジタル監」を民間から起用し、さらに総勢500人のうち約100人を民間からの公募で集めている。
DXの実現にとってもっとも大事なことはデジタル人材の内製化だ。つまり政府も企業もデジタル人材を組織内で抱え、DX実行力を組織自身の課題解決エンジンとして機能させることが大前提となる。
政府のデジタル人材は極めて貧弱であることから、デジタル庁設置にあたっては中途採用で民間からの多様な人材を集め、組織のほとんどを民間人で占めるくらいにしなければならない。
当然のことながら事務次官もあるいは大臣自体も民間からスカウトすべきだ。
これまでの政権、政府の組織原理にどっぷり浸かった政治家や官僚にはイノベーションは起こせないと腹をくくるべきなのだ。
上司に忖度する組織風土からは改革は実行できない。人材は手垢の付いていない民間から高給で獲得するべきだ。
デジタル省でなくていいのか
そもそもデジタル化によって国家、国民の課題を解決することがデジタル庁の目的であるならば、デジタル省にしなければ実効性はほとんど期待できない。
デジタル省にした上でデジタル省は政府全省庁のデジタル予算を全て巻き取ることが可能になる。また政府全省庁のデジタル人材は厳選した上で、デジタル省に異動させる。残りのデジタル人材は各省庁でスタッフのデジタル・リテラシー拡張に貢献し、同時にデジタル省の開発する新システムの定着に貢献すれば良い。
その上で全省庁の抱えるデジタル化による課題の整理と優先順位付ができて初めて政府のDX化の道が拓ける筈だ。
こうした条件整備を整えた上でならば、政府のDX化は次のような理路によって中央政府の革命的な機能拡充に道を拓くことになるはずだ。
l 官庁の縦割り構造の土手っ腹に風穴を開けて、全官庁組織横断的な課題追求型組織への転換を実現する
l 政府の政策実現状況の完全な透明化の実現
l 政府の政策実現に伴う作成全文書の完全保存、改ざん防止の実現
l データに基づく実態把握を前提とした政策提案の実現
最低賃金を引き上げよ
政府の「骨太の方針」に最低賃金を早期に全国平均1,000円に引き上げることが掲げられた。
これを巡って日経新聞のコラム『大機小機』は、「最低賃金を引き上げ、所得増を起点に新たな経済の好循環を生み出すとの考えは危ういのではないか」。と危惧を表明した。
その論点は二つ。
「基礎的な経済学が教えるところでは、実質賃金(名目賃金÷物価)が上昇すれば企業は雇用を減らし、失業者が増加する」。
「賃金上昇は、生産性向上の成果配分として労使間交渉を経て決まるもので、最低賃金はそれに合わせる形で公正性の観点から引き上げられていくべきものだ。賃金と物価を操作しようとすれば、経済に大きなゆがみを生みかねない」。
そして次のように結ぶ。「最低賃金さえ引き上げれば経済情勢が改善すると企業や労働者が思い込むと、生産性向上に取り組む意欲がそがれてしまう」。
筆者の賃金引き上げが経営者、並びに労働者の生産性向上に向かう意欲を削いでしまうという懸念はあたらない。
バブル崩壊から30年間の日本の生産性の伸びは精彩を欠いている。一人当たりのGDPを見れば一目瞭然だ。(図1)
しかし同時にこの30年間日本企業の内部留保は継続的に積み上がり500兆円の規模にも達した。(図2)
企業は30年間利益を出し続けてきたことは間違いない。企業収益の拡大を支えたのは賃金の低水準のままでの維持と法人税の引き下げの二大要因だ。
法人税率は40%から23%の水準にまで引き下げられた。(図3)この法人税率引き下げの原資は消費税率の引き上げによって賄われた。消費税は社会保障政策の充実に向けられることが目的であったはずなのだが。
そして賃金水準は引き下げられ、先進国の中での劣位が際立ってきている。(図4)
明らかに日本企業は賃金を低水準のままに維持し、しかも法人税の引き下げによる税引き後利益の拡大によって、30年間増益基調が続き、それによって得た利益を配当を手厚くすることに回しただけで、生産性の向上や画期的なイノベーションに投資することなく、内部留保として積み上げ続けてきた。
結果として何が起きたか。給与所得の伸び悩みはそのままストレートに消費水準の拡大に水を差し、結果としてGDPはもはや縮小軌道を余儀なくされることになった。
つまり日本企業は生産性の向上に向かう努力を放棄してきた。それでも利益を増加させることができたからだ。なぜなら賃金と法人税が継続的な引き下げに応じてくれていたからだ。
賃金を引き上げると生産性向上に向けて努力をしなくなるなどというのはあたらない。むしろ生産性をあげる意思を持たずともなんとかなってきたのだ。つまり企業努力をせずとも利益が上がる軌道が敷かれていたのだ。
となるとむしろ思い切った賃金引き上げを強制的に強いること、つまりは最低賃金を世界水準を上回るところまで引き上げることが、企業経営者に生産性の向上に向かうモチベーションを注入することになるに違いない。
最低賃金は1,000円ではなく2,000円を目指すべきだということになる。企業を生産性向上に本気になって向かわせる方法は外圧に拠らざるを得ないというある意味で末期的な状況にあるということだ。
図1一人当たりGDP推移

図2内部留保推移

ボード(取締役会)3.0
以下のメモは日経新聞21.06.01朝刊の記事に依拠している。
取締役会にバージョン・アップの兆しが現れ始めた。
投資ファンドのエンジン・ナンバーワンは脱炭素社会にふさわしい戦略を再構築することを目的に、米エクソンモービルに社外取締役を送り込むことに成功した。
彼らが送り込んだ取締役は、米コノコフィリップスで長く経験を積んだグレゴリー・ゴフ氏やフィンランドのネステで代替燃料事業にかかわったカイサ・ヒータラ氏など、カーボン・ニュートラル時代に相応しい戦略立案に貢献すると思われるエネルギー業界の専門家だった。
これまで企業統治モデルは次のような進化をしてきた。
ボード1.0 1950年代〜 独立社外取締役が経営陣に助言
ボード2.0 1970年代〜 独立社外取締役が外部の視点で経営をモニタリング
50年を経過して、「2.0」では時代の変化に追いつけず、CEOの孤立と暴走を止められないとの指摘が増えた。リーマン・ショックは象徴的な具体例として語られる。
そしてボード3.0の兆しが今回のエクソンモービルで始まった。
独立社外取締役が戦略立案やビジネスモデルのデザインに関わる企業統治のかたちだ。
提唱者は米コロンビア・ロー・スクールのロナルド・ギルソン教授とジェフリー・ゴードン教授だ。
日本企業の企業統治はまだボード1.0でまだウロウロしている状況だ。
この周回遅れを挽回するには、一気にボード3.0へと踏み出し、経営戦略の策定に向けて知恵を絞れる人材を取締役に招致しなければならない。
業界の専門家であることは必須ではない。外部の業界で戦略経営を実践し、圧倒的な業績を実現してきた経営者であるなら取締役候補者たりうる。
むしろ他業界の経験者の方が優れた提案を頻発できる可能性が高い。
日本企業が長引く低迷期を乗り越え、VUCAの時代に置いて飛躍するには、こうした人材を揃えて真っ当な経営戦略を創出し、その実行を監視する形の企業統治への大転換が唯一の道だ。
2021年9月9日に次の記事が掲載された。
戦略機能の実装に向けて踏み込んだ提案がなされている。
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210909&ng=DGKKZO75567180Y1A900C2TCR000
電力各社は原子力を管理する能力を持っていない
テロ対策などから原発の核物質のある区域の出入りは、
厳重に管理しなくてはならないが、
日経新聞5月20日朝刊によれば、
原子力規制委員会は19日、
4原発で核物質がある防護区域の管理が不十分だったと発表した。
具体的には、
・ 福島第2原発では1~4号機の防護区域境界にある出入り口で金属探知機の手続きに不備があり、指摘を受けて扉を閉鎖した。
・ 同じく福島第2原発では不要になった社員のIDカードの回収を怠っていた。
・ 浜岡原発では関連会社従業員が立ち入り手続きをせずに原発内に入った。
・ 伊方原発では周辺防護区域に至る場所で閉鎖措置が不十分な開口部があった。
・ 柏崎刈羽原発でテロ対策の不備が発覚した。
このように東京電力、中部電力、四国電力の原発で、
ずさんな管理状況が指摘された。
原発事故は福島原発の事故で明らかになったように、
国の存亡を左右する巨大なリスクを抱えている。
この巨大なリスクを管理する能力を持つことはある意味で不可能に近い。
ましてやこのような危険なシステムを防御するための、
施設入退所管理すらできない企業が、
原発の持つ巨大なリスクに対する管理能力を備えることが可能だとは、
全く考えられない。
米国ではハッカー集団の社会インフラへの攻撃が、
社会生活を脅かす事件が発生している。
こうした新たなリスクの発生も次々に予想される。
原発のリスク管理はますます困難を極めることになる。
地震や火山噴火などの自然災害への備えも、
人為的なテロによる攻撃への備えも日本の電力企業には手に余る。
原発は即時に停止し、廃炉への道を歩むことを決断すべき時期にきている。
バイデン大統領の大規模経済再建計画
米国のバイデン大統領による大型経済対策が矢継ぎ早に進められている。
29年の大恐慌にルーズベルト大統領が実施した「ニューディール政策」の現代版だ。
コロナ対策
まずは3月11日に新型コロナ対策の経済対策法に署名した。
これによって次の政策が実行に移される。
・ 高額所得者を除くほとんどの国民に1人あたりり最大1400ドル(約15万円)が支払われる。
・ 週300ドルの失業保険の追加給付期間が9月6日まで延長される。
・ 数百万人を貧困から救うことが期待される、子どものいる世帯への税額控除。
・ 州政府や自治体には3500億ドル、学校には1300億ドルが支給される。
・ 新型コロナウイルス検査の拡大や研究に490億ドル。
・ ワクチン供給に140億ドルを支出する。
これに続いて大統領は28日夜に、
今後10年に及ぶ「米国家族計画」ならびに「米国雇用計画」について方針を示した。
米国家族計画
米国家族計画は、子育てや教育の支援、
人種や所得の違いなどで生じる不公平の削減を目指し、今後10年で1兆ドルの財政支出を計画している。
その中核政策は以下の通りだ。
・中低所得層の保育負担の軽減に2250億ドル。
・ 介護など包括的な有給休暇制度の確立に2250億ドル。
・ 幼児教育の機会拡充に2000億ドル。
米国雇用計画
米国雇用計画は以下の政策を中心に、15年間で2兆ドルを見込んでいる。
・ 米国雇用計画は道路、橋、EV用の充電設備などのインフラ投資に6,210億ドル。
・ 学び直しの機会を増やすため、日本の短大にあたるコミュニティーカレッジの無償化に1090億ドル。
財源は?
これだけの大規模政策の財源はどのように設計されているのだろうか。
富裕層向けの増税と、法人税の増税で賄う設計だ。
富裕層向けの増税策は以下の通りで、10年間で1.5兆ドルの増税を見込む。
・ 連邦個人所得税の最高税率を37%から39.6%へ増税。
・ キャピタルゲインの税率を現行の20%から39.6%へ増税。
法人税の増税策は以下の通りで、15年間で2.5兆ドルの増税を見込む。
・ 連邦法人税率を20%から28%へ増税。
・ 多国籍企業の海外収益に21%課税(現在の2倍)。
・ 大企業の会計上の利益に最低15%を課税するミニマム税の導入。
・ 歳入庁による税務調査の厳格化で脱税を摘発し、10年間で7,000億ドルの増税を見込む。
法人税率の世界標準化
増税によって、租税回避がとりわけ法人のそれが懸念される。
これに対して法人税率を世界各国で共通の税率にすることが求められる。
すでに米国は先進国に対してその呼びかけを開始している。
コロナによる経済に対する打撃はあらゆる国の経済を困難に陥れている。
とすれば大規模な経済対策は世界共通に必要なはずだ。
コロナ禍を奇貨として法人税率の共通化が進むことを期待したい。
カーボンニュートラルを名目に進められる原発再稼働・増設を許してはいけない
政府は22日、30年度の温暖化ガス排出量を、
13年度から46%減らす目標を公表した。
国内の温暖化ガス排出量の約4割を発電部門が占めている。
46%目標の設定に伴って、
経産省は発電部門の脱炭素電源の割合を、
現在の24%から50%以上を目指す方針を掲げた。
この時の電源種類別の現状値と30年目標値は以下の通りだ。
・再生可能エネルギー 18%→30%台
・原発 6%→20%
・化石燃料火力 76%→40%台
原発がカーボンニュートラルに不可欠の前提として、
大手を振っての登場となっている。
しかもこの目標は原発の数字を、
30%まで引き上げないと実現しないという含みを持たせてさえいる。
とすると原発は全基再稼働、更に増設も視野に入ることになる。
原発は地震大国日本にとって国を滅亡させるほどのリスクだ。
福島原発のメルトダウンが大地震による、
配管、配線の破談、機能不全によって引き起こされた、
しかも原子炉格納容器の爆発や、
使用済み核燃料プールの蒸発が、いくつもの偶然によって幸いにも回避された、
という事実がこれを雄弁に物語っている。
とすれば原発はあくまでも稼働ゼロを前提に、
長期的な目標設定をしなければならない。
原発が封じ手であるとすれば、
再生可能エネルギーと省エネだけを手段として追求することしか方法はない。
この戦略目標を設定することで、
日本のエネルギー産業の革命的な再構築が可能になる。
それは同時に日本のエネルギー産業が世界的に圧倒的な競争優位に立つことにもつながるはずだ。
かつて排出ガス規制を世界で最も厳しい基準でクリアーした、
日本の自動車産業が、世界を席巻したように。
米国の脱税額はなんと年間1兆ドル
日経新聞21年4月23日朝刊によると、
米国の脱税額が年間1兆ドルにも及ぶらしい。
「IRS(米国内歳入庁)のチャック・レティグ長官が、
4月13日の米上院財政委員会の公聴会で、
脱税の規模は年1兆ドルに上ると推定されると証言した。
脱税額の大半は、米国の納税者の所得上位1%によるものだ」。
なんとも巨額な脱税が見逃されていることか。
バイデン政権の掲げる8年間で2.1兆ドルのインフラ投資の、
4年分に相当する額だ。
かくも巨額な脱税がなぜ放置されているのか。
その要因は二つ。
一つは杜撰な税法。
「米国の税法は悪名高きザル法として知られる。
実際、2020年、米ナイキや米フェデックスを含む米最大手の企業55社は、法人税を全く納めていない。
55社で総額にして約400億ドル(約4兆3000億円)もの利益を上げた、
にもかかわらずだ」。
二つめの要因はIRSのリストラが継続し、
税務調査が骨抜きにされていること。
「IRSは11年以降、予算を実質計20%近く削られてきた。
その予算はGDP比で見ると約3分の1減らされた形だ。
削減された税務調査官は約1万7400人に上り、
その多くは非常に熟練した人材だった」。
バイデン大統領はトランプ時代に35%から21%に引き下げられた法人税を、28%まで引き戻す方針を示している。
増税と脱税の回収を合わせれば、
米国政府の財政赤字は最も簡単に解消されるに違いない。
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210423&ng=DGKKZO71266570S1A420C2TCR000
戦略的な改革を矢継ぎ早に進めるEU(2)
日経新聞4月10日朝刊は、欧州委員会が21年4月9日、30年達成納期のEUのデジタル改革目標、名付けて「デジタルコンパス」を発表したと報じた。
記事によるとEUのデジタル戦略目標は以下の4本柱からなる。
1. デジタルリテラシーの向上と高度デジタル技術者の育成。
(1) IT専門家を2000万人に増やす。19年現在は780万人。
(2) 成人の80%が基本的デジタル技術を習得(現状は58%)。
2. 安全・高性能・持続可能なデジタルインフラの整備
(1) 全家庭にギガビット通信を接続(現状は59%)
(2) 全ての居住地域で第5世代移動通信システム(5G)を提供(現状は14%)
(3) 気候中立に対応した高セキュリティーなエッジノード(クラウドサービスと接続する基地局やルーターなどの情報機器、処理装置を1万台配備し、域内のあらゆる地域のビジネスに対してデータサービスへの遅延のないアクセスを保証(現状は配備なし)
(4) 次世代半導体の生産シェアで世界の20%をめざす。
(5) 2030年までに量子情報処理技術で世界をリードするために、2025年までにEU初となる量子コンピュータを導入
3. 企業のDX推進に対する支援。
(1) 域内企業の75%がクラウドサービス(現状は26%)、ビッグデータ(現状は14%)、人工知能(AI、現状は25%)などの技術を活用
(2) 域内中小企業の90%以上が最低限の基礎的デジタル技術を活用(現状は61%)
(3) ユニコーン企業(企業価値が10億ドルを超える未上場企業)を育成し、現在の2倍となる250にする。
4. 公的サービスのデジタル化
(1) 公的サービスのオンライン経由での提供を促す。
(2) 電子カルテを普及させる全てのEU市民が電子医療記録にアクセス可能に
(3) 80%のEU市民がデジタルIDを利用
デジタルを社会の隅々まで普及し、社会・経済改革の手段として徹底的に活用するための戦略目標が示されている。
いずれも現状値とともに具体的な目標が設定されている。
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf
EUのデジタル化に向けた方針に比べて、日本政府の取り組みは周回遅れだ。
デジタル庁の創設は決まったが、これも9月にやっと組織が出来上がる。
その組織の中で今後の方針が揉まれて日の目を見るのは多分来年あたり。
具体的な活動が始まるのは22年度からということになりそうだ。
戦略的な改革を矢継ぎ早に進めるEU(1)
EUはカーボンニュートラルを目指して大胆な目標を設定して、50年には発電を100%再生エネルギーで賄う政策の実現に向けて確実な動きを進めている。
EUの革新的な政策は地球環境分野だけでなく、男女間の賃金格差の是正や半導体の自給率の向上そしてデジタル・トランスフォーメーションといった領域でも矢継ぎ早に進行している。
EUの男女間賃金格差是正
EUの欧州委員会は男女間の賃金格差解消に向けて、2年先の加盟各国での新法制定を目指した指令案を策定した。指令案は大きく、
(1)賃金の透明性向上策
(2)賃金で差別された労働者への支援措置
からなっている。
具体的には以下のことが盛り込まれている。
透明性については、
・ 面接前に求職者に広告などを通じて賃金水準を明示することが義務付けられる。
・ 企業が求職者に過去の賃金水準を聞くのを禁じ、過去の情報を参考に新賃金を決められなくする。あくまでその企業の職務にあった金額を提示すべきだという考えだ。
・ 労働者に、同様の職務に就く従業員の平均賃金水準を知る権利を認め、企業は情報提供に応じなければならなくなる。
・ 男女間の賃金格差に関する情報をホームページなどで年ごとに明示することを義務付ける。
・ 格差が5%以上の場合は、企業は是正に向けた対応を求められる。
労働者への支援措置では、
・ 性別で差別を受けた労働者が企業に補償を求めやすくなるよう、裁判などで差別が存在しないことを証明する責任を企業側に負わせる。
・ 欧州委は各国での法制化の段階で、違反企業に罰金を含む罰則を科す規定を盛り込むよう求める。
こう見るととても具体的に賃金格差の是正に取り組む意思が明確に読み取ることができる。そして何よりも男女間の賃金格差の是正だけでなく、すべての労働者に「同一労働、同一賃金を保証する立法意思が確認できる。あるいは男女賃金格差に切り込むことで、「同一労働、同一賃金」への近道が見えてくるという戦略的な意図が隠されているのかもしれない。
以上が日経新聞2021.03.09朝刊の報道するところだ。
日本こそ男女賃金同一化に取り組むべきだ
EU統計局によると、19年時点でEU域内の女性の賃金は男性に比べ14.1%低いという。10年に比べ1.7ポイント改善しているものの、欧州委は不十分と判断して新法制定に踏み切る。
ところで日本の男女間賃金格差はどうか。大和総研の報告によると17年の数字で、24.5%の開きがあり、先進国7カ国中最も格差が大きい。
米国とカナダの男女間賃金格差が18.2%で日本に次いでいる。
EU内部での男女別の賃金格差は国によるばらつきが大きい。チェコ、ラトビア、オーストリア、ドイツ、エストニアなどの格差がおおきく20%近辺の実態がある。しかしそれでも日本よりはその格差は小さい。
EU委員会はEU内部でのバラツキの実態を重く見て、男女賃金格差の是正に向けて本格的な対策に乗り出したと言える。
EUのこれからの成熟化の中で女性の活躍が避けては通れない、との判断がこうした思い切った戦略的な政策を打ち出した背景にあると言える。
日本も成熟国として女性の活躍は待ったなしの課題だ。しかし日本の現状はまことに寒々しい状況にある。
賃金格差だけでなく女性の活躍を阻む実態は世界水準から見ても大きく遅れをとっている。
世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数2018」では、日本は110位/149カ国。先進7カ国では最下位だ。
日本においてこそ男女賃金格差の是正は真っ先に取り組まれるべき課題だ。
DXによる民主主義のイノベーション
2020年11月8日の日経新聞のコラム「風見鶏」で、DXと民主主義のイノベーションについての、興味深い論考が開陳されている。
民主主義は現在二つの厳しい課題に直面している。
一つ目の困難は代議制民主主義が抱える民意の反映の不完全性だ。
選挙制度によって選出された政治家が長期に渡って、多様な政治課題に対して「民意を汲んで」意思決定に加わるという代議制は、その全ての課題に民意が反映されるとは限らない。
つまり選民が自らに投票した市民の声を、その時々の多様な課題に正確に反映することにははじめから無理があるということだ。
二つ目の困難は情報の非対称性だ。
行政が生み出す情報は政府や自治体などの行政側に集積され、その情報への市民によるアクセスはきわめて限定されている。
さらに個々の市民に関する情報も行政に集約され、この情報に対する市民によるアクセスもきわめて限定的だ。
DXの活用によって代議制の限界を超えようとする試みが始まっている。
一つにデジタル直接民主主義がある。
「『複雑さを増す社会において大きな統治機構が全てを決める方法は限界にある』。ITを使い地域社会の問題解決をめざす一般社団法人『コード・フォー・ジャパン』の関治之代表理事は語る。市民一人ひとりが行政の主役になる。従来は物理的に難しかったそんな方法も『今ならテックの力で可能になる』
日本でも一部の自治体が導入を進める『デシディム』というプラットフォームはその一例だ。単なる掲示板ではなく議論の流れや賛否の状況をわかりやすく可視化し、テックで熟議を促す。開発したバルセロナは都市再開発の議論に4万人が参加し、約1500の行動計画が生まれたという。
」。
行政によるデータの独占に対しても、DXを活用して風穴を開けようとする挑戦が始まっている。
分散型ネットワークの試みだ。
「エストニアの電子政府は分散型台帳技術のブロックチェーンを使う。国は国民の情報を電子化するが、データは個人の手にあり他者のアクセスを管理・把握できる。『データ主権を個人に戻す思想』といえる」。
行政が作成する情報はことごとく電子化され、ブロックチェーン技術によって管理される。
そこでは一旦登録された情報は改竄、削除は行うことはできず、この情報に対するアクセスの事実も記録される。
そして情報に対するアクセスは法的に認められた権限を有するものに与えられる。
この権限をデジタル直接民主制によって市民の総意によって決定することで、現在民主主義の抱える二つの課題は解消に向かうことになる。
政府が取り組もうとする行政のデジタル化はこのような「民主主義のイノベーション」の実現というビジョンを掲げることではじめて、まさしく世界で最先端のデジタル国家の形成が可能になる。
読書ノート:デイビッド・モンゴメリー著『土・牛・微生物』(築地書館刊)
絶望的な農産物生産システムの現状
現代の農業は農産物の品質と収量および労働生産性を高度化するために化学肥料と農薬と高額の農機に対する依存度を極限にまで高めている。
結果として何が起きているか?
化学肥料と農薬そし高額でありエネルギー多消費型の大規模農機に対する依存は土壌の健全性を損ね、化学肥料と農薬に対するさらなる依存を招く悪循環に陥っている。そして土壌が健全性を失うことによって、土壌を取り巻く生態系が破壊され、環境破壊が進んでいる。
また化学肥料と農薬そして大規模農機に対する依存は農産物生産のコストを増加させ農業は収益事業でなくなり、個人営農者は経営の維持が困難になり農業からの離脱を余儀なくされている。
こうした状況に抵抗して世界中の先進的な農業生産者が新たな農業システムに挑戦を始め、その成果が徐々に出始め、しかもそれが他の生産者の関心を呼び始め、その画期的な農法が広がり始めているという。
本書はその新しい農産物生産システムへの挑戦を実行している生産者や研究所を訪問しその実践活動を紹介し、この新機軸が産み出す大きな価値の実態と、そうした価値の生まれる所以を明らかにしている。
新農産物生産システムの三原則
新しいシステムの原則は次の三項目だ。
1. 不耕起
2. 被覆植物による土壌の被覆
3. 多様な植物による輪作
この三原則によって何がもたらされるか。それは土壌中の有機物の活性化であり、有機物を分解して活きる土壌中の微生物の活性化だ。つまり失われつつある肥沃な土地の回復だ。
そもそも土壌中の有機物と微生物と植物の間の相互代謝関係が植物の成長を促し、また免疫力を増強して自己治癒力によって疫病を克服し、また害虫を寄せ付けない物質を発散することが本来の生態系のあるべき姿なのだ。
ところが土地を耕すことで土壌中の有機物はズタズタに破壊され死滅する。有機物がなくなると土壌中の微生物が死滅し植物に対する代謝作用を停止してしまう事になる。こうして土地は肥沃さを失う。
まさに農地を耕すという、古来から農作業の基礎中の基礎である耕起が農産物生産システムにとっては最大の障害であったということだ。
だからまさに非常識としか思えない不耕起こそが現代の農業が抱える困難を一気に解消させる打ち手として浮かび上がるということだ、
二番目の原則は被覆植物による土壌の被覆だ。
被覆によって土壌は保水力を維持し、結果として有機物の活性化を促し、微生物を活性化させることになる。さらに被覆は水分を含まない表土が風によって飛散し土壌の希薄化つまりは土地が痩せる事態を阻害する。
三番目の輪作は畑作においてはよく知られている農法だ。同じ植物を毎年植えると土壌が貧困化する。西洋史で学習した「三圃式農法」がまさにこれだ。欧州の中性に常識的であったこの農法は化学肥料の活用によって忘れられ、過去の物となっているのだ。
三原則が農産物生産システムを持続可能な物に転換する
三原則は土壌の健全化を保証する画期的な農法だ。これによって植物は土壌中の微生物との協働作業によって健全な生育を保証され、化学肥料や農薬の多用という悪循環から抜け出すことが可能になり、やがてそれらをまったく使わずに済む事態も可能にするはずだ。
そして不耕起は高額な農機の使用という必要性を解消し、個人農業生産者でも手軽に購入し、エネルギーの多用を要しない簡単な農機で生産が可能になる訳だ。
結果として農業生産者は化学肥料、農薬、農機、エネルギーに関わるコストをゼロに近いところまで削減でき、しかも収量は従来と変わらないかそれより増加する状況を楽しむことになる。
農産物生産システムは国家の補助金から自由になり、しかも収益も増加し、楽しい日々を生産者に保証することになる。
堆肥の重要性
持続可能な農産物生産システムにとって忘れてならないのは堆肥の力だ。堆肥は土壌中の有機物の活性化を促す大きな要素だ。堆肥の活用によって従来型のシステムに比べて収量の増加が期待できるはずだ。
著者もこのことに気づいていて、農地で牛を放牧し、牛糞の作用で土壌が活性化することに言及している、著書のタイトルにも「牛」が突出している。
しかし持続可能な農表生産システムの原則に堆肥は掲げられていない。この点は本書の残された課題ともいえるのではないかと考えられる。
筆者としては持続可能な農産物生産システムの原則は堆肥を追加して四原則に是非ともしてほしいところだ。

読書ノート:デイビッド・モンゴメリー著『土・牛・微生物』(築地書館刊)
読書ノート:マイケル・ウオルフ著『炎と怒り』(早川書房刊)
トランプ政権誕生からバノン大統領補佐官の辞任までのドキュメンタリーだ。
なぜトランプは大統領になれたのか
読者はまずトランプ大統領誕生の秘密を知って驚くに違いない。その秘密とは、トランプ選挙対策陣営のすべての人々が、トランプ自身を含めて誰一人として「トランプが大統領に当選するはずはないと」確信していたことだ。
このような負の自信に満ちた選対の人々は、「負けるに決まっているが、クリントンに対してここまで接戦にこぎ着けられたことで、その戦いに参加し貢献した自分の次のキャリアは輝かしいものになるに違いない」という事を唯一のモチベーションとして戦っていたのだ。
万が一にもあり得ない事が起こってしまったことが、トランプの大統領就任以後の信じられないドタバタを生み出すことになったというわけだ。
トランプ氏はなぜ大統領になるはずがないと自身の選対陣営からも信じられたのだろうか。それはトランプ氏が大統領にはあまりにもふさわしくない人物だったからだ。それを示すトランプの桁外れの非常識さを挙げ出せばきりがない。
トランプは自己中心で、わがままで、平気で嘘をつき、とても飽きっぽくて、すぐに怒りを露わにし、演説は支離滅裂で、紙に書かれた情報には見向きもしない、だから常識がなくて、そのうえ無知なのだ。
しかしインテリが大半を占める政治家や官僚やマスコミの人々から見たら異星人のようなトランプだからこそ大統領選にお見事な勝利を納め、トランプに票を入れた人々さえも信じなかった状況を作り出したのだ、
そうトランプは無知だから強いのだ。常識がないから強いのだ、単純にしか考えられないから強いのだ。つまり大衆そのものだったのだ。だから大統領になってしまったのだ、まさしくトランプはポピュリストそのもので、自分の意思を大衆の意思に重ね、結果として大衆の意思を占有できたからこそ大統領選に勝つことができたのだ。
トランプの実像
トランプ大統領は理屈に基づく意思決定はしない、あるいはできない。彼にとっては直感こそが意思決定のよりどころなのだ。そしてその直感は、「自分がヒーローになれるか?」という価値判断のみに基づく直感なのだ。
「誰もがトランプが好きだ。そしてトランプをヒーローだと思っている」。これこそがトランプを安心させる状況なのだ。この状況にマッチしない不都合な現実や論評はすべて「フェイクだ」と片付けられるハメになるわけだ。
ロジックの積み重ねによる判断は説明が可能だ。しかし直感に基づく判断は説明不能だ。「フェイクだ!」というような断定的な決めぜりふをぶつけるしかない。トランプがtwitterを活用するのは決めぜりふを投げかけるメディアとして最高だからだ。Twitterは短文しか受け付けないから、説明的な長文を書けないトランプにはもってこいのメディアなのだ。
大衆はこれまで政治を牛耳ってきた政治家、官僚、マスメディアというエスタブリッシュメントの掲げるきれい事の政策をいつもうさんくさく見ている。既成勢力がいかに美しいビジョンを掲げようと大衆の生活は一向に良くならない。むしろ大衆は追い詰められていると感じている。
大衆の置かれたこの状況を鋭く感じ取り、直感的な言葉で現実を断罪したからこそトランプは大衆を代弁することができたのだ。「グローバリゼーションこそ大衆を貧困に追いやっている」などという理屈は抜きに、「アメリカ・ファースト」だけを語ったからこそ大衆はトランプに期待をかけたということだ。
トランプ抜きのトランピズム(トランプ主義)
トランピズムの教祖は実はトランプではなくバノンだ。バノントランプ大統領を巡る補佐官や閣僚メンバー内での権力闘争に敗北して下野した。バノンはまさに軍人やゴールドマンサックス人材からなるエスタブリッシュメントとジャレットとイバンカのトランプ親族派閥の連合軍との戦いに敗れたのだ。
しかしバノンはトランピズムのもつ大衆を取り込む圧倒的な力を信じかつそれを自ら体現する力をこの間しっかりと身につけることができた。
バノンはトランプ政権はもはや一期4年を全うすれば御の字でむしろ4年も持たないと判断している。
ロシア疑惑にはじまりポルノ女優との不倫などトランプを追い詰める輪は徐々に狭まってきている。この状況を踏まえてトランプに代わってトランピズムの教祖として大統領選に打って出ようというのがバノンの戦略だ。
虐げられた大衆を巡る右と左の闘争
一方バーニー・サンダースを教祖とする民主党左派もリベラルな大衆の代弁者として依然として勢力を拡大しつつある。
となるとアメリカの次期大統領選挙は極右と極左による大衆の争奪戦になることが予想されることになる。
読書ノート:マイケル・ウオルフ著『炎と怒り』(早川書房刊)
読書ノート:孫崎享著『戦後史の正体』(創元社刊)
日本の戦後史の正体は米国政府が日本を事実上支配し続けてきたという事実に尽きるというのが本書の主張だ。
1951年の日米講和条約によって日本は連合国軍の占領に終止符を打って独立したかのように思われる。
しかし実は日米講和の裏側で米国が目指したのは次のことだった。
「米国は日本から我々が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留する権利を確保する」。
この原則は51年から現在に到るまで見事に完徹されている。
その典型的な事例が2009年に成立した民主党政権で鳩山由紀夫首相が「沖縄普天間基地を国外、少なくとも県外に移転させる」という方針を示した時だ。
「この主張は、米軍関係者とその日本協力者から見れば、半世紀以上続いてきた基本路線への根本的な挑戦でした。そこで鳩山首相を潰すための大きな動きが生まれ、その工作は見事に成功したのです」。
米軍基地の設置と基地運用に関わる治外法権的な米国の権利を制限する試みは米国の虎の尾なのだ。
そしてもう一つの米国の虎の尾は「日中友好関係をアメリカを外して促進する」ことに他ならない。
この虎の尾を踏んだのが田中角栄首相だった。
田中首相はニクソン大統領の日本の頭越しの電撃的な訪中の後で中国を訪問し、議会の反対にあって友好条約の締結が遅れていた米国より先に日中友好条約を締結したのだ。
このことがニクソン大統領並びに大統領補佐官であったキッシンジャーを激怒させた。
キッシンジャーはこの時次のように怒りを吐露している。
「汚い裏切り者どもの中で、よりによって日本人野郎がケーキを横取りした」。
この結果田中角栄はロッキード事件の罠にはめられ政治生命を失って悲痛のうちに亡くなった。
このようにアメリカの政治的な意図に対抗して自主的な判断に基づいて政権運営を図ろうとした日本人首相は、常にアメリカの工作によって短命に終わったり、政治生命を失う目にあってきたということだ。
このようにアメリカが自主路線を追求する日本人首相を追い落とす方法は、著者によって次のように整理されている。
-
占領軍の指示によって公職追放する 鳩山一郎、石橋湛山
-
検察が起訴し、マスコミが大々的に報道し政治生命を断つ 芦田均、田中角栄、小沢一郎
-
政権内の重要人物を切ることを求め、結果的に内閣を崩壊させる 片山晢、細川護煕
-
米国が支持していないことを強調し、党内の反対勢力の勢いを強める 鳩山由紀夫、福田康夫
-
選挙で敗北 宮澤喜一
-
大衆を動員し、政権を崩壊させる 岸信介 」
岸信介が対米自主路線であったと評価されていることには驚くかもしれない。
このことの理解のためには日米講和条約締結時に結ばれた安保条約について理解をすることが求められる。
安保条約第1条には次の規定があります。
「アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその付近に配置する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国はこれを受諾する。
この軍隊は、極東における國際の平和と安全に寄与し、並びに、一または二以上の国による教唆または干渉によって引き起こされた日本国における大規模な内乱及び騒擾を鎮圧するため、日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するため使用することができる」。
「使用することができる」というのは法律上は義務ではないことを意味する。
つまり日本に配置するアメリカ軍は日本を防衛する義務はないということだ。
さらに安保条約際3条には次のような規定がある。
「アメリカ合衆国の軍隊の、日本国内及びその付近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する」
実はこの行政協定によって「米国は日本から我々が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留する権利を確保する」ことが可能になっている。
そればかりか基地に所属する軍人、軍属並びにその家族が日本国内で日本国の法律に触れてもその裁判権はアメリカ合衆国に帰属するということで実質的な治外法権を認めているのだ。
こうした日米安保条約とそれに付随する行政協定の不平等性を取り除くことを意図したのが岸信介であった。
彼は安保条約を改定しその後で行政協定を改定する二段階での工程を企図した。アメリカ政府は岸の望んだ不平等性の除去の方針を歓迎せず、この米国政府の意図を汲んだ池田隼人ら自民党首脳部が岸の政治生命を絶つべく財界と結託して岸内閣の打倒を謀ったということだ。
このように見てくれば戦後の政治史はまさにアメリカ政府つまりはアメリカ合衆国の要望に応じる政治が連綿として続いてきた。アメリカ政府の意図に対抗して独自路線を打ち出した首相並びに権力者は様々な手練手管で政治生命を絶たれたり、非業の死を迎えたりしたということだ。
読書ノート:村上世彰著『生涯投資家』(文芸春秋社刊)
村上氏は日本におけるアクティビスト(もの言う株主)の草分けだ。
次の条件を抱え込む企業が村上氏の格好の標的だ。
・無借金
・現金等価物(現預金ならびに有価証券)>株式時価総額
・BPRが1を下回る
つまり安定的な利益を稼ぎながら、その利益を企業内部に溜め込んで株主に還元していない企業だ。
村上氏はこうしたキャッシュリッチな企業に投資する。そしてまず経営者に対して成長戦略を問いかける。これに対して満足な回答が得られなければ、配当の増額や自社株買いを要求する。
こうして配当を稼ぎ、さらには株価が上昇したところを見計らって売り抜ける。
このような手法で投資家から巨額の資金を任されるようになって、その潤沢な資金を背景にTOBやMBOという手練手管を使って経営者に対して大いなるストレスをかけることもいとわない。
村上氏はこうした投資行動の前提にある「崇高な」ミッションがあるのだと説く。
「日本にはお金がある。日本政府は5百兆円を軽く超える金融資産を保持している。海外純資産残高も3百兆円を超えていて、永年世界1位だ。家計の金融資産も、1千7百兆円以上あると言われている。それなのに世界一の借金大国となっている。なぜなのか。わたしの答えは簡単だ。『お金が循環していないから』という理由に尽きる。
資金の循環を促すきっかけとなるのは、まずは企業がコーポレート・ガバナンス・コードに則り、投資や株主還元を行って手元資金を放出しながら、余分な手元資金や銀行からの借り入れで賄った資金を、昇給や新規雇用に積極的に回すことだ。その結果新しい仕事が生まれたり、リターンを受けた投資家が次の投資先を探したり、昇給や仕事を新たに得た人々がお金を使うようになる。こうして景気が動き始めて市場が活性化してくると、個人も銀行に預金するだけでなく、株式投資を行ったり、不動産へ投資したり、という新たな動きが生まれる。その動きの一つひとつから、新たな税収が生まれる」。
つまり企業が手元資金を株価の上昇に向けて流出させることで国民経済的な資金循環の流れが生まれ、それがさらなる勢いを付けて日本経済が活性化するという構図だ。
しかし残念なことに村上氏の手法は株主だけの利益に資するだけであって、国民経済的な資金循環を生み出す駆動力にはなり得ない。
つまり村上氏のミッションは株主だけあからさまな利益追求を糊塗するためのいいわけにしかすぎない。
企業は株主だけでなく顧客、従業員、取引先、地域社会などの多くのステークホルダーによって支えられて活動が展開できている。
これらのステークホルダーのすべての満足が同時に得られることがなければ継続的な成長はありえない。とすれば過剰に溜め込まれた利益があるとするならば、それはすべてのステークホルダーに均等に配分されなければならない。
昨今のコーポレート・ガバナンス・コードに見られる企業に対する株主優先の動きはこの意味において警戒しなければならないことと受け止めるべきだ。
読書ノート:村上世彰著『生涯投資家』(文芸春秋社刊)
読書ノート:ジェイク・ナップ著『SPRINT 最速仕事術』(ダイヤモンド社刊)
グーグルで開発された高速問題解決メソッドがSPRINTだ。
通常多くの人材を何か月も投下し、巨額のコストをかけて実現している課題解決や製品・サービス開発をなんと7人の専門家だけで5日間で実現してしまう驚異のメソッドだ。
Sprintはつぎのような状況で役に立つという。
・リスクが高いとき
・時間が足りないとき
・何から手を付けていいかわからないとき
まさに絶体絶命の状況で役に立つということではないか。
本書はこのSPRINTのノウハウを懇切丁寧に開示してくれている。
思わず、「こんなにすべてのノウハウをタダ同然で提供してくれていいの」と随分と得した気分にさせてくれるほどだ。
SPRINTの手順は簡単だ。月曜日からはじめて金曜日には大きな成果を手にしている。
その手順は次のとおりだ。
準備 適切な課題とチームを選ぶ。SPRINTのための時間と空間を用意する。
月曜日 問題を洗い出し、どの重要部分に照準を合わせるかを決める
火曜日 多くのソリューションを紙にスケッチする
水曜日 最高のソリューションを選び、アイデアを検証可能な仮説の形に変える
木曜日 リアルなプロトタイプを完成させる
金曜日 プロトタイプを生身の人間に試してもらう
これだけ見るとあたりまえの手順であって、「これのどこが画期的?」と思ってしまう。
実はこの月並みな手順を実行するに際してのルールが画期的なのだ。このルールがあるから超高速で問題解決が可能になるのだ。
そのルールとは次のとおりだ。
-
課題解決の目標を定義する。「新規顧客によいコーヒーをオンラインで届けること」
-
目標実現の前提条件や障害を定義する。定義にあたっては疑問文の形式で表現する。「顧客はうちの専門知識を信頼してくれるだろうか?」
-
チームに「決定者」を参加させる。意思決定者だ。彼がメンバーの一員でないと、チームがせっかく創造したソリューションも、きまって後で意思決定者からのちゃぶ台返しを食らって日の目を見ないことになる。
-
チームメンバーから「進行役(ファシリテーター)」を選任する。
-
一日6時間集中して作業する。普通は10時から17時まで。昼食休憩を1時間とる。メンバーはこの6時間缶詰めになる。
-
デバイス(PC、スマホなど)を持ち込まない。ホワイトボードとふせんと紙で作業する。
-
全員での議論を避けて個々人が作業に集中する。作業結果を持ち寄って全員で疑似投票を行ってベストを選定する。ブレーンストーミングは時間効率がきわめて悪い。
-
決定は民主主義によらない。ベストソリューションの選択にあたって各人が投票はするが、最終決定は「決定者」が行う。
-
ベストソリューションに従ってプロトタイプをつくる。プロトタイプはどんな場合にも制作可能だ。
-
プロトタイプを選ばれた5人の顧客にテストしてもらい、仮説を検証する。
ブレストはしない。民主主義はしない。たぶんこれがSPRINTの真髄なのだ。
そんなばかな!
でもあたかも全員参加で文殊の知恵が湧きだすように思われているけれど、ブレストも民主主義も時間ばかりかかってその割にたいした成果にはつながらない。そんな経験をいやと言うほどしてきたのではないだろうか。
個々人が一人で集中して考え抜いて、それを全員で評価するほうがどれだけ効率的でしかも高品質の作業につながるかわからない。
多数決で決めても意思決定者が腑に落ちない選択は最終的には良い成果にはつながらないこともいやというほど経験してきたではないか。
だから、超高速で最大の成果をもたらすためには、ブレストも民主主義も捨てなければならないのだ。
こうしてみるとSPRINTは特別な重要プロジェクト向けのメソッドだKでなく、日常的な会議などにおいてもきわめて有効なメソッドになるはずだ。
このような意味においてもSPRINTは労働生産性の飛躍的高度化に向けての切り札になるに違いない。まさに「働き方改革」のメソッドになるということだ。
デフレの真因は経済のグローバル化だ
トランプ大統領の目指す保護主義政策に対する批判が飛び交っている。その典型的な批判を信州大学の真壁教授の主張に見ることができる。
「トランプ保護主義の矛盾に対応しなければ日本は孤立する」(ダイヤモンドオンライン2017.01.31)
「しかし、世界経済の運営は企業経営とは異なる。自動車を生産する場合、労働コストの高い米国よりも、メキシコで生産した方がコストは抑えられる。これが比較優位性の概念だ。低コストで、効率的にモノを作る国から産品を輸入することは、自国の消費者にとって十分なメリットがある。中国から輸入しているアップルのスマートフォンはその典型例だ。
米国内外から最も高性能、かつ、安価な部品を集め、それを相対的に労働コストの低い中国の企業(ホンハイ傘下のフォックスコン)で組み立てる。そして、完成品を米国、その他の国に輸出する。そうして、米国の消費者は国内で生産するよりも低いコストで最新のスマートフォンを手にすることができる。同時に、新興国にも雇用機会の創出などのプラス効果がある。これがグローバル経済のもたらした恩恵だ」。
企業は比較優位性の原理に則ってもっともコストの低い国に進出して製品を製造することで世界中の企業も消費者も低価格で財を調達することが可能になる。リカード以来のいわゆる「比較生産費原理」だ。この原理に基づいて貿易と資本の自由化を世界中で推進することがきわめて合理的な選択になるというのがグローバリズムの主張だ。
しかしこの主張はいくつかの大事な「不都合な真実」を見落としている。
-
グローバル企業は投資先の国や地域の労働者の賃金や労働条件さらには社会保障の水準を自国(先進国)並みの水準に引き上げることはありえない。自国と投資先との賃金や社会保障にかかわるコストの格差が利潤の源泉であるからだ。
-
グローバル企業は投資先の国や地域の製造プロセスについて自国並みの自然環境保護のための備えをすることはありえない。自国と投資先との環境保護に関わるコストの格差が利潤の源泉であるからだ。
-
グローバル企業はもっとも利潤率の高い国や地域へと進出し、そこで経済活動を展開することで巨額の利潤を蓄積する、しかしその利潤はほとんどがグローバル企業の出身国に回収されるか、最悪の場合は課税回避を目的として他国へと移転されてしまう。従って利潤は投資先の国や地域に還元されたり、再投資されて投資先の国や地域を潤すことにはつながらない。
-
投資先の労働者の低賃金や劣悪な環境対応によって実現したグローバル企業の製品がグローバル企業の出身国の消費者の手に渡ることは、結果として先進国の労働者の賃金水準を押し下げる。
このような不都合の真実はグローバル企業に巨額の利潤を創出させるその裏で投資先の国や地域の労働者ばかりか自国の労働者の生活水準の向上を押しとどめ、投資先の国や地域の環境を劣悪な状態のままに放置する。つまりグローバル化は世界中で貧富の格差を拡大し、それを継続させることになるわけだ。
このような事実から先進国を襲う長期にわたるデフレ経済の真因は経済のグローバル化にあったと考えることができる。とすればデフレ対策に金融緩和や財政支出を打ち出すことはまったくもって的外れと言わざるを得ない。
むしろ金融緩和や財政支出はグローバル企業の資金調達を無限の規模に拡張し、資本の海外投資を加速化させることで経済のグローバル化を加速させ、したがってデフレ経済の深化を促進させることになる。先進国の世界的な金融緩和競争がデフレの推進力であったということだ。つまりアベノミクスも火に油を注ぐという本末転倒の政策に血道をあげているということになる。
ところでこうした状況からの脱却に向けてトランプ流の政策はどの程度の有効性をもつのだろうか。トランプ大統領はさしあたって次の政策を掲げている。
-
海外に蓄積されているアメリカのグローバル企業の資金を米国に還流させる。
-
海外に移転したグローバル企業の製造拠点を米国に還流させる。
-
NAFTAやTPPなどによる関税撤廃の地域経済圏から脱退する。
-
米国の製造業を脅かし、米国の労働者の職を奪う海外製品に高関税を課す。
単純化していえば、
-
米国の製品やサービスの地産地消を推進する。
-
グローバル企業の海外での稼ぎはすべて米国に還流する。
ということになる。
ここで問題は米国さえよければ多国はどうなっても構わないという米国第一主義だ。トランプはグローバル企業が海外で投資先の国や地域の労働者がどんな悲惨な労働条件におかれようと、また投資先の国や地域の自然環境がどんなに破壊されようとまったくお構いなしという発想に立っている。
このような自国第一、自国優先の考え方では労働者の仕事を増やしたり、デフレ経済からの脱出を実現することは叶わない。
デフレから脱却し、経済の拡張を実現するには労働者の賃金や労働条件や社会保障の水準を高度化し、同時に自然環境の保護を推進して労働者の生活環境を改善し続けることしか突破口はありえない。なぜなら有効需要は消費支出に多くを支えられているということ、そしてその消費支出は最終的に労働者の生活水準の高度化によってのみ拡大するからだ。
この前提に立てばグローバル企業は海外の投資先で労働者の賃金、労働条件、社会保障を自国と同等の水準に設定し、自然環境保護の施策も自国と同等の水準のもとで企業活動を推進するということが求められるのだ。
こうした前提に立つ世界では経済のグローバル化の推進力である「比較生産費の原理」が効かなくなる。かくしてグローバル企業の海外進出のインセンティブは海外市場の獲得という一点だけになる。つまり「比較市場規模の原理」(筆者の造語)が誘因になるということだ。
この原理に立脚することになると企業の行動原理はイノベーションによる新価値創造に向かうことになる。多くの企業が競争優位に向かって価値創造に切磋琢磨することになれば多様な形で市場創造、需要創造が旺盛に実現されることになる。
こうして世界は真の意味でグローバル化して、これまでとは全く違った次元で豊かになっていく道が拓けるということだ。
企業はすべてのステークホルダーに配慮しなければならない時代が来ている
ハーバード大学教授のマイケル・ポーター氏が日経ビジネスの記者のインタビューに答え、トランプ大統領に対しての高評価と期待を語っている。
「マイケル・ポーター教授が語るサステナブル経営」(日経ビジネスオンライン)
ポーター教授はトランプ大統領の登場を二つの意味で歓迎している。
一つはトランプ大統領が経済の成長を目標に置いているという点だ。大統領選で敗れたクリントン氏は成長よりも再配分に重点を置いていた。
二つ目にはトランプ大統領が社会的な課題の解決を提案しているということだ。これまでの20年間政治は雇用の拡大が進まないというような、平均的な市民が経済成長の恩恵を受けていないという社会問題を何一つ解決することはできなかった。
CSVの重要性
記者はポーター教授に次の問いかけを行っている。
「ポーター教授は、企業がCSV(Creating Shared Value=共通価値の創造)に取り組むことの重要性を提唱しています。昨年発表した米国経済に関する論文では、米国の問題は繁栄の恩恵を社会と共有できていないことだと指摘しています。ブレグジットやトランプ大統領誕生の背景を考えると、企業はこれまで以上に社会との『共通価値の創造』を重視する必要性に迫られるのではないでしょうか」。
ポーター教授は次のように答えている。
「まさにその通りです。既に多くの企業は、利益の一部を寄付したり、単にCSR(企業の社会的責任)活動に取り組んだりという状況から、CSVへと移行してきました。つまり、事業そのものを通じて、社会によりよい影響を及ぼそうという方向に動いています。ブレグジットやトランプ大統領の誕生によって、企業は社会課題の解決に、より積極的に取り組む必要性を認識するでしょう。その意味で、現在の状況は共通価値の創造を企業の経営戦略に組み込む流れを、これまで以上に加速するはずです。
CSVというのは、博愛の精神を指す考え方ではありません。企業が競争上、ライバルとは異なる方法で優位に立つための戦略です。まさに、そのムーブメントが今、本当に加速し始めています。
社会に与える影響について配慮せよという、企業に対する市民の要求は、急速に強まっています。そのため、すべてのステークホルダーに対して配慮しなければならないと考える企業は、ますます増えています。
エネルギー効率を改善し、健康に寄与する商品を作り、従業員が会社の中で成長できる機会を提供することなどは、そもそも、企業が持続的に成長し、より成功を収めるために不可欠なことだと理解されてきました。
共通価値の創造というコンセプトは、資本主義が持つ究極の力を引き出すものです。企業が得た利益を社会に再分配するという発想ではなく、社会課題を解決し、社会のニーズに応えること自体が、企業を競争上、より優位にする。そうしたコンセプトを企業戦略に組み込むことが、資本主義の真の力を引き出すことにつながるのです。
そのことを、世界をリードするグローバルカンパニーの多くが理解している。スイスのネスレなどは、その典型でしょう。米国のウォルマート・ストアーズでさえ、最近は大きく変わりました」。
企業が全てのステークホルダーに対して配慮しなければ企業活動を継続的に実現できない状況がすでに出現しているということなのだ。
これこそまさに資本主義を社会的および公共的観点から改造して、資本主義が引き起こし、その究極のすがたであるグローバリゼーションの果てに生み出した極端な貧富の差や中産階級の没落や南北問題、さらには地球環境の持続性の危機などの諸矛盾を乗り越えようとする修正資本主義の立場だ。
メキシコ工場建設はCVSに適うか
このような観点で現在トランプ大統領がフォードやトヨタを名差しで非難した米国企業のメキシコでの工場建設の問題を考えて見よう。
企業は製造工場を米国につくるか、メキシコにつくるかの意思決定を迫られたときに、その判断基準としてどちらの立地が自社にとって利益を最大化するかという視点を用いるはずだ。
この利益至上主義が結果として米国の生産拠点の減少と雇用の減少を結果したわけだ。しかしその裏で米国民は米国産の製品と同等の品質のメキシコ産の製品を従来の米国産の製品より安価に購入することが可能になる。
そればかりか翻ってメキシコに目を移せば工場誘致によって雇用が生まれ、同時に工場を支えるパートナー企業の増産効果でここでも雇用が相乗効果的に生まれ、結果として賃金の上昇も期待できることになる。米国で仕事を奪われる市民以外のステークホルダーが満足することになるように思われる。
メキシコ工場建設はメキシコの社会問題を解決しない
しかし良く考えると重大な問題が取り残される。メキシコから米国へ輸出される製品価格は労働者の所得水準の米国労働者との格差を是正することはないし、また工場が生み出す環境破壊の解決をもたらすこともない。ましてや地域のインフラ整備などに寄与する水準でもない。
極端に言えばメキシコの市民や地域の抱える社会問題を是正することには貢献することはないということだ。つまりメキシコ進出は米国の労働者の雇用を奪うばかりかメキシコ社会やメキシコ市民というステークホルダーにとっても決してプラスに働くことにはならないというわけだ。
メキシコ社会というステークホルダーに配慮するということ
メキシコの労働者に米国の労働者と同等の賃金、福利厚生を保証し、地域社会に対して米国と同等の法人税を支払い、米国土同様の基準での環境規制に従うことを前提にメキシコ工場の建設を行うことではじめてメキシコのステークホルダーに配慮することになるわけだ。
つまりグローバル化時代にすべてのステークホルダーに配慮するということは、自国のステークホルダーにのみ限定するのではなく関係するグローバルなステークホルダーすべてに配慮するということに他ならない。
この原則は「フェアトレード」の主張を取り入れて企業活動を実行することにつながる。グローバル化の果てに資本主義が行き詰まりの罠に陥らないためにはそこまでの奥行きを持ってCVSを語らなければならない時代に来ているという認識が問われているのだ。
「女子力」ってなんだ?
「日経ビジネスオンライン」に掲載されている河合薫さんの「無責任な『女子力』願望が強要する女性の社畜化」が面白い。サブタイトルは「女性特有の視点、気遣い…そんなもんないワ!」
アベノミクスとやらの打ち手の一つに女性活躍がある。この方針に踊らされて、大企業の経営者が女性管理職比率の高度化を競い合って悪あがきをしている。
だいたい「女性管理職比率を30%にせよ」と政府が指示しこれに唯々諾々従う風潮はまさに全体主義に他ならない。中国共産党の一党独裁体制に負けず劣らないほどにひどいもんだと考えるべきなのだ。
全ての企業は継続的に事業を展開するうえで必要なことなら当たり前に実行するしかない。女性の雇用も活躍も必要に迫られて、積極的に実行するほうが良いと考えるから行うのであって、お上から命令されてやるようなものではない。
現に慢性的に人手不足に悩む中小企業は女性の力を借りなければ存続は不可能なのだ。そこでは女性を特別扱いはしないし、あるがままに戦力化しているだけだ。
「女性の働き方改革」はまさに「女性の悪しき働かせ方改革」にほかならない。女性は男性とは異なる「女子力」なるものをもっていて、それを縦横に発揮していただくことが必要なのだ、などという見当はずれの働き方をめざしているからだ。
河合さんによれば女性を働かせるために、女性にとって不自然とも、迷惑千万とも思える期待が寄せられ、これに辟易して働く意欲さえ失う女性が増えているというのだ。
「とにかく彼女たちはみなさんが想像する以上に、
•女性=結婚、出産
•女性=女子力
•女性の活躍=管理職
•女性の働きやすい職場=育休・時短勤務の充実
•女性=休日はプライベートを充実させるetc、etc……といったキーワードで女性を語るテクストに辟易している」。
『働く女性はこうに違いない』という見方が強くなってきていることに憤り、戸惑い、疲弊しているのだ」。
女性管理職比率の目標達成のために経験もトレーニングも不十分な女性を管理職に登用する女性にだけの昇任バブルが蔓延し、しかも管理職は成果主義でチャレンジングな目標を求められ、部下も含めて疲弊している状況が目に浮かぶ。
河合さんは女性の活躍を無理なく実現するにはそれなりの準備がなされなければならないという。「仕事の再設計」というトレーニングプログラム」がそれだ。
「『仕事の再設計』というトレーニングプログラムはチーム、個人、管理職、経営トップが一丸となって次の3段階を実行することにより、従業員のワークライフバランスを実現する。
(1)仕事と理想的な従業員像についての既存の価値観・規範を見直す。
(2)習慣的な仕事のやり方を見直す。
(3)仕事の効率と効果を向上させ、同時に仕事と私生活の共存をサポートするための変革を行う。
プログラムを完成させるには、従業員からの要望と企業からの要望を一つひとつ丁寧に組み合わせる作業が重要になる。実に手間のかかる作業だ。その作業はまるで『ジグソーパズルを行うのと同様である』と言われるほど、頭と労力を使う。
もし、本気で『女性の働きやすい職場』を目指すなら、仕事の再設計をやらなきゃダメ。今のように『ムード』や『福祉』でやっていたのでは、ウィンウィンならぬ、フヒ~フヒ~。女性たちは疲弊し、不満を蔓延させるばかりか、企業もいずれヘタっていく」。
河合さんの提案する「仕事の再設計」は女性の活躍のためというより、性別に関係なく生活と仕事の関係のあるべき姿を再発見してそれを全員で目指そうということから始まるようだ。
しかし河合さんの言うように再設計のために多くの労力と知恵を出さなければいけないとしたら、並みの企業では実現するのは困難だ、
再設計はそれほど難しく考えることはないのだと思う。すべての仕事を棚卸して、価値ある仕事だけを選択し、それ以外を排除することから始めればいいだけなのだ。
そしてもっとも排除しなければならないことは、管理職や経営者が思いつきで部下に仕事を与える悪しき習慣なのだ。
イタリアの解雇規制緩和は日本にとってのベストプラクティスたりえるか?
安西法律事務所の弁護士倉重氏のレポートによると昨年イタリアで労働法が改定され、これまでの解雇規制を緩和し、不当労働行為などの差別的解雇でないかぎり、解雇の金銭解決が認められることになったという。http://toyokeizai.net/articles/-/153024
イタリアでは勤続年数が1年単位に2ヶ月分の解雇手当を払えば解雇が原則自由に行える。ただし手当の上限は24ヶ月(勤続12年を超えても解決金は増加しない)とされている。
解雇規制の緩和はイタリアでは次のような目的を掲げて実施された。
-
厳しい解雇規制の下では解雇に伴うコストの見通しが立たなかったり、見通しが立ったとしてもその見積が多額に上るため、起業や海外からの資本投下が行われにくかった。規制緩和によってこの問題が解消され起業が容易になり、海外からの新規投資も活発になり、これに伴う雇用の拡大が期待される。
-
中小企業にとっては解雇に伴う解決金が業績を圧迫し倒産に追い込まれるケースが多くみられた。この問題も解雇に伴う解決金がリーズナブルになることで中小企業による雇用の拡大が活発になることが期待される。
-
技術革新のスピードが速く、求められるスキルの変化も急速である。要請されるスキル変化にふさわしい人材の入れ替えが解雇規制によって実行できずに事業の陳腐化が進行することに有効な手を打てなかった。いわゆる雇用のミスマッチ。解雇規制の緩和で変化する必要スキルを持つ人材に対する雇用が積極的に行われることになる。
解雇規制の緩和に上記のようなメリットが認められたとしても、個々の労働者にとっては解雇の自由化は雇用の不安定化を意味し、労働者の不安を増大することに他ならない。こうした不安を取り除くために、イタリアでの規制緩和は、解雇された労働者の保護を強化し、不安を払しょくするために次のような施策が解雇規制の緩和と同時に行われることになった。
-
ハローワークの機能を充実して解雇された労働者の求職活動を強力に支援する。
-
失業手当を厚くする。
-
労働監督機能を強化拡充して不当労働行為による解雇を未然に防ぐ。
-
法人税、社会保障費の面で、雇用維持、雇用拡大企業に対するインセンティブを付与する。
以上のような対応策を用意したところで、若年層の失業率が40%にも達するイタリアで解雇規制の緩和を実施すれば、失業率がさらに増大してしまうリスクはきわめて大きいと思われる。
イタリアの場合企業の倒産、とりわけ中小企業の倒産が増大したり、起業が活発に行われなったり、外資の新規投資が伸び悩んだりする原因を解雇規制に求めた。従って企業活動を活性化し、経済成長を持続的に求めるために解雇規制を大幅に緩和して、労働力の流動化を実施するに至った。
しかし日本の場合解雇規制は本当に企業活動の足かせとなっているのだろうか。企業はリストラと称して業績が思わしくなった場合に従業員の整理を実施することは日常茶飯事に行われている。
とはいえリストラは最後の最後に取られる手段として行われるのであって、そこに至ることなしに危機を乗り越えるためのあらゆる手立てを実施した上で、最終的にやむを得ずというかたちで取られる手段だ。したがってリストラを実行する経営者は従業員に対しても社会に対してもうしろめたい気持ちを持たざるを得ないし、またそうであるがゆえにリストラ後の経営立て直しに必死に取り組む努力義務を自覚するのだ。
解雇規制が緩和されれば経営者はそれこそ自由に、リストラにまつわるやましさなど毛ほども感ずることなしに従業員を解雇することができてしまう。まさに経営者はモラルハザードにおちいることになるのだ。安易な解雇は経営者から従業員の雇用を護るという自覚を無くして、安易でお手軽な経営を助長することになる。
解雇規制は経営者に安易な経営をさせえないために自らを律するための箍(たが)でもあるわけで、この箍があるおかげで日本的な経営は世界から賞賛される輝きを持ちえたのではなかったか。
「スマートテロワール」宣言
「スマートテロワール協会」が24日に発足予定です。
弊社代表の中田康雄は当協会の理事に就任予定です。
本日11月22日の日経新聞朝刊に意見広告を掲載しましたのでそれをここに再掲いたします。
お目通しいただければ幸いです。
TPPが頓挫して、先ずは一安心 だが油断できないトランプの2国間交渉
いまこそ、「スマートテロワール」で砦を築いて日本の食料自給力を拡充しよう!
TPPには日本の農業を衰退に導く罠が仕掛けられていた
畜肉について関税率を段階的に削減し16年目に牛肉は関税率9%(現状38.5%)、10年後の豚肉の関税1kgあたり50円(現状482円)。
この畜肉に関する約定は、他のどの約定にもまして危険です。畜肉の「自由化」は『国のかたち』に係る大問題だからです。
現在日本人のカロリー摂取量は、稲からは25%程度、畑作穀物(小麦・大豆・トウモロコシなど)からは55%で、圧倒的に畑作穀物が必要とされています。しかし残念なことに畑作穀物(畜肉や油脂に形を変えているものを含む)は米国をはじめ海外からの輸入に依存していますので畑作穀物の国内生産量を拡大し、自給率を上げることが日本農業再生にとって急務です。
この畑作穀物生産量の拡大にとって欠かすことのできないのが畜産業から提供される「堆肥」です。
しかし畜肉の関税が下がると畜肉が海外から大量に押し寄せ、国内の家畜の肥育頭数が減少し、畜産業が衰退することになります。影響はそれだけにとどまりません。畑作穀物が増産の推進力である堆肥を失って、日本農業再生の道が閉ざされることになります。このように畜産業の衰退は我が国の将来に大きな禍根を残すことになるのです。
トランプ次期大統領はTPPから脱退しても、農産品の関税引き下げを迫る
米国による日本の農業干渉の歴史は終戦直後の「農地開放」に始まり、防共政策と食料支援政策をセットにして米国の庇護を受ける1954年のMSA協定につながります。この軍事外交と食料をワンセットで米国に依存する政策は1960年安保改定とそれに伴う「農業基本法」で決定的になります。
「農業基本法」の主題は、穀物は米に集中し他の穀物は米国などからの輸入に依存する「選択と集中」の方針でした。いわゆる「加工貿易立国論」です。十勝地方には有数の畑作地であるのに稲作奨励策を説きに来た農林省の役人を「米はやらない!」と言って追い返した有名なエピソードが残っています。
当時わが国で耕地は600万ha、栽培は800万haで食料自給率73%でした。二毛作と裏作をしていた地域があっての数字です。それが現在耕地450万ha、しかも100万haは休耕田というありさまです。自給率は39%にまで低下しカロリー換算量で米国から輸入する食料と変わらないまでになりました。
孤立主義の意思を強めているトランプ次期大統領がそのことを知れば、やはり軍事外交と食料安保を天秤にかけてこれまで以上に自国農畜産品の輸出拡大に向けて厳しい圧力をかけてくるのではないでしょうか。
TPPがお蔵入りすることで安心はできません。むしろTPP以上の脅威が日本の農業を襲うことに備えなければなりません。
日本は本気になって食料自給力を拡充しなければならない
世界を席巻したグローバリゼーションの潮流は大きく潮目を変えて、保護主義へと逆流するかのように見えます。しかしグローバリゼーションの対極は保護主義ではありません。反グローバル化の潮流は「国際分業の流れ」に代わって国内で活用されていない未利用資源に光を当てる「サスティナビリティ」(持続可能性)の活動として再認識すべきです。
我が国の未利用資源に100万ヘクタールを超える休耕田や40万haを超える耕作放棄地があります。これを畑地や放牧地に転換すれば小麦や大豆やトウモロコシなどの畑作穀物さらには畜肉の自給率が一挙に向上します。
また穀物は食品加工場を必要とします。農村に食品工場が立地(農工連携)すると日本人口の1/2が住んでいる農村部で雇用機会が拡大し、所得は大幅に伸長し、元気になります。
また食品工場は女性の活躍する職場となり女性が農村部にUターンする流れを作りだし、少子化にも歯止めがかかることも期待できそうです。
今こそ田畑転換によって畑作穀物の生産を拡大し食料自給力を揺るぎないものにする最後の機会なのです。
食料自給率拡充への道は堆肥の活用が拓きます
欧州では、1000年以上前に「三圃式農法」として畜産と畑作の循環型農業が標準になりました。その頃日本では畜肉食を禁じられていたために堆肥の活用は畜産業が勃興した明治時代をまたなければなりませんでした。
堆肥は微生物の活動を促し有機物成分を分解、活性化し健全な土壌をつくります。穀物の輪作体系も土壌を元気にします。これらの相乗効果で収穫量も30年あれば2倍にできます。収穫量が2倍になることは耕地が倍増することに等しい効果を生みだします。その反収増が自給率70%を可能にします。
農薬と化学肥料と行政の施策によって損なわれた国力の源である「大地」を再興する途が堆肥の活用によって大きく拓けてくるのです。
反収量の増加で、悩み多い市場経済を卒業することができます
「契約栽培」が食品加工場と農家との間の取引形態(農工連携)を牽引します。
「契約栽培」(農工連携)は市場相場や為替レートに影響されない安定した価格と究極の品質を追い続ける好循環を生みだします。
「契約栽培」は生産過剰の心配をなくします。農産物の過剰は飼料として畜産業が引き受けるからです。つまり家畜は過剰な食料の貯蔵庫でもあるということです。また飼料の過不足の調整は輸入飼料が引き受けることになります。こうして豊作貧乏はなくなります。
耕畜連携と農工連携が両輪となって「テロワール」(独自の気候風土を共有する地域自給圏)を産み出します。
地域内の農家と食品加工場、さらには外食店、小売業の努力を地域内の住民が誇りにし支援するという形で各プレイヤーの連携が深化し、進化していきます。
これが自給圏「スマートテロワール」の目指す姿です。日本の豊かさはここから実現していくはずです。そして日本の食料自給力拡充の活動もこの「スマートテロワール」を砦に力強い歩みを始めることになるはずです。
永守流働き方改革が日本の働き方問題のほとんどを解決する
日本電産の永守会長兼社長は日本電産での働き方改革が大きな成果を上げていると決算会見で語った。
「『モーレツ』はもうウチにはない」。永守社長は働き方改革の説明に多くの時間を割いたのだ。労働時間を減らして収益力を底上げするという。
代表例が残業削減。1年前から定時退社を推進し、朝礼時に上司に申告して許可を得ないと残業ができないようにした。ムダな仕事が理由の残業は認められない。業務の生産性を落とさずに残業を3割減らした。研究開発部門の若手男性社員は「仕事が残っていても定時を過ぎると『早く帰れ』と言われる。どう仕事の効率を上げるか必死で考えるようになった」。
「16年度からは会議時間も短縮。会議用資料の分量も減らすように号令をかけた。すると資料作りのための残業は減った。
残業削減による4~9月期のコスト削減効果は約10億円。この一部は成果に応じて社員に一時金や教育などで再配分する予定だ。『定時退社して語学を学んでもらった方がはるかに競争力が高まる』。こう語る永守社長は『20年までに残業ゼロを目指す』という」。(日経新聞2016.10.25付朝刊)
残業ゼロを目指して何が起きたのか。
-
仕事上のムリ、ムラ、ムダの削減が行われた。労働生産性の大きな改善が見られたということだ。「上司の指示はほとんどが思いつきだ」と言われるように、個々の作業や会議について「どんな目的のためにそれを行うか?」を改めて問い直すことが残業セロという制約を設けることで始まるのだ。
-
定時に帰社することで従業員は自己啓発や趣味を楽しむこと、さらには家族との団らんに時間を積極的に使うことが可能になった。つまり生活の質や従業員のスキルアップを通して従業員の労働の質が向上するということだ。
結果として大きなコスト削減効果が得られた。良いことづくめだからすべての企業でこれが実現できるとは限らない。永守氏のようなカリスマ的な経営者が号令をかけなければ様々な言い訳が噴出して実行に移せないことは目に見えている。
一番大きな抵抗は残業代が生活給の一部に組み入れられているという従業員側の実態だ。日本電産でも6ヶ月で10億円多分年間では弾みがついて30億円ほどのコスト削減を達成してしまうだろう。しかしその裏には30億円の給与の削減と言う事態が貼り付いているのだ。
この従業員の抵抗感を排除しなければ大きな成果はえられない。従業員の抵抗を乗り越える方策は、日本電産のように残業ゼロの成果を会社がすべて吸収するのではなく、すべてを従業員の報酬として還元することだ。このやり方はすでにSCSKが実行して残業削減で大きな成果を上げている。
永守氏のようなカリスマ経営者がいないところではこのようにすれば残業ゼロを実現しその成果を享受できることになる。従業員参加による仕事の見直しや従業員のスキル・能力拡充による生産性向上は残業代を超える大きなメリットを会社にもたらしてくれるはずだ。つまり残業ゼロの成果を従業員にすべて還元しても、それを上回るコストダウンが実現できるということだ。
アベノミクスの中心に働き方改革が位置づけられて様々な議論が行われているけれど、日本電産の事例を見るまでもなく残業ゼロを実現すれば働き方改革は大きく前進するはずだ。
労働基準法では労働時間は週40時間以内と定められている。残業ゼロの世界を作るにはこの基準を厳格に運用することだけで良い。つまり36協定を廃止すればいいとうことだ。36協定があるために残業時間はある意味で無制限になっているのであるから。
日本電産と同じように2020年までに残業ゼロすなわち36協定廃止を目指してステップバイステップで実現に向かうことが働き方に関わるほとんどの課題を解決していく一番の近道と考えられる。
読書ノート:松井今朝子著『料理通異聞』(幻冬舎刊)
筆者にとっては今年のベスト書籍上位一、二を争うほどの興味津々の物語。
松井さんの本ははじめての経験だが、話の運びは軽快、文章はよどみなく、なにより主人公の造型がとても魅力的。思わず作中に引き込まれ寝る間を失うほどの傑作だ。
江戸時代、田沼意次から松平定信へと世の中が大きく節約、倹約に向かった頃、八百屋から精進料理の道へと進み二代で江戸一番の料理茶屋の高みに登った福田屋こと八百善の二代目八百屋善四郎の物語である。
善四郎は父親からの手ほどきを受け精進料理に精通し、そこにとどまらず海鮮、鳥獣も見事に裁くまでに腕を広げ、江戸市中に名声を揚げ、やがて飛ぶ鳥を落とす勢いにまで上り詰める。
素材と調理法の幅を拡げるために、伊勢や京、更には長崎にまでも足を伸ばし研鑽を積む傍ら、当時の超一流の文化人の知己を得て、料理に文化的な彩りを加えるに至る。
その文化人がまたすごい。
大田南畝(蜀山人) 幕府勘定方役人、狂歌に長けていた。
酒井抱一 老中、大老に任ぜられる格式の姫路藩酒井雅楽頭家の次男として誕生。尾形光琳に私淑して画家として大家をなした。
谷文晁 御三卿の田安家に仕え、松平定信に認められ定信の近習に取り立てられ、幕府の奥絵師としても活躍した。狩野派、北宋画、大和絵、朝鮮画、はては西洋画までもこなし、一家風を建てた。渡辺華山が弟子入りしている。
亀田鵬斎 儒学者にして書家。松平定信の寛政の改革で儒学は朱子学のみとされ、1000人にも上った弟子がことごとく退塾したために赤貧に甘んじて、それでも粋を極めた。門弟に藤田東湖がいる。
こうした文化人のサロンとして福田屋が場を提供していたのだ。
登場する江戸っ子の伝法な語り口がまた話をテンポよく運んで盛り上げる。こんな具合だ。
「できるもんか、できねえもんか、やってみなきゃわからねえじゃねか。やる前からしっぽを巻くなんざ男の風上にもおけないよ」
太田蜀山人の肝入りによるものか、芝神明前の書肆甘泉堂主人和泉屋市兵衛が八百善の料理本を企画し、料理のレシピや盛り付けを内容とする『料理通』が刊行された。
蜀山人と鵬斉が序文を記し、抱一が挿絵を描く豪華な顔ぶれがさらなる人気を博し、全国の趣味人の興味を惹きつけた。
『料理通』は引き続き三巻まで出版された。
まさに文化文政期の成熟した江戸文化とその担い手たちの息遣いが厚みも奥行きもたっぷりの表現で今そこにあるように感じられる素晴らしい一書だ。
習近平主席と李克強首相との権力闘争が経済金融政策で表面化した
日経新聞2016.8.5付朝刊は「中国政府内で金融政策を巡る部門間の溝が表面化した」とする記事を掲載した。
「投資の許認可権限などを握る国家発展改革委員会は3日午前、投資の下支えに関する提言を盛った文書を発表した。金融市場が注目したのは『適切な機に一段の利下げ、預金準備率引き下げを実施する』との一文。発表を受けて中国の株価は上昇した」。
しかし中国人民銀行(中央銀行)は動かず、発展改革委は3日午後、文書をいったん取り下げ、その後、改めて発表した文書からは金融緩和に関する表現を削除した。
こうした異例のドタバタ劇は金融緩和を志向する発展委と人民元の下落を回避しようとする人民銀行の間に経済金融政策の認識に大きな差異があることを物語っている。
こうした政策の違いはすでに5月に表面化していた。
「5月に党機関紙、人民日報に『権威人士』なる人物が登場。中国経済の行方について、V字型回復は不可能、U字型回復はあり得ずL字型をたどると強調して過剰債務や安易な財政政策に警鐘を鳴らして注目を集めた。習近平・国家主席の側近とみられるこの人物は、足元の小康状態は古い手法に頼っており、バブルを生んでリスクを増大させるとも断じた」。
権威人士は習近平国家主席に近い人物との見方が一般的で、金融緩和をテコにして経済のハードランディングを避けようとする李克強首相への、強烈な批判と受け取られている。
つまり経済金融政策の政府内の違いは習近平国家主席と李克強首相との権力闘争が表面化したものと考えられている。
習近平主席は李克強主席の出身母体である共青団の影響力の弱体化を狙って共青団への党中央による統制を強化しつつあり、李克強派に対する攻勢はじわじわと実を挙げていると考えられる。
日経新聞がついに円高政策推奨に転換か?
ついに日経新聞も本音を語り始めた。円安ではなく円高が本当は望むべきことだということを。
「この円レート下落により、円で計った輸入物価は上昇し、物価はマイナス状態から脱せた。また多くの輸出企業は外貨建ての価格を引き下げて輸出量を増やすのではなく、外貨建ての輸出価格を据え置いて、円で計った手取りを増やすという道を選んだ。これによって製造業を中心に企業収益は大幅に増加した。
しかし、この経験で分かったのは『円安は企業の持続的な成長基盤の強化にはつながらない』ということである。そもそも円安による物価引き上げや企業収益増大の効果を続けるには、円安が進み続けなければならない。当然、これは不可能である。円安の効果は本質的に短期的なものにすぎない。
企業もこれを自覚しているからこそ、収益が増えても設備投資や正社員の雇用を増やすのをためらい、ベースアップに慎重となる。
企業の持続的な成長基盤の強化には、働き方の改革を通じて労働生産性を高め、技術革新を図り、規制改革によって医療・介護などの福祉分野で民間活力が発揮できる範囲を拡大していくことが必要だ。
こうした成長戦略が効果を発揮すれば、生産性の上昇を反映して為替は円高方向に動く。円高への動きは輸入価格の下落を通じて交易条件を好転させ、国民の実質所得を高めるから、国民の生活や福祉水準も上昇する。これが円高のトリクルダウン効果だ。
長期的には、日本の企業の実力に応じて円高への動きが生まれるような経済を目指すのが正しい道である」。(日経新聞2016.07.21朝刊)
筆者は先日のブログで円高は次のプラス効果を日本経済にもたらすと書いた。
「1.輸入品の価格が下落する。原油価格の低下と相まって消費者物価をマイナスに導く。つまりは実質賃金が上昇し、円安時代に低迷した消費支出が増加する。
2.海外投資が増加する。長期的な内需の縮減を見越して円安のさなかにも海外企業のM&Aや海外直接投資が進展したが、この流れが一層際立ってくる。
海外投資の増加がもたらすリターンの還流は円高による企業収益の減少を補てんする。
3.円安によって企業の収益は輸出企業を中心にこの3年間で約25%増加したが、輸出価格の上昇による売り上げの増加や対外投資のリターンの増加によるいわば架空の利益に過ぎない。
つまり輸出企業は新規需要を開拓したり、コストダウンに取り組んだり、販売促進投資を積極的に行って設備の稼働率を引き上げたり、と言うような努力をすることなしにいわば濡れ手で粟の利益を享受しただけだ。
これに対して円高の環境は企業をこのような緩んだ対応は許されない。身を削るコストダウンの努力を重ね、新規重要開発のためのイノベーション実現のために積極的に投資したり、需要喚起のための販促投資を的確に行ったり、海外企業との資本・業務提携を推進して公債的な競争力を磨いたりすることが求められる。
つまり円高によって日本企業はより競争力を拡充する打ち手を実行しなければならない。そしてこのことが日本企業の実態を伴う競争力の拡充と成長を加速するということになる」。
まさに筆者の見解はそのまま日経新聞の認識と重なったということだ。安倍政権誕生以来日経新聞はアベノミクスの大本営発表を金科玉条にして喧伝してきたが、ついにその過ちに気付いて方針転換を始めたように思われる。
このコラムが日経の一部の非主流派のものではなく日経新聞の共通認識であることを期待したい。
もしかしてこの日経新聞のコラムは政府が円安から円高容認へと方針転換をすでにしていてその様子見のために放ったアドバルーンかもしれない。
読書ノート:顔伯鈞著『「暗黒・中国」からの脱出』(文春新書
手に汗握る逃避行。まるで映画「逃亡者」を観るような、中国の官憲からの追及を躱しながらの息詰まる逃亡生活を2年間も続けた筆者の逃亡の記録だ。
著者は中国の大学教員にして中国共産党員。もとは中国共産党中央党校の修士課程を終了したエリート。卒業後北京市の通州行政区人民政府に勤務したが現場の実態があまりに建前と乖離していることに絶望して離職し、北京工商大学の副教授として教育研究活動に転じた。
筆者は2012年ころから人権活動家の許志永の主催するNGO[公盟](公民)に参加し徐々に公民活動の中枢を担うようになった。
公民運動は「自由・公義・愛」をスローガンに掲げ、中国の社会改革と民主化を求める活動だ。この活動には絶対的な権力を持つリーダーや専従職員もいないそれ自体が民主的であり、自然発生の草の根的な活動だ。
公民活動の主たるイベントは「同城聚餐」と呼ばれる食事会だ。毎月末の土曜日の午後に同じ地域の住民が集まり、「環境問題」や「官憲の腐敗問題」などをテーマに議論する催しだ。
気軽に参加できる集まりと言うことが多くの人の賛同を呼び運動はあっという間に全国に広まった。12年末にはネットでの情報交換を通じて運動は大きく盛り上がりを見せた。
食事会と並行して行われたのが「官僚の財産の公開を要求する」運動だ。習近平の「反腐敗」運動を受けて、官僚の財産公開により官僚の特権を見える化し、腐敗の実態を明らかにすることが目論まれた。
著者はこの運動の中心となって当時香港で盛り上がった「雨傘革命」に呼応して北京で横断幕を持ってデモ行進をするイベントを企画し実行した。
こうした活動が全国的に広がるにつれて当局の弾圧も厳しく行われるようになった。
中国憲法は集会やデモの自由を認めているにもかかわらず、公民運動が民主化を求めていることから、共産党一党独裁体制を否定する運動に直結することを危惧し公民運動に積極的にかかわる人々を逮捕し、拘禁する事態に至った。
著者も逮捕の危険を察知し2013年4月から北京を脱出して以降2年間2万キロに及ぶ逃亡生活に入った。中国国内の逃亡生活は2015年5月にタイに亡命することで一応終わるが、現在なおもタイ政府が中国政府からの引き渡し要求を受けて拘束されることを恐れてタイ国内で潜伏生活を強いられている。
著者は過酷な逃亡生活の中で多くの公民活動のシンパに出会い、助けを求め、そして数知れない善意の支援によって厳しい官憲の眼を潜り抜けることができた。
こうした草の根の支援を経験する中で筆者は中国の権力につながらない市民の置かれている悲惨な状況に触れている。
例えば河北省太源の簡易宿泊所に潜伏した時、同宿してこまごまと支援をしてくれることになった若手インテリアデザイナーの肅海峰(仮名)の場合はこうだ。
肅はたまたまヘアサロンの内装工事を11万元で受注し、約2万元の利益を見込んでいたが、工事の途中で様々な計画外の出費が重なり最終的に彼の手元に残る利益はほとんど残らない状態で簡易宿泊所からの脱出は不可能になった。
その計画外の出費とはなにか。
「例えば施工を始めた数日後、市の城管(地方政府が運営する半官半民の治安維持組織)の男たちがやってきた。こちらの作業員が乗る電動バイクが路上をふさいだ罰金として500元を支払えという。わたしたちはやむなく、翌日彼らの事務所に支払いに行った。
だが、その後はたとえ駐車違反があっても罰金を要求されなかった。彼らは本気で都市環境整備のための取り締まりを行ったのではなく、単にみかじめ料をもらいに来ただけにしか見えなかった。
城管のほかにも、それから2週間ほどの間に、現地の協警(協助警察。警察業務を補助する民間人。日本の江戸時代の岡っ引きのような役割を担う)や治安管理人員を自称する男たちが合計5回もやってきて、そのたびに200~500元ほどを「管理費」の名目で掠め取った。また、市の環境保護局を名乗る男たちは、店の入り口にごみが溜まっているという名目で「罰金」600元の支払いを求めた。さらに停電のあとには、やはり市の電力関係部署を名乗る人々がやってきて、今度は「検査費」300元とタバコ2本を要求―――もはやキリがなかった。
さらには地元にチンピラとしか思えない身元不明の男たちも作業現場に10回近く闖入し、盛んにタバコをねだった。わたしたちはこういう連中が来るたびに彼らにタバコを一箱渡し、時には食事までご馳走して、期限をとってやらなくてはならなかった。さもなくばどんな目に遭うかわからないからだ。・・・
現代中国の社会で『持たざる者』は悲しいほどに無力だ。
彼らは権力を笠にきた小役人や街のチンピラに徹底していじめられ、ただでさえ少ない金銭と人生のチャンスを奪われ続けるのである」。
絶対的な独裁権力はその公的な統治機構の末端周縁に無数の疑似権力を生み出し、それらの末端に群がる偽権力が無力の市民から過酷な収奪を行う。市民は黙ってその理不尽な仕打ちに耐えなければ生き延びられないという惨状が生まれるということだ。
著者は2年にわたる逃亡生活のはてにタイへの亡命をめざし雲南省から密航を手引きするエージェントの援けを借りてミャンマー、ラオスを経由してタイへと入国するに至る。
こうした過酷な逃亡生活で、様々な厳しい困難に心身ともに打ちひしがれながらもなお著者は希望を捨てることなく、どのような時にも多くの人の善意に助けられ、それにこころから感謝をささげながら、常に前向きに進んでいる。
著者がこの逆境に耐えるうえで支えとなった言葉こそ、「君子は以て自強して息まず」(易経の言葉で、知識人たるもの自己の向上を怠るな)であった。
つまり著者を支えたのは大義を追求する強烈なエリート意識であったということだ。これほどまでに揺るぎのない確固たるエリート意識を作り上げたのはおそらく共産党員として受けたエリート教育のたまものではないか。
その教義に素直に同化した純粋な向上心こそが水滸伝を彷彿とさせる現代の武勇伝の原料であったということだ。
とすれば中国共産党の党員教育は原理主義者を生み出すという意味において体制にとっては危険な装置とならざるを得ない大いなる矛盾をはらんでいるに違いない。
円が「最強通貨」であることは喜ぶべきこと
円が「最強通貨」になることにそれほど悲観的になることはない。円高は次のプラス効果を日本経済にもたらす。
1.輸入品の価格が下落する。原油価格の低下と相まって消費者物価をマイナスに導く。つまりは実質賃金が上昇し、円安時代に低迷した消費支出が増加する。
2.海外投資が増加する。長期的な内需の縮減を見越して円安のさなかにも海外企業のM&Aや海外直接投資が進展したが、この流れが一層際立ってくる。
海外投資の増加がもたらすリターンの還流は円高による企業収益の減少を補てんする。
3.円安によって企業の収益は輸出企業を中心にこの3年間で約25%増加したが、輸出価格の上昇による売り上げの増加や対外投資のリターンの増加によるいわば架空の利益に過ぎない。
つまり輸出企業は新規需要を開拓したり、コストダウンに取り組んだり、販売促進投資を積極的に行って設備の稼働率を引き上げたり、と言うような努力をすることなしにいわば濡れ手で粟の利益を享受しただけだ。
これに対して円高の環境は企業をこのような緩んだ対応は許されない。身を削るコストダウンの努力を重ね、新規重要開発のためのイノベーション実現のために積極的に投資したり、需要喚起のための販促投資を的確に行ったり、海外企業との資本・業務提携を推進して公債的な競争力を磨いたりすることが求められる。
つまり円高によって日本企業はより競争力を拡充する打ち手を実行しなければならない。そしてこのことが日本企業の実態を伴う競争力の拡充と成長を加速するということになる。
このように考えれば円が「最強通貨」になることを悲観したり、恐れたりすることはまったく見当違いな行為と言うことになる。
それでなくても円高は日本の資産価値が高く評価されることに他ならない。何よりも24日に大幅に下落した株価が本日は上昇基調にあることがそのことを雄弁に物語っている。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/062200372/?P=1
参議院選挙開示にあたって
読書ノート:藻谷浩介著『和の国富論』(新潮社刊)
藻谷氏とユニークな実践者との対談集だ。
対談相手はいずれも現場に根差して日本固有の現実と向き合って確実に付加価値を生み出す実業を実践しているという意味でユニークなのだ。
本書で最もユニークな対談者は林業を経営する速水氏だ。
速水亨氏:1953年三重県生まれ。速水林業代表。慶應義塾大学法学部卒。東京大学農学部林学科研究生を経て、現職。森林再生システム代表取締役。日本林業経営者協会顧問。
まずは林業の奥深さが語られる。
「藻谷 今朝、三重県の尾鷲林業地域にある速水さんの山林に来て驚いたのは、谷川の水がまったく濁っていないこと、昨晩は台風であれだけの豪雨だったのに。
速水 うちの山は、間伐を強くしているから、地面まで日光が届き、下草が生える。その下草を刈らずに残しておくから、表土が流出せず川が濁らない。下草のおかげで、土壌自体も豊かになって、木も良く育つ。
じつは川を見れば山林の状況というのは全部わかります。下流の石をめくって、虫がいっぱいついているのは、泥が少ない証拠。つまり山の手入れが行き届いているってことです。
藻谷 速水さんのご著書『日本林業を立て直す』を拝読して、改めて林業の奥深さを勉強させていただきました。例えば年輪の幅がきれいにそろっている木を育てるのも、そう簡単ではないと読んで、『なるほど』と。
速水 ええ。木は年をとればとるほど成長量が衰えていきますが、年輪を揃えるためには、逆に年々成長量を増やしていかなきゃいけません。
藻谷 円周が大きくなれば、同じ年輪幅を保つために必要な成長の面積は、二次関数的に増えていく。なるほど、言われてみればそうですが、人間に例えれば、いつも前年以上に背を伸ばし続けなければいけないという話で、簡単にできるわけがない
速水 だから、木の成長とともにドンドン間伐をして、一本当たりの枝葉の量を増やし、太陽光を取り入れる力を強くしていくわけです。間伐の際は、みんなその時点の森林の状態を良くしようと考えてしましがちなんですけど、本当は数年後の状態をイメージしてやらなくちゃあいけない。
藻谷 ご著書には、間伐は『遺伝子の選別である』とも書いてありましたね。
速水 ええ。うちの間伐は、小さかったり曲がったりしている悪い木を伐っていく。それを世代を超えて繰り返していくうちに、どんどん遺伝子の淘汰が進んで、森の平均点が上がってくるわけです」。
林業は木を育てるのではなく森を育てる仕事だ。だから目指すゴールは少なくとも50年先を見据えなければならない。
速水氏は「300年後の法隆寺の補修にこの木が使ってもらえるかもしれない」というような超長期のビジョンを持って仕事をしているという。
林業に対する需要は健在だけではない。バイオマス燃料としての需要も拡大しつつある。
「速水 需要を増やすと言えば、藻谷さんが『里山資本主義』で紹介していた木屑を使ったバイオマス発電。実はうちの山の木も随分とバイオマスにいっているんですよ。
藻谷 いや、じつは本を出してから内心冷や汗をかいているのです・・・。本で紹介したのは、製材所からでる木屑の燃料使用であるわけですが、燃やすことを主目的に木を伐る動きも各地で出てきている。そうすると、また日本がはげ山だらけになってしまいかねません。
速水 いえいえよくぞ書いてくださいました。今後人口が減っていく時代に、住宅などの耐久消費財として木材を使っていくだけでは林業の将来性はないと思っていました。消費財としての燃料という需要は、林業にとって救世主だと思います。周囲からは『100年かけて育てた木をもやしてしまっていいのか』と言われるけれど、もともと燃料として木を使っていたわけですし、そもそも建築用の木材に使うのは主に木の幹の下の方だけで、上の部分の梢端部や枝葉を燃やす分には効率的です」。
木屑や枝葉など林業が生み出す未利用資源がエネルギー源として活用される時代が来ている。
日本の林業の困難は継続的な木材価格の低下だ。この原因を巡って驚くべき実態が明らかになる。
「速水 木材だろうがバイオマスだろうが、木を伐ったら、その分は必ず植えるというのが林業の基本です。
今の森林法の問題点は、森林所有者に造林義務を課してはいても、現実的には伐採行為者には強い義務を課していないことです。林業を見限った所有者が、少しでも森林から資金を回収するために、法の抜け道を利用して、安い値段で素材生産者に立木を売ってしまう。素材生産者は植林コストを負担しないで木を伐採し、安値で叩き売るから、今のように再生産が不可能な値段まで市場価格が下がってしまう。再生産を目指さない伐採行為からでてくる木は、再生産を目指す業者の木を瞬く間に駆逐してしまうんです。
藻谷 うーん、まさに『悪貨は良貨を駆逐する』ですね。そうなると、日本もまたハゲ山への道をまっしぐら・・・
速水 伐採作業をする素材生産者に強く再造林義務を課せば、彼らはそのコストを上乗せした値段でしか売れなくなるから、今のように市場価格が値崩れすることはなくなります。
藻谷 ただ、本の中では『そうすると日本の木を伐採する人が誰もいなくなるだろう』とも書いていらっしゃいましたね。
速水 たしかに儲けが出なければ、誰も木を伐らなくなる。だから、植林コストも含めて、ちゃんと利益が出るようにしなくてはならない。
そのためには、まず、海外で違法伐採された木の輸入を禁止すること。再生産の義務を課していない木は一本たりとも日本に入れてはいけません。
藻谷 郊外を垂れ流す海外の工場で作った製品を買うべきではないのと同じですね。よくCMで、『アマゾンで植林をしています』『東南アジアの森を守っています』とか流れていますが、ああいう会社は再生産義務を果たしているのですか。
速水 企業によりますが、たいていの場合、これまで伐採してきた面積に比べて、わずかな面積に植林しているにすぎません。また、豪州やインドネシアでは、ユーカリやアカシアマンギウムという超短伐期の木を植えている。これらは成長が速い分、養分を大量に消費するので、土壌が痩せ衰えて、長期的には再生産が不可能になってしまいます。
藻谷 ご著書の中に、『ラワン材の違法伐採の末に、木材輸入国に転落したフィリピンでは、結局誰も幸せになっていない』とあったのが印象に残っています。
速水 そうです。だから、他の先進国はみんな違法伐採されたものは買わないという法律を作ったわけです。それなのに、日本だけが創らない。
環境意識が高いEUはもちろん、アメリカもレイシー法という州間の野生動物などの取引を禁止した100年以上前の法律を改正して、違法伐採を規制しています。遅れていたオーストラリアでも新しい法律ができました。そのうち、違法伐採の木材がすべて日本に集まるなんてことになりかねない。
藻谷 規制嫌いのアメリカが、よく規制に踏み込めましたね。林業ロビーとかに邪魔されなかたのでしょうか?
速水 いや、林業ロビー自体がそれをやりたがったのです。違法伐採の木を規制したら、木材価格が6%上がるはずだと計算して。日本でも、法政大学の島本美保子教授が、違法伐採材の輸入を規制すればベニヤの値段も上がるという試算をしています。規制は林業関係者にとっても、ベニヤ業者にとっても絶対にプラスになるはずなんですが・・・・
藻谷 違法伐採木を輸入すると、みんなが損をする。だからアメリカの林業ロビーだって規制に賛成したのに、日本がそれをやらない理由ってなんでしょう?
速水 それはすごく簡単な話で、ただ面倒くさいだけなんですよ。
藻谷 えっ!と驚きたいところですが、日本では良くある話ですよね。本当は規制をした方が、公益に則するだけでなく企業も儲かるんだけれど、『規制緩和』という、怪しい経済学者が広めた現代の錦の御旗に逆らうのは、エネルギーを要するのでやりたくない、と」。
日本林業にとっても地産地消が需要拡大の決め手となる。
「速水 日本には製材工場が5000以上もあるんです。正直に言えば、むかし通産省が繊維の機械を壊して業界の集約化を進めたように、製材業界もある程度集約化をすすめていくしかないと思います。
しかし一方で、地域に根差した製材工場として、地元の工務店と連携しながら、生きて行く道はあると思います。年間に何万戸も既製品のような家を建てる巨大な住宅メーカーがあるのは日本ぐらいです。もっと自分好みの家をじっくり建てたいという需要にこたえるのが、地域の製材工場の役割じゃないかと思います。
藻谷 確かにアメリカのほうがよほど、個人住宅のデザインは個性的ですね。みな木造で新建材の家などむこうでは見たことがない。地域の個人需要に応えるパパママ・ストアがなくならないように、地域に密着した小さな製材所も必ず生き残れるはずだというわけですね」。
読書ノート:T.ソーチック著『ビッグデータ・ベースボール』(角川書店刊)
2012年まで20年間負け越しを続けたメジャーリーグ中部地区のピッツバーグ・パイレーツが2013年になんといきなり地区リーグ2位になる大変貌・大躍進を遂げた。
この劇的な業績改善を成し遂げた裏にはビッグデータの活用による戦術の大転換があった。
パイレーツのジェネラル・マネジャーのハンティントンと監督のハードルは、2013年の成績が従来のような無様な形で終われば、解雇されるに違いないという状況に追い込まれ進退窮まっていた。
この困難な状況を切り開くために二人はデータ活用による戦術の大転換に賭けるしかなかった。
彼ら二人のリーダーシップの下で実現した戦術の大転換は従来の野球界の常識からすれば「そんなバカな!」と言われる打ち手の連続技だった。
「ヒットは投手に責任があるのではなく守備の責任だ」
データ解析によって守備位置が適切でないことによるヒットが多いことが確認された。打者の打球の飛ぶ方向には規則性があり、この規則性に従って飛んでくる打球を待ち構える守備位置に野手が配置されればヒットの数は大幅に減少するということだ。
従来の守備位置は均等間隔が常識で誰もそれを疑うことはなかった。
「投手は三振よりゴロを打たせる方を高く評価しよう」
打者によって守備位置を最適化することが行われれば、投手は三振を奪うより内野ゴロを打たせてアウトにすることに徹したほうが良いということになる。となるとゴロを打たせる球種た球速を特定しその球種・球速に特化して投げ込んでいけばよいことになる。
「ピッチフレーミングに価値を見いだす」
ボールかストライクかの判定がむずかしいきわどいコースに投げ込まれたときに審判の判定に影響を与える捕手の技術がピッチフレーミングだ。
「捕手によるボールの捕り方は視覚のトリックで、その巧みなごまかしの技術によって主審にきわどいコースの投球をストライクと判定させることができる」。
この技術は捕手によってレベルに大きなばらつきがある。ピッチフレーミングを通じて1シーズンあたり約15点~30点の失点を防いでいた優秀な捕手がいた一方で、1シーズンあたり15点も失っている計算になる捕手もいたという。
パイレーツのデータ分析官たちは膨大なデータを活用してこのピッチフレーミングにずば抜けた才能を発揮している捕手を探し出し獲得した。こうしてスカウトされたのがラッセル・マーチンだった。マーチンはパイレーツに移籍して、これまで正当な評価がされていなかったピッチフレーミング技術を高く評価されたことも手伝って、チームの要として信じられないほど大きな貢献をした。
「投手を負傷から守れ」
シーズン中にかかる投手への肉体的負担はきわめて大きい。より速い球が期待され、より多様な球種を要求されるようになってその負担は極限に達し、負傷して手術を受ける投手が急激に増えている。
予算上の制約から投手の人数に制限を設けざるを得ないパイレーツにとって投手の負傷は致命的な戦力ダウンをもたらす。いかに負傷から投手を守るかがパイレーツにとって死活的な課題になった。
この課題に対するソリューションもデータ解析によって得ることが可能になった。投手にデータ測定装置を装着してもらって、投球のフォーム、球種、球速によって身体のどの位置にどれほどの負担がかかるかのデータを収集し、このデータを解析していかに負担を減らすかの処方箋を導き出した。
以上のようにこれまでは非常識と考えられてきた戦術を次々と打ち出すことを可能にしたのは2007年以降急速に進んだデータ収集の装置の球場への設置とそこから得られる膨大なデータの公開であった。
PITCHf/xは2007年にデータ収集装置として設置が始まり数年後には全球場に展開を終わっている。PITCHf/xは投手が投げた投球の速度、球種を始めその軌跡を三次元で計測してデータ化した。
2013年にはさらに進化した装置「スタットキャット」が導入された。これはグランド上のすべての動き、すべてのステップ、すべての送球を全面的に数値化する異次元の装置だ。すでに2015年には全球場に設置された。
こうしたデータ収集面のイノベーションによって野球に関わるビッグデータが公開され活用される時代が本格化しつつある。まさにパイレーツはそのパイオニアとしてこのイノベーションをリードしたことになる。
このイノベーションを成功に導いた要因を本書から取り出すと次の二つになる。
「仮説検証がすべての鍵だ」
膨大なデータをやみくもにコンピューターに投げ込んでぶん回してみても価値ある情報は得られない。やはりここでも「ギャベッジイン・ギャベッジアウト」の原則が生きている。現実にしっかり向き合う中で得られた仮説をまずは組み立てることが必要なのだ。この仮説に基づいてそれを検証するべきデータを選択しこれらのデータを分析してはじめて有意な結果が得られるということだ。
「現場と分析官の双方向コミュニケーションが仮説を生み出す」
そして何よりもこの仮説を生み出すプロセスが大事だ。仮説は現場に埋め込まれている。埋め込まれている仮説を掘り出すのにはデータ分析官が現場に足しげく通い詰めて、現場との双方向のコミュニケーションを成立させていることが必優なのだ。
現場は当初は分析官に「胡散臭い奴だ」という目を向ける。現場からの信頼を獲得するのは分析官が現場に出向いて現場の困難な課題を引き受け、データ解析を活用してそれを解決する糸口を見つけることを重ねるしかない。
現場から頼りになる存在だという認識を重ねることで分析官と現場との良い関係が生み出されていく。こうした関係が構築されてはじめて分析官は現場に埋め込まれている仮説を掘り出す機会を手にすることが可能になる。
「現場と分析官の双方向コミュニケーションが戦術の大転換を実現する」
現場と分析官との良好なコミュニケ―ションが進化するにつれて、これまでは非常識だった戦術を共有し、実践的に展開する機運が生まれてくる。
この戦術の大転換を共有するためのミーティングをリードするのはもちろんGMや監督やコーチたちだが、この時彼らの提案する戦術の絶大な効果を分析官はデータ解析によって見える化し、説明しなければならない。
この分析官の説明を選手たちが素直に前向きに受け止めてくれるかが戦術転換の決定的な鍵になるが、この鍵が有効に作動するかも現場と分析官とのコミュニケーションの深さにかかっているということなのだ。
セブン&アイのガバナンスは実はまことにお粗末だった
日経ビジネスオンラインがセブン&アイの鈴木会長の記者会見の一部始終を掲載している
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/040700304/?P=1
そこから浮かび上がったのはまことにお粗末な経営の実態だった
記者会見には鈴木会長と村田社長のほかに佐藤氏、後藤氏という二人の顧問も同席していた。経営の責任を担っているわけでもない二人がなぜ同席したのか。
それは今回の辞任劇の背景に伊藤最高顧問が井阪社長更迭について反対であったことがあり、その経緯を伊藤顧問と鈴木会長の「連絡役」に説明させるためであった。
「鈴木会長から紹介されて最初にマイクを握った後藤顧問の語った話は、日本を代表する企業の実態とは思えないようなお粗末な中身だった。『伊藤名誉会長と鈴木会長のお部屋を行ったり来たりする役割』『井阪社長のお父様と昵懇の仲』など、理よりも情実や縁故が物を言うような、極めて属人的に経営の意思決定がなされてきた様子が浮かび上がった」。
彼らの話から浮かび上がるあらすじはこう推測される。
鈴木氏が井阪氏に社長解任の内示をしたとき、井阪社長はこれを受諾した。しかし井阪社長が伊藤最高顧問に報告した時点で、伊藤氏は井阪氏に「やめる必要はない。鈴木さんに受諾しない旨つたえなさい。私があなたの社長継続を約束する」と説得した。そこで井阪氏は鈴木氏に叛旗を翻す決心をしたということだ。
その後伊藤氏は井坂氏や伊藤氏の二男の伊藤雅敏取締役と一緒になって取締役会で人事案を否決すべく多数派工作に取り掛ったというわけだ。
鈴木氏は「資本と経営の分離」を標榜し、赫々たる実績を気付きながら伊藤氏から経営の実権を与えられてきたという自信がある。しかし伊藤氏からしたらその実績は認めるもののすでに83歳に達した鈴木氏にいつまでも経営を任せておくつもりはなかった。チャンスを見て鈴木降ろしの行動に移るべく身構えていたということだ。
そこへ鈴木氏が井阪氏の社長解任の人事案を提案した。井阪氏のもとでセブンイレブンは7年間最高益を塗り替え、コンビニ業界さらには小売業界でのゆるぎない地位を築いてきた。外部から見れば解任されるいわれは全くない理不尽な人事だ。
鈴木氏にしてみれば7年間社長を務め求心力をましてきた井阪氏が自身のコントロールを超えるモンスターになる兆候に懸念を覚えていた。そこで自身のコントロール下で唯唯諾諾と汗を流すだけの古屋副社長に替えようと思い立ち社長更迭を画策したということだ。
この鈴木氏のムリ筋の人事案に伊藤氏はすかさず隙をついてきたというわけだ。
なんのことはない。ことは伊藤氏と鈴木氏の長期にわたる潜在的な権力闘争が表面化したということだ。
残念ながらセブン&アイのコーポレート・ガバナンスの実態はお粗末と言わざるを得ない。
本年度第一回目の"中田康雄を囲む会"を4月27日(水)19時から行います
歓談の他、ゲストと中田による講義と、参加者からの自社プレゼンを数社予定しております。
(株)ドリームアーツ常務の小河原様(元アスクル執行役員)にお越しいただき、アスクルの急成長フェーズにおけるIT及び営業上の"修羅場"や学びをお話しいただきます。
【日時】2016年4月27日(水)19時〜21時
【場所】XEX日本橋
銀座線、半蔵門線の三越前駅A9出口直結、日本橋室町野村ビルYUITO4階
http://www.xexgroup.jp/nihonbashi/access
【人数】企業のマネジメント層や起業家中心に40名ほど
ご参加いただける方は下記の参加登録フォームより登録をしていただければと思います。
参加登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1hZfgqJC1Yi8jK74dF8HtwZWpJmsAIaKvYpqv9gp5x1g/viewform
日経新聞2016.03.15「経済教室:一橋大学教授青島矢一『電気不信は何を写す』」
かつて日本の製造業を牽引した電気・エレクトロニクス産業の衰退が著しい。その根本要因に青島教授が迫り明解な解明を試みている。
青島教授の論考を敷衍すると以下のとおりになる。
日本企業の強みはモノつくりだった。より良い品質の製品を作れば売れる、というある意味でプロダクトアウトの意識が根底にあったわけだ。
この強みは半導体の微細化と集積度の向上そしてソフトウエア制御の高度化によって過去のものになってしまった。いわば誰もが高品質の製品を作れる時代になってしまったのだ。
こうした時代には単品を超えた製品の組み合わせや付随するサービスの提供が求められるのだが残念なことに日本企業は事業部制の壁に阻まれて、企業内部の製品群の組み合わせさえままならない状況に陥っている。
またこうした製品やサービスの諸機能の結合は顧客の生活実態に寄り添ってはじめて実現できるのだが、その実現を阻むさまざまなリスクを引き受ける強力な経営意思と必要資源を自社の枠組みを超えて活用する編集能力が日本企業にはきわめて貧弱である。
総じていえば今求められているのは真の顧客本位に向かう意識改革と、自社の諸能力を事業部を超えて組み合わせること、これに加えて自社を超えて存在する先進的な知識・技術やそれを担う人材資源との協働の枠組みを形成し実行する強い経営意思なのだ。
革めて青島教授の論考を見てみよう。
「第1の原因は、半導体の微細化に起因する技術進歩により、『より良いモノ』を生み出す日本企業の強みが生かされにくくなったことである。
半導体の集積化とソフトウエア制御の進歩により、多様な機能を組み合わせる自由度は飛躍的に高まり、固定的な製品の枠に縛られた改善努力は相対的に価値を失う。より良い製品を届ける『すり合わせ能力』は価値につながりにくくなる。
こうなると産業の付加価値は、既存の製品や事業の枠を超え新たな組み合わせを提案するソリューション事業や、様々な製品に広く使われる強い基本部材を提供することに移転する。しかし日本のエレクトロニクス企業の多くは、モノの境界にこだわった事業から脱却できなかった。
第2の原因は過剰な政策的保護である。技術的に成熟段階にある産業を無理に支援することは、短期的な延命措置として機能しても、根本的な問題を先送りし、その後のダメージを大きくする。一例が2009年5月導入の家電エコポイント制度だ。
第3の原因は環境変化の中で生じた経営の機能不全である。一つは市場と技術の複雑性の増大スピードに経営が追いついていないこと、もう一つは経営に効率性や透明性を求める圧力に屈してイノベーション(技術革新)への投資がおろそかになったことだ。
より深刻な問題はイノベーションの創出に十分な資源が振り向けられなくなったことだ。バブル崩壊後の業績低迷の中で、一方では強く効率性が求められ、他方では透明性、説明責任、コンプライアンス(法令順守)が要求されるようになった。
その結果、不確実性が高く、説明が難しいイノベーションへの投資が困難になった。当面の収益に貢献しないイノベーション活動は後回しにされた。新規事業の種が枯渇し、既存製品の改良を中心とした事業展開を余儀なくされた」。
こうした状況を打開する方向性については以下のような処方箋が提示された。
「技術進歩に伴う問題は顧客価値の本質を改めて見直す必要性を示唆する。顧客は様々な製品の機能を組み合わせて価値を実現している。だから一つの製品をいくら良くしても、顧客に価値をもたらすとは限らない。顧客は供給者よりも広い視点を持つ。顧客の広い視点を共有して、目の前の製品の枠にとらわれず、価値を高める方法を柔軟に考えることが重要だ。
複雑化する市場への対応では他社の力を借りる手も考えられる。フラッシュメモリーでの東芝と米サンディスクの関係のように、開発や生産での日本企業の強みを理解する適切なパートナーと協業し、海外市場展開は任せてしまうのが、解決に向けた近道かもしれない。経営再建中のシャープにとって鴻海(ホンハイ)精密工業がそうしたパートナーになる可能性はある。
イノベーションへの対応は難しい問題だ。効率性や透明性の追求は、逸脱を伴うイノベーションと本質的に相いれない。これら矛盾する2つの課題を両立させるのが経営の妙だが、大手企業ではますます困難になりつつある。
一方で、優秀な人材も余剰資金も大手企業が囲い込んでいる。ならば大企業では正当化されないイノベーションを推進する中小企業の活動に、大企業の優秀な人材と豊富な資金を活用することが全体最適をもたらすはずだ。ベンチャーに投資するコーポレートベンチャーキャピタルや技術者の異動を含めた大企業と中小企業の協働が必要だろう」。
「国際金融経済分析会合」は「愚者の会合」だ
政府は16日、世界経済について有識者と意見交換する「国際金融経済分析会合」の初会合を開いた。
この席で日銀の黒田東彦総裁がジョセフ・スティグリッツ米コロンビア大教授にこんな問いを投げかけた。
「『不可思議なことがある。アベノミクスのもとで企業収益は改善し労働市場も引き締まっている。急速な賃上げが起きるのが普通だと思われるが、実際の賃上げのペースは緩い』」
スティグリッツ教授は米国では職探しを諦めた人が失業者に分類されないなど『失業率が労働市場を正確に表していない』と指摘。『失業率とインフレ率の関係が瓦解してきている』と語った」。(日経新聞2016.3.17朝刊)
世界経済の経済政策の中心に据わる経済学者並びに経済官僚たちがこんな間抜けた議論をしていることにあきれ果てた。
グローバル化した市場経済の只中では各国政府が打ち出す経済政策はもはや効力をまったく喪失してしまっていることにいまだに気付いていないということに驚かざるを得ない。
たとえば未曾有の金融緩和を実行しても企業は最も有効な投資先を世界中に求めるから、国内の民間投資が増加することはありえない。
企業は世界中の多国籍企業との競争に明け暮れているから、製品価格は世界水準に収斂し、したがって賃金も世界水準に収斂するので、利益が増加したとしても賃金を上げるビヘイビアにはつながらない。
こんな単純な事実をさておいてすでに陳腐化した一国経済の枠内でしか通用しない議論に血道を上げている「国際金融経済分析会合」はまさに愚者の会合と言わざるを得ない。
日本農業の再生のために何をなすべきか
日本農業の抱える三重苦
日本農業は三つの大きな困難を抱えています。
第一の困難:コメ中心の農業システム
困難の一つ目は日本農業が稲作を中心に組み立てられていることです。
弥生時代に日本で稲作が広範囲に展開して以来、コメ作りは日本の農業の中心に位置してきました。ヤマト朝廷の統治システムとしての律令制はコメ作りを経済・産業基盤として成り立っていました。以来今日までコメは日本農業の中核として、更には「豊葦原は瑞穂の国」たる日本の経済社会の基盤としての役割を担ってきました。
このような長い伝統を持つ稲作中心の日本農業を決定的なものにする方針決定が1960年に行われました。「農業基本法」の施行です。これによって政府の農業政策は稲作至上主義の色彩に染められることになりました。
この時以来農業の振興を意図した予算措置はことごとく稲作生産システムの改善と稲作農家の保護に向けられ、コメの耕作面積そしてコメ生産量は70年には史上最大の規模を記録するまでに至ったのです。
しかし1970年代になって日本人の食生活は大きな変貌を遂げることになりました。食品の消費カロリーは戦後の飢餓時代以来増大し続けましたが、やがて飽食の時代を迎え1972年の一人一日当たり2287kcalをピークに摂取カロリーは減少局面に入り、現在に至るまで一貫して減少を続け、今では1800kcalを切るまでになりました。
同時に食文化の欧米化が進展し、コメ中心の食生活は分解再構成の時を迎え、小麦や牛乳や食肉を原料とする食品の増加に伴う食生活の多様化の時代になりました。
以上の二つの要因によってコメの消費量は著しく減少し、結果としてコメの生産過剰が表面化し、この対策として減反政策が余儀なくされ、余剰となった水田は休耕田や耕作放棄地と化し、農地という貴重な生産手段が大量に未利用のまま放棄されるに至りました。
第二の困難:畑作農業の貧困
日本農業の抱える二つ目の困難は畑作が著しく貧困かつ脆弱であることです。畑作の中心的な作物は小麦、大豆、飼料用トウモロコシ、馬鈴薯ですが、その自給率は小麦13%、大豆28%であり、なんと飼料用トウモロコシにいたってはほとんどゼロという惨状を呈しているのです。
畑作ものの生産量が著しく少ない要因は先に見たようにコメ中心の農業政策が続けられてきたことにあります。しかしいかにコメ中心とは言え畑作は70年代まではそこそこの耕作が行われていました。因みに1965年の自給率は小麦が28%、大豆は41%を記録しています。先に触れたように1970年の「農業基本法」の制定を契機に稲作が農政の中心に置かれることが決定的になることで、畑作農業は一気に壊滅的な状況を呈していったのです。
稲作中心の農政への転換は、畑作物は海外からの、特にアメリカからの輸入に依存することを決定づけるということを意味していたのです。
日本の安全保障をアメリカに依存することの見返りに畑作物の供給をアメリカにっ全面的に依存することが取り決められたと理解することが妥当のようです。
第三の困難:畜産業の脆弱さ
日本農業の抱える三番目の困難は畜産業がきわめて脆弱であることです。畜産物のうち肉類の自給率は55%ですが、そのうち国産飼料で飼育された肉類の自給率はなんと9%でしかありません。豚肉に至っては国産飼料で飼育された自給率はわずか6%にとどまります。
農業の生産システムにおいて畑作と畜産は相互補完関係にあります。家畜の屎尿は堆肥となって土壌の改善に活用され、畑作物の生育に欠かせない資源になります。また畑作物は飼料用トウモロコシをはじめ、大豆、小麦など家畜の飼料として活用されます。このような耕畜連携こそ大地を媒介項とした自然の循環システムであり、これが持続可能な農業生産システムを作り出すのです。
さらに畑作物の規格外品や余剰品さらには畑作物を原料とした食品加工プロセスで排出される残滓も飼料として有効に活用することが可能です。これらの未利用資源はタダ同然で家畜の飼料として供され、畜産物の価格をリーズナブルな水準に維持する原動力となっているのです。
こうした耕畜連携こそ1000年以上の歴史を誇る欧米の農業生産システムの基軸となっているのです。日本の農業システムに畜産という機能を欠くに至った要因も稲作中心の農業に求められます。すなわち畑作が農業の中核に位置づけられてこなかったという歴史的な要因が畜産業の脆弱性を決定づけているのです。
明治維新にいたるまで日本では「食肉忌避」の食文化が支配的でしたが、このことも畜産が業として成立することを妨げてきたと見ることができます。しかしこの風習ももとはと言えば天武天皇の「食肉禁止令」(675年)が発端であり、この勅令の目的が稲作の生産量の増産のために農繁期には食肉、飲酒を禁止して、農作業に精励することにありました。この食肉禁止令は稲の生育中に肉食すると稲の生育が悪くなるという信仰が背景にあり、農繁期に限られた禁止令でありましたが、いつの間にかそれが肉食の忌避へと拡張されていったと理解することができます。いずれにしろコメ中心の農業が畜産の発達を妨げた主要因であったということができるわけです。
TPPは三重苦を拡大する
TPPによってコメを除く農畜産物の関税はやがて撤廃ないし大幅に削減されることになります。特に食肉の関税が廃止されることによって日本の畜産業は壊滅状態になることが予想されます。関税の廃止によって食肉は掛け値なしの価格競争に向き合うことになり、基本的にタダ同然の飼料価格で飼育される米、豪の食肉との競争に敗退せざるをえないということになるのです。
畜産業が潰されれば畑作農業も効果的な堆肥の供給源を失い小麦も大豆もトウモロコシ同様に深刻な打撃を受けることになります。
かくしてTPPは日本の農業の再生の道を完全に閉すばかりか、現状の細々とした状態の畑作農業の息の根を止めることになります。
何をなすべきか
日本農業の抱える三重苦からの離脱はいかにして可能でしょうか。
田畑転換
まず初めに取り組むべきは畑作の再構築でありましょう。畑作の再構築の第一歩は放置されている水田を畑地に転換することです。
現在水田のうち休耕田は100万ha、耕作放棄地は70万haあるとされています。(農水省は減反面積を平成16年度以降公表をやめました。従って正確な数字は農水省の開示資料からも窺えません)
水田から転換された畑地は4つに区分し、一区画ごとに小麦⇒馬鈴薯⇒大豆⇒カバークロップというように輪作する4圃制の輪作体系を導入します。一区画ごとに毎年作物を入れ替えることで土壌の疲労を回避し、また4年に一回休耕地とすることで土壌の養生が行われ生産性の継続的な増大が可能になります。
耕畜連携
次いで構築連携のシステムつくりを行います。地域内に畜産農家が、畜産農家の飼料を輸入品から地域産への置換を促します。この時の決め手は飼料価格をタダ同然の価格で供給することです。当面は輸入飼料に混ぜる形での置換を進めることになりましょう。
もう一つ重要なことは家畜の屎尿を堆肥にして畑へ還すことを実行することです。堆肥は余剰が出ればバイオ・エネルギー源としての利用も可能になります。
農工連携
畑作物の生産が始まれば必要になるのは畑作物を原料とする加工食品の生産システムを再構築することです。小麦にはパン工場、麺工場、パスタ工場が、大豆なら味噌工場、醤油工場、納豆工場などとの連携が構築されなければなりません。
畑地に転換された地域に食品加工場があればその原料を輸入品から地域産への置換を進めることです。地域に加工場がなければ食品加工場を誘致して地域内で生産される畑作物を地域内の加工場で加工し、地域住民へ提供する地域内の農産品の連鎖を形成することが必要です。
食品加工場と畑作農家の間には農産品の売買契約が締結されることになります。品質規格を前提に規格品の売買量と価格を取り決め、播種前に締結します。契約は天候による作柄の豊凶に関わらず約束した量と価格をたがえずに履行することが求められます。
従って農家は作柄が良くなくとも契約を履行することが可能なように契約量の20~30%増しの播種を行います。この余剰を前提とした播種を無理なく行うためにはあらかじめそれを前提とした売買価格設定が行われます。
また農作物には品質規格が決められていて品質の格付けによって価格が決められます。高品質の作物を生産すれば農家の収入が増加するというインセンティブは高品質に向けて改善改良を農家に促すことになります。食品加工メーカーは高品質の原料を加工することで高品質の製品がムダなく生産可能になるということで歩留まりが上がり、メーカー自体も収益を拡大することが可能になります。
こうして契約栽培の仕組みは「利己主義」に基づく市場経済のルールを超えた「利他主義」の原理に基づく取引とかんがえることができるのです。
「スマート・テロワール」の形成
これまで見てきた日本農業の再生の道は畑作農家、畜産農家、食品加工業者が三位一体の連携をすることではじめて可能になります。
加工業者は消費者から製品の品質や価格に対する様々な要求を受け止め、それを実現すべく、加工プロセスの不断の改善を実施し、そのために原料農産物の品質規格を設定します。農家は農産物の品質向上を目指して栽培プロセスの改善を進め、更には種子の改善、開発に力を注ぐようになります。
こうした農・畜・工の連携を前提としたチームワークが特定の地域内で機能することが畑作の再生ひいては農業・農村の再生が可能になるのです。このチームワークに地域の消費者も参加し、地域の産物を消費する、地産地消の行動に転換することではじめて大きな効果を産み出すことになります。
このような地域のありかたを「スマート・テロワール」(美しく強靭な自給圏)と名付けその実現に向けて努力を結集することが今求められています。
「スマート・テロワール」の実現は農業・農村の再生を結果するばかりではありません。これまで輸入に依存してきた畑作物、畜産品が自給品に置換されます。そして自給原料を加工することで地域の加工場は操業規模を拡大することになります。
農畜産物と食品加工場の規模拡大は地域の創造する付加価値額を拡大し、同時に地域の雇用を生み出します。農村から都市への人口移動が逆流を始めることになります。雇用の場が拡大することで若手のUターンも一気に拡大します。若年層の都市への流出が止まり、逆流が始まれば出生率も改善をし始めます。農村の出生率は都市よりも高く2.0人を上回るところも多いことから、少子化の流れを押しとどめることが期待できるのです。
さらに農村の景観が変わり、美しい村が返ってきます。畑作の回復は水田中心の景観から多様な畑作物が生育し、豚や牛が放牧される色とりどりの風景へと変化しはじめます。コメ一穀から五穀豊穣の風景への大転換です。
こうした美しい村は都会の人々を引きつけるようになります。地域の畜産物を美味しく調理して提供するレストランやホテルが生まれることになります。まさに「スマート・テロワール」発の「美食革命」が沸き起こることになります。
桃源郷を再び
英国人女性イザベラ・バードは明治11年外国人がまだ足を踏み入れたことのない東北地方を馬で縦断し、その時訪れた米沢地方について次のように記録しています。
「米沢平野は南に繁栄する米沢の町、北は人で賑わう赤湯温泉をひかえて、まったくのエデンの園だ。“鋤のかわりに鉛筆でかきならされた”ようで、米、綿、トウモロコシ、煙草、麻、藍、豆類、茄子、くるみ、瓜、胡瓜、柿、杏、柘榴が豊富に栽培されている。繁栄し、自信に満ち、田畑のすべてがそれを耕作する人々に属する稔り多きほほえみの地、アジアのアルカディアなのだ」。(イザベラ・バード『日本奥地紀行』)
TPPによって日本の農村、農業が潰されないうちに「スマート・テロワール」を日本の各地に展開し桃源郷と称されるような農村を復興しなければなりません。
「スマート・テロワール」が全国に100ヶ所ほども構築できれば、食料自給率の大幅改善と、GDPの2~3%ほどの押上げが可能になるでしょう。そして何よりもイザベラ・バードの見た逝きし日の農村の面影が現実のものとして蘇ることが期待できるのです。
日銀の消費者物価上昇率2%目標は即座に廃棄すべきだ
「DIAMOND ONLINE」で野口悠紀雄氏が興味深い論説を展開している。
http://diamond.jp/articles/-/84936
野口氏の論旨とそれをベースにさらに議論を展開すれば以下の通りとなる。
1.原油価格が14年央に100ドルから30ドルを割る水準にまで急速な低下をしている。この傾向は今後も長期的に継続すると予測される。
2.原油価格に象徴される資源価格の大幅な低下は資源の輸入価格の低下をもたらし、その効果は15年に13.2兆円の輸入価額の削減を実現した。
3.資源輸入価格の下落にもかかわらず消費者物価にそれが反省されない状況が15年には顕著になった。資源を原材料あるいはエネルギー源として利用する企業がコスト削減を価格引き下げに反映せずそのまま利益に計上したことが大きな要因だ。結果として15年に企業収益はこのコストダウンが大きく寄与して顕著に増大した。
そして企業のこの行動を後押ししているのが日銀および政府の物価上昇目標だ。
4.直近の円高は資源輸入価格の更なる押下げにつながる。これを企業が製品価格の引き下げに反映する行動に移れば、消費者物価の低下は顕著な形で現れるはずだ。
5.円高は輸入資源価格だけでなく輸入食品の価格の低下にもつながる。食料品自給率39%の現状は円高が食料品の輸入価格の低下につながり、それが食料品全般の価格低下をもたらすことは明らかだ。しかしここでもそのコストダウンを企業が製品価格に反映しないとすれば、消費者は恩恵を受けられない。
6.日銀および政府は消費者物価2%上昇目標を即刻廃棄し、輸入物価の下落を消費者物価の下落につなげるための旗振りを始めるべきだ。消費者物価が下がることで勤労世帯の可処分所得拡大をもたらし、消費支出は増加し、有効需要拡大が実現し、GDPの拡大が現実のものとなる。
7.企業は価格の引き下げを実行しても原材料価格のコストダウンと、価格効果による需要の拡大の好循環によって業績が向上し、実体経済の好調に基づく株価の上昇が期待できる。つまり円高でも企業業績は拡大し、株価は上昇するのだ。
8.またこの好循環は企業の設備投資、個人の住宅投資の資金需要を産み出し、結果として金利の上昇と、それによってここでも有効需要の拡大が実現する。
カリスマ会長は後継者を潰してしまった
セブン・アイ・ホールディングスの傘下にあるイトーヨーカドーの社長が突如交替した。
14年に社長就任したばかりの戸井氏が退任し、7年社長を務め、14年に戸井氏に引き継いだ亀井氏が社長に復帰した。
9日付け日経新聞朝刊によれば事の経緯は下記のとおりだ。
「『業績低迷の責任をとり辞任させていただきたい』。1月7日の午後、戸井氏はセブン&アイ本社9階にある鈴木敏文会長の執務室を訪れ、辞表を差し出した。突然の申し出に鈴木会長も慰留したが、戸井氏の辞意は固かったという。
ヨーカ堂は15年3~11月期に144億円の営業赤字となり(前年同期は25億円の赤字)、業績悪化に歯止めがかかっていない。日米のコンビニエンスストア事業が好調でグループとしては営業最高益となるなか、足を引っ張るヨーカドーへの風当たりは強まっていた。
『懸命にやってるのだろうが、成果に結びつかなければ惰性の仕事だ。ヨーカ堂は何も変わっていない』。戸井氏が辞表を出した前日の6日、ヨーカ堂の店長会議で鈴木会長は激しい言葉を飛ばした。戸井氏ら幹部は黙り込むしかなかった。
今回、取締役からも外れ、社長付となる戸井氏は営業畑の『エース』と呼ばれ、14年に社長に就任した。現場からの信頼も厚く、7年半続いた亀井政権から、周囲も納得する自然な交代だった。
売上高は毎年落ち込み、営業の強化は待ったなし。戸井氏は経営者として非情な決断を迫られた。15年9月には全店舗の2割にあたる40店を閉鎖する方針を決めた。これはヨーカ堂として過去最大規模の店舗閉鎖だ。並行して画一的な売り場づくりから脱却するため、店舗ごとに仕入れなどを任せる独立運営方式を導入するといった改革も急いだ」。
通常社長に就任して手腕のほどを本当に評価できるのは3年程度の時間が必要だ。まして戸井氏は昨年9月に経営業績の立て直しのための抜本策となる改革案を練り上げたばかりだ。
多分この回復策は第一歩でありこれに続いて次々に改革策が打ち出される手はずが調っていたに違いない。
しかもこうした改善策は当然のことながら鈴木会長に了解を受けていたはずだし、実行に移る前に、その成果を危ぶむということは最高経営責任者としてはあってはならないことだ。
全店長を前にして戸井氏の手腕に疑問を呈する発言は、鈴木氏としては役員社員に対する激を飛ばすくらいのつもりであったろうが、背水の陣を敷いていた戸井氏にとっては、役員社員を掌握するパワーを失うことにつながると判断したに違いない。
鈴木会長の後ろ盾を失って、孤立無援のままどうやって改革の指揮が取れるだろうかと考えた時に、深い喪失感にとらわれたはずだ。
厳しい状況にある部下を孤立無援の状況に置いた鈴木氏は、まさか戸井氏にかみつかれるとは思いもしなかった。いつもの調子で激を飛ばしたつもりでいたのだろう。
そもそも鈴木氏はイトーヨーカドーの経営基本方針を設定するCEOだ。そして石井氏はCEOの基本方針を実行するCOOの役割を担っていたはずだ。
したがってイトーヨーカドーの立て直しは会長と社長が一心同体で取り組むべき課題で、その一体感を役員社員に信じさせることができて初めて成り立つものであった。またその出来栄えが順調でないとしたら、CEOの経営基本方針(経営戦略)に瑕疵があることに思い至るべきなのだ。
仮に戸井氏の手腕が劣ると考えるのならばなおさら鈴木氏は戸井氏を支えなければならなかったということになる。
イトーヨーカドーの再建が進まない最大の要因は、セブン・イレブンを大成功に導いた鈴木氏にしても、セブン・イレブンの成功体験があまりに巨大であったがゆえにイトーヨーカドーの再建についてはついに的確な再建策を見いだしえなかったことにあるのではないだろうか。
とすれば亀井氏が復帰しても業績の衰退は加速するだろうし、いずれは外国人アクティビストが指摘するように売却することを余儀なくされるにちがいない。
あなたが経営する(所属する)組織の経営戦略の品質を測ってみませんか?
株式会社中田康雄事務所は経営戦略の品質評価のメソッドを開発しました
そしてこのメソッドを使ってあなたの経営する(所属する)組織の経営戦略の品質を測定するサービスを本日から開始しました
戦略評価の手順は至ってシンプルです
下記に添付しましたシートに記入していただいたうえで、これら二枚のシートを添付して㈱中田康雄事務所宛にメールしてください
1週間以内に戦略の品質を100点満点で何点になるかを測定してお返しいたします
生まれ変わったら入りたい会社
週刊現代の編集部から以下のアンケートが届きました。
「これまでのご経験から、「あの会社は素晴らしいな」「
そこで次のように回答しました。
①生まれ変わったら入ってみたい会社名:株式会社オリエンタルランド
②その理由: 顧客満足および従業員満足を徹底して同時追求している
多くの会社を見てきた、多くの会社と接してきた皆様だからこそわかるその会社の「雰囲気」「社風」「制度や働き方」「職場の空気感」「業界での見られ方」「実際の仕事のダイナミズム」など、その会社を特徴づけるエピソードを可能な限りまじえていただけると幸いです。
東日本大震災が発生した日に東京ディズニーランドおよびシーには7万人のゲストが来園していました。これだけの人がいささかもパニックを起こさず安心して地震の収まるのを静かに待ったのは見事と言うほかありません。
稼働していたアトラクションも安全に停止し、途中でゲストが孤立する事故も一切ありませんでした。
地震の起きた瞬間にキャストがゲストのために取った行動は標準動作をベースにしながらもそれぞれが臨機応変の対応を行い、その結果顧客接点で無数の感動を誘いました。
また当日はアクセスが大きく乱れ2万人のゲストが当地で仮眠しました。そこでも心のこもった対応でゲストをもてなし、翌日混乱が収まったところでゲストは安心して家路につくことができました。
こうした見事な対応は震度6、来場者10万人を想定した訓練を年間180日実施していることによって可能になったと言えます。でもそれだけでこれほどの感動を産み出せるわけはありません。訓練だけでなく日頃のゲストに夢と楽しさを提供することが何にもまして重要だという共通の意識が約2万人にも達するキャスト全員にしっかり植えつけられていたことが、ゲストの期待を大きく超えた無数の感動を呼び起こしたのでした。
年間3000万人の来場者でにぎわう秘密はこのエピソードによってうかがい知ることができます。
ディズニーランドとシーは2015年から10年間で5000億円の設備投資を計画しています。これまでも年間300億円から400億円を投資してアトラクションの新設やリニューアルを繰り返し実行してきました。これがいつ訪れても新鮮なエンターテインメントを楽しむことを可能にし。多くのゲストのリピート来場を実現する成功要因になっているのです。
この裏には緻密に計算された財務戦略があります。顧客満足を継続的に拡張していくために、最重要な打ち手を創出し、それらを実現するために投資はいかほどなされなければならないかを算定し、そのための資金源泉を見通すという、財務計画の王道とも言うべきプロセスが踏まれています。
資金源泉の主役は主に営業利益と減価償却費から構成される営業キャッシュです。10年間に5000億円の投資を実行することは毎年1000億円もの営業キャッシュを産み出している同社にとって実現可能性は極めて高いということができます。
そしてディズニーランドではアトラクションが年中無休で正確にそして安全第一で稼働することが決定的に重要なことになります。
それには設備の保守や運転に携わる腕の良い裏方の存在が不可欠です。顧客接点で活躍するキャストに加えて、キャストのパフォーマンスを最大限引き出す裏方の技術力がコラボレーションしてはじめてゲストの感動をうみだす構造になっているのです。こうした構造もオリエンタルランドのエクセレンスの秘密であるといえましょう。
読書ノート:デービッド・アトキンソン著『イギリス人アナリストだからわかった日本の「強み」「弱み」』(講談社+α選書)
「日本は経済力が強くて住みやすい」はほんとうか?
日本について他国と比較して、「安全だ」、「勤勉だ」、「技術力が高い」、「おもてなしが上手だ」、「住みやすい」などの点で自慢したり、自信を持ったりする日本人が多い。
しかし著者はそれらの他国に対する「強み」は、事実ベースで証拠が明確にあげられてはおらず、概して一方的な思い込みに過ぎないことが多いと説く。
例えばIMFの統計に表れた購買力平価でみた人口一人当たりGDP(US$)のランキングを見ていただきたい。
1.カタール 143,432
2.ルクセンブルグ 92,049
3.シンガポール 82.762
9.スイス 58,087
10.香港 54,722
11.米国 54,597
15.オランダ 47,355
16.オーストラリア 46,433
17.オーストリア 46,420
18.スウエーデン 45,986
19.ドイツ 45,888
20.台湾 45,854
21.カナダ 44,843
22.デンマーク 44,343
24.ベルギー 42,973
25.フランス 40,375
28.英国 39,511
29.日本 37,390
この数字は国民一人あたりの生産性を表現していると考えることができる。なんと日本は29位にあまんじている。
残業をもいとわず良く働く、勤勉な日本人ではあるのだが、仕事の効率からみると米国に比較して70%の水準にしかすぎないのだ。台湾に比較しても80%の水準なのだ。
つまりは日本人の働き方にはかなりムダが多いということになる。
日本の経済力の強さにしても、技術力や資本蓄積力が突出しているからではなく、単純に人口が多いからだといえなくもない。
こう考えると、「日本が住みやすい」ということも、事実ベースでは割り引いてみなければならないと思われてくる。
なぜ日本人の仕事の効率は低いのか?
日本人の働き方の効率の悪さは何にゆらいするのだろうか?
著者はいくつかの原因を上げている。
一つには会議がやたらに長いことが挙げられる。関係者のコンセンサスを十分に取らなくてはならないという思い込みが長い会議の原因ということだ。
二つ目に挙げられている原因は「完ぺき主義」だ。ほとんどの事柄は90%の品質で十分なのに、100%を目指そうという完ぺき主義がはびこっている。
90%で納得せずに残りの10%を追い詰めていくと、それまでに要した以上の時間がかかってしまう。しかも100%で手に入れた品質は90%で達したものとさほど変わらなかったりする。
三つ目にあげられる原因は数字で判断しないことだ。ほとんどの事実は数字やデータで確認することができる。しかし日本では数字によらず勘や経験や思い込みで判断が下されることが多い、と智者は言う。
これらの原因にも増して効率の悪さをもたらす重要な要因として「面倒くい」ことを著者はあげている。
「日本の『効率が良くない』というものの問題を辿っていくと、かなりの部分はこの『面倒くさい』という言葉に帰結する感じがします」
「面倒くさい」とはどういうことか?
何らかの問題や課題を解決しようとするときに、「ゼロベースで考える」とか「根源的な解決策を考える」ことが求められるはずです。しかし日本では、根本的な可決策を考えたり、ましてやそれを実行するとなると、とても「面倒な」事態になるというのが著者の考えだ。
どういうことなのか?
日本では、現状維持こそが波風が立たず、全員にとって居心地の良い状態と言える。そこにあえて波風を立てて、しかも有力者や上司の感情を害することまでして、かいぜんや改革を行うことは許されないことになるわけだ。
根本的な解決をゼロベースで実行するようなことを提案しようものなら、とてもではないが「面倒」なことになるわけだ。
だから誰もそのような面倒なことにならないように、仲間の調和を崩さないように、慎重に振る舞うことが求められるということなのだ。
ということで「面倒くさいことはしない」ということが日本の組織人の行動原理になったということだ。
この代償として日本は困難な問題を抜本的に解決する能力を失うことになってしまったということだ。
日本の強みは?
日本の強みも指摘してくれている。強みは「加える」こと。つまりは「新しいものを取り入れつつも古いものを残していく」ということだ。
日本では古代から新しい勢力は古いものを根絶やしにせず、古いものを残しながら、あるいは古いモノのを土台としてその上に新しい勢力を確立してきた。このことはヤマト王朝が出雲の国を制服するのではなく、出雲を包摂しつつ国造りをしたことまで遡るわけだ。
さらには、武家政権が実質的に権力を握った鎌倉時代以降も天皇制が連綿として残るのもそのことを良く象徴している。
観光が日本再生の切り札として位置づけた時に、この「古いものが残っている」ことが、世界に類を見ない日本の優位性を保証するものになるということだ。
強みと弱みは結び合っている?
このように見てくると著者が言う日本の強みと弱みは分かちがたく結び合っているようにも見えてくる。波風が立つのを嫌う風土は、古いものを否定せず、残しながら新しいものと結合させることを得意としてきたからだ。
こうした風土において改革は抜本的に行われることはなく、関係者が全員納得のゆく、微温的なものとして実現するしかないということを意味しているのかもしれない。
読書ノート:小熊英二著『生きて帰ってきた男』(岩波新書)
本書は戦後70年の日本の現代史をそれぞれが自分史として振り返るための良いきっかけを作ってくれる好著だ。
慶應義塾大学総合政策学部教授で社会学者の小熊英二氏(1962年生まれ)が父謙二氏(1925年生まれ)の生涯を、謙二氏への聞き取をもとに生活者の個人史としてまとめたものだ。
本書は単なる聞き書きではない。聞き出した事実を巡ってその時々の客観的な社会、経済、政治状況をも掘り起し、謙二氏の体験がその当時の社会状況の中でどのように位置づけられるかについても考察が加えられているという意味で、個人史による20世紀の日本現代史の再構築の作業が丹念に行われているといえる。
謙二氏は東京で育ち、早稲田実業中学を卒業したいわゆるエリートには属さない市井の生活者だ。吉本隆明の言葉を借りれば「大衆の原像」をそのまま生きたといえる人物だ。
謙二氏は1944年19歳で召集され、満州に送られ、終戦時にソ連軍によって捕虜となり、そのままシベリヤに抑留され、3年間強制労働に就いて、零下30度の極寒と飢えで、それこそ死と隣り合わせの極限生活を強いられた。
このシベリヤ抑留を経験し、そこから生きて「帰った」経験がその後の生活者としての原点であることから本書の題名が決まったと考えられる。
謙二氏は帰国後結核に感染し、1951年に結核療養所に入所した。ストレプトマイシンなどの抗生物質が登場する直前の時期で、治癒する見込みもなく、しかも治癒しなければ出所できないという意味で、いつかは帰国できるという希望を持てたシベリヤ抑留よりもはるかに希望の持てない状況が続くことになった。
幸いなことにストレプトマイシンが治療に使われることになり、療養所生活は5年で幕を閉じることになった。
出所しても青春の20歳代をシベリヤと療養所で過ごした謙二氏には定職に就くことは困難で、いくつもの最底辺の職を転々とせざるを得なかった。
しかし日本が高度成長経済期に入るとともに、社会全体が浮揚し始め、そのチャンスをうまくつかんで、謙二氏の生活も浮揚し始めることになる。
ところで終戦後、日本の戦争を指導した将校や高級官僚がのうのうと生き延びて恩給をもらってよい暮らしを続けているのとは対照的に、大衆は戦争によって死と隣り合わせの悲惨な被害を受け、やっとそれを切り抜けたと思う間もなく、戦後はなけなしの金融資産を超インフレで喪失し、飢えに苦しむ過酷な現実に直面した。
謙二氏も例外ではなかった。終戦後はゼロからの出発だった。
常に悲惨な状況に大いなる力によって強制的に陥れられる存在であることへの憤りを感じつつも、それに言挙げすることなく諦念とともに飲み込む謙二氏の姿に大衆の原像を見る思いがする。
謙二氏は喜怒哀楽の表現を表だってする人物ではなかった。身に起きる、不安も恐怖も歓喜も絶望も怒りもある意味で淡々とした表情でやり過ごした。
しかし東条英機や昭和天皇にまつわる思いはさすがに重い感情を込めて語られている。
終戦時に東条英機が自殺未遂で巣鴨に拘置されたとき、謙二は「生きて虜囚の辱めを受けるなと訓示した東条が自殺に失敗し、占領軍に捉えられたと聞いて激しい憤りにかられた」と話している。
また昭和天皇に対しても開戦の詔勅を発布し、結果として国民を塗炭の苦しみに陥れた責任を全うしていないことに、憤りを感じている。謙二氏は「終戦とともに天皇は退位すべきであったとの思いを禁じ得なった」と語っている。
少なくとも天皇は終戦時に、日本国民に対し、また軍事力によって侵略し交戦した諸国民に対して、心からの反省とお詫びをするべきであった。
そして終戦記念日には毎年同様の反省とお詫びを飽くことなく繰り返していれば、天皇の戦争責任は全うされたはずだ。
そしてなによりアジア諸国民からの日本に対する疑念を完全に払しょくすることになったと思われる。
以上の意味で本書は戦後70年の日本の現代史をそれぞれが自分史として振り返るための良いきっかけを作ってくれる好著だ。
読書ノート:野中郁次郎著『史上最大の決断』(ダイヤモンド社刊
1944年6月6日、計画から2年2ヶ月を要し、300万人の将兵を投入した、市場最大のノルマンディー上陸作戦が始まった。
本書はノルマンディー上陸作戦がどのようにして決断され、実現に向けてどのような組織つくりが行われたのか、そしてノルマンディー上陸からベルリン陥落に至る作戦がどのように実行されたのかを独特の切り口で分析する。
その独特さは歴史の中で人間が多くの選択肢の中から一つを選んで下された決断が、その後の歴史を大きく決定してしまう分岐点になることがあり、その分岐点を拠り所に歴史を追体験するという方法論に見ることができる。
連合軍の勝利を決定付けた分岐点
「冷戦研究の泰斗ジョン・L・ギャディスによると、歴史を複雑系として捉える場合、絶対的な因果関係ではなく、偶発的な因果関係の連鎖に対する洞察が重要となる。だからこそ、歴史家は事象のモデル化よりシミュレーションを好む。人間は多くの可能性の中から決して後戻りのできない一つの分岐点を選び、歴史を創っていく。それが小さな選択のように見えたとしても、その後の歴史は多数の原因とそれらが交わるその分岐点を境に大きく変わっていくことがまれではない。ノルマンディー上陸作戦においても、そうした不可逆的なターニングポイントがいくつもあった。
-
間接戦略を否定して直接戦略を選択する
-
「6月6日にノルマンディー上陸」という決断を下す
-
戦略爆撃目標をフランス国内の輸送機関とする
-
機動力を組織化する
-
消耗戦と機動戦を総合する」
アイゼンハワーのリーダーシップ
しかし本書の魅力はこの複雑な歴史的プロセスの分析もさることながら、この作戦を勝利に導いた最高司令官アイゼンハワーのリーダーシップの解明にある。
「士官学校時代はフットボールとポーカーに明け暮れ、入隊後も戦場とは長らく無縁で、大佐で退役し、後は悠々自適の人生を送りたい、と思っていた平凡な男に、われこそは人類共通の敵を倒す十字軍の頭領たらん、という共通善を志向する志を与えたのである」。
なぜ凡人であったアイゼンハワーが非凡人に変身したのか、彼はなぜ史上最大の作戦のリーダーとして歴史に名を留めるに至ったのか。
平凡人アイゼンハワーはいかにして非凡人に変わったのか
アイクが非凡人化した要因を筆者は次のように解明する。
-
職人道を真摯に追求、実践したこと
-
複数のすぐれたメンターに恵まれたこと
陸軍きっての教養人であるコナー、カリスマの手本そのものだったマッカーサー、参謀の鏡としてのマーシャル
-
類まれな文脈力を身につけたこと
文脈力は文脈の察知、返還、創造に関わる知の作法である。見えないものを見、一見関係なさそうなもの同士の間に道筋をつけるパターン認識の文脈力こそ、あらゆる職業に必要な至高の能力であるとわれわれは考える。アイゼンハワーの文脈創造力は、現状に満足せず高みに向かって努力する職人道の実践、師から受け継いだ優れた実践知、師の一人であるコナーが伝授した物事の関係性にたいする洞察を深めるリベラルアーツの知識、そしていくつかの戦場経験によって培われたのではないだろうか。実践理性の方法論は、演繹よりは帰納、さらには仮説推論と言える。
-
アメリカ陸軍という伸び盛りの組織に属していたこと
39年9月、ルーズベルトは熟慮の末、マーシャルを新参謀総長に抜擢した。マーシャルは日独伊三国同盟に対抗すべく、陸軍の拡大と近代化を決定し、時代遅れとなった老将校団のリストラを断行した。アイゼンハワーやパットンは上の世代が一掃され、いわば重しが取れたおかげで、活躍の舞台を与えられたのである。
アイゼンハワーのリーダーシップはいかにして可能になったのか
続いて問いかけるべきは、こうして非凡人化したアイゼンハワーの類稀なリーダーシップは何によって可能になったのだろうかという疑問だ。
著者によるとリーダーシップの本質は「実践知」にあるとされる。
「リーダーシップの本質は理想主義と現実主義、それらの不断の緊張関係の上に進展する動的均衡プロセスにある。しかも両者のバランスは静態的な分析によってではなく、弁証法による動態的な総合という危うい実践知によって担保される」。
そしてこの実践知は実践と知性を総合する賢人の備える智慧だ。
「フロネシス、すなわち実践知は実践理性という訳語もあるように、実践と知性を総合するバランス感覚を兼ね備えた賢人の智慧である。利益の極大化や敵の殲滅という単純なものだけではなく、多くの人々が共感できる善い目的を掲げ、個々の文脈や関係性の只中で、最適かつ最善の決断を下すことができ、目的に向かって自らもまい進する人物(プロニモス)が備えた能力のことだ。予測が困難で、不確実なカオス状況の中でこそ真価を発揮し、新たな知や革新を持続的に生み出す未来創造的なリーダーシップに不可欠な能力でもある」。
実践知リーダーの備える能力とは
また著者は実践知リーダーは次の6つの能力を備えていると考える。
-
善い目的をつくる能力
-
ありのままの現実を直観する能力
-
場をタイムリーにつくる能力
言葉の意味は文中での位置や他の言葉との関係性によって確定する。一方で人は非言語的な暗黙知も、身体的な共振、共感、共鳴によって察知する。人はそうした現実や他社とのダイナミックな関係性の只中に生きている。人と人、人と物事、物事と物事、部分と全体、それらの関係性を察知し、新たな関係性を保管したり、転換したり、創発させたりする力を「文脈力(Contextualizing Capacity)と呼びたい。
それまでの自己を超えたところに真理を発見する観察はその場に棲み込んで初めて可能となるが、他者や環境に同質化してしまうと全体像を見失ってしまう。その場に棲み込むことと、物事をあるがままに見ることの両立、つまり主観を差し挟まず、相手の視点に立つことと、そうした自分を相対化することの双方を同時に行わなければならない。場からせり出してくる情報を無心に浴びて自らの暗黙知を豊かにするとともに、他者の心中でなにが起こっているかを予測し、その意味を総合的に解釈する。こうした働きを適時かつ適切に行える人が文脈力ある人だ。
アイゼンハワーはこの文脈力に恵まれていた。しかも常時、磨いていた。その力を育んだのは、ポーカーやブリッジといったカードゲームであった。しかも、カードプレイヤーとしても軍司令官としてもフェイントの達人だった。他人の心の中を分析し、それぞれがどんなオプションを持っているのか、それらのオプションは本人以外の他人にも知られてしまった場合、どう行動したら勝つことができるかを予測できる才能を持っていた。
-
直観の本質を物語る能力
-
物語を実現する能力(政治力)
リーダーシップはある人の持つパワーや影響力に関連して定義することができる。それを「目標達成に向けて人々に影響を及ぼすプロセス」と広く定義すると、人間が持つ社会的パワーの基盤は次の6つの力で構成される。
-
合法力(組織から公的の与えられた権限に由来する力)
-
報償力(報酬を与える能力に由来する力)
-
強制力(処罰する能力に由来する力)
-
専門力(専門的知識や技能に由来する力)
-
親和力(互いの一体感に由来する力)
-
情報力(情報の量や質に由来する力)
このうち、もっとも人間を強く拘束するのが親和力だ。親和力とは、人が他社、集団、規制、役割などに同一性(一体感)を認めた時に拘束される力である。別名「愛による統制」といってもよい。親和力に基づく統制は、人を最も強く、深く統制するが、一体感に基づいたものなので「意識されない自己統制」となる。アイゼンハワーのパワーマネジメントの本質はまさにこの親和力にあった。「この人のためなら死ねる」
-
実践知を組織する能力
アイゼンハワーは自分ですべてを囲い込もうとせず、各組織にいるすぐれた人材をうまく使った。それはアメリカ軍の組織がドイツ軍はもとより、味方のイギリス軍よりも自律分散型、すなわちフルクタル性が高かったことも影響していた。
歴史にあえてifを持ち込む
歴史にifを持ち込むことは禁じ手とされている。しかし著者はifをあえて考察することで、歴史上の人物が下した意思決定のプロセスやその決定の意味をより鋭く際立たせる効能があると説いている。
「歴史を通じて未来の物語をつくるために有益なことがある。歴史上の出来事に関して、他にどんな可能性があったのかを検討してみるのだ。歴史は単なる過去の記録ではなく、未来創造のための意味ないしは教訓を引き出す格好の題材である。そのためには史実の背後にある関係性ないし文脈の洞察が不可欠になる。意味は関係性の中から生成されるからである。
洞察を働かせるためによい方法がある。歴史に、通常は禁物と言われるif(もしこうだったら・・・)をあえて持ち込み、史実に基づくシミュレーションを行ってみるのだ。そうした過程を通じて、我々は当時の人々が下した決断のプロセスをより深く理解することができる。そこから多大な教訓が得られるのだ」。
もしノルマンディー上陸作戦が一年早く実現していたら
著者はノルマンディー上陸作戦に関して、二つのifを持ち込んで検証している。
一つは上陸作戦が1944年ではなく43年に行われていたら。というifだ。
「戦死研究科のハロルド・C・ドイッチェらが詳細にこれを論じている。
それによると、43年の時点で、連合軍は大陸侵攻を実行するだけの戦力を十分に持っていた。特に侵攻戦力の中心を担ったアメリカ陸軍は43年までにその戦力が頂点に達しており、それ以降は海兵2個師団が追加されただけだった」
「もし43年に上陸作戦が行われていたら、戦争の最後の1年間で殺されたユダヤ人200万人の命も助かっただろうし、東ヨーロッパをソ連に明け渡すこともなかった。彼らのIFが正しいとすると、ノルマンディー上陸作戦の敢行を渋り、ワニの腹から攻める間接戦略にこだわったチャーチルは判断ミスを犯していたことになる」。
もしヒトラーがソ連に向かわずスエズ運河の制圧を優先していたら
第2は、ヒトラーの戦略に関するifである。
「40年のフランス崩壊後、イギリスはエジプトとスエズ運河を機甲1個師団のみで防衛していた。一方のドイツは北アフリカに未使用の装甲40個師団を要していたので、エジプトとスエズ運河をやすやすと占領できた可能性が高い。その結果フランス支配下の北アフリカ(モロッコ、アルジェリア、チュニジア)は枢軸軍に占領されてしまい、イギリスは地中海の放棄を余儀なくされる。そうなると、地中海に面したギリシャ、そして隣のユーゴスラビアはドイツとの和平交渉を始めざるを得ない。ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアはドイツの味方である枢軸国だったので、ドイツは一兵も出すことなく、東及び南ヨーロッパを支配することができた、というのだ。
しかもスエズ運河を占領できると、ドイツ軍がシリア、アラビア半島、イラク、イランを蹂躙し、戦争遂行に不可欠な石油を無尽蔵に入手できる。そしてアラブ地域とイランの占領によって、ドイツは3つの「天恵」を手に入れる。まずは中立国のトルコが孤立する。さらにイギリスのインド支配に脅威を与える。コーカサスとカスピ海沿岸にわたるソ連の油田地帯をドイツ軍の火砲と戦車の射程内に収めることができる。
結果、トルコは連合軍に加わるかドイツ軍に国土の通過を認めるかの選択を迫られ、イギリスはインド防衛に専心せねばならず、ソ連はドイツとの和平の継続を余儀なくされる。東部戦線におけるソ連の戦力増強を当てにできなくなれば、アメリカは地中海における大規模な水陸両用作戦を遂行できなくなる。さらにアメリカは太平洋地域で増大する日本軍をも迎え撃たなければならない・・・・。
ヒトラーがソ連の主面を攻める直接戦略ではなく、北アフリカ侵攻という間接戦略を採った場合、第二次世界大戦の結果はこうも変わった可能性がある」。
もし日本が真珠湾ではなくウラジオストックに侵攻していたら
第三のIFは日本の例だ。
「アメリカの軍人アルバート・C・ウエディアミヤーは、第二次世界大戦において日本は「太平洋でアメリカとことを構える」という大きな戦略的錯誤を犯したと述べる。ではどうすべきだったかというと、ソ連の沿海州、例えば東部シベリヤの要衝地ウラジオストックに攻撃を加えるべきだったと主張する。結果はどうなるか。
ソ連は東部シベリヤに大兵力をとどめ置かねばならず、結局、西からはドイツ、東からは日本と、二正面作戦を余儀なくされる。それによって日本の同盟国ドイツが大いに助けられ、モスクワは陥落、スターリングラードも同じ運命をたどったろう。そのドイツ軍がさらにコーカサスの占領まで成功させたら、ドイツはさらに長期にわたって戦争を継続することができた。「形勢悪し」とみるアメリカの参戦はもっと遅れ少なくとも枢軸側は戦争を手詰まり状態に持ち込むことが可能だったかもしれないと述べている
リーダーの決断がその後の歴史を創っていることが実感できるのである」。
もし日本がポツダム宣言を7月26日に受諾していたら
ここで著者に刺激されて、日本の終戦の決断を巡るifを考えてみたい。
日本の無条件降伏がポツダム宣言を受諾した45年8月14日ではなく、ポツダム宣言が発せられた7月26日、あるいは沖縄戦が終了した6月20日、さらに遡ってドイツが無条件降伏した5月8日に行われていたとすればというifだ。
日本の降伏が早期に行われていたなら、8月6日の広島、8日の長崎への原爆投下は行われず、20万人を超える市民の虐殺も避けられたことになる。
また8月9日のソ連の参戦も回避され、それに続く70万人にも上る日本兵捕虜のシベリア抑留も避けられていたことになる。
日本の降伏の意思決定はまさにリーダー不在の無責任体制の中で延々と続いた小田原評定の末、最悪のタイミングで漸く行われるに至った。
今年の終戦記念日には終戦を巡るifをあたうかぎりの想像力を駆使して構想して、日本人のリーダーシップの欠陥について考えを深めてみたい。
読書ノート:エマニュエル・トッド著『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる』(文春新書)
世界の見方が大きく変わる!
本書は読了後に世界の見方が大きく変わる。そんな強烈な読書体験をさせてくれる刺激的な著書だ。
筆者はオランド大統領よりもはるかに左に位置するフランスの社会民主主義者であり、フランス人特有のドイツに対する根深い確執を、普通のフランス人よりも過剰に意識していることを割り引いても、国際情勢の把握についてはかなりの説得力を持って語っていると思われる。
では世界の見方はどう変わるのか?
要約すればヨーロッパはすでにドイツによって強力な支配構造が構築され、盟主であるドイツはアメリカに対抗するまでの経済的、政治的に支配的地位を獲得するに至った。
その地位はフランスさえもドイツの隷属国に成り下がってしまったという事実によって大きなインパクトを人びとに与える。
このドイツの支配的な位置の強靭さを筆者は次のような例え話で説得する。
「今日、政治的不平等はアメリカシステムの中でよりも、ドイツシステムの中での方が明らかに大きい。ギリシャ人やその他の国民は、ドイツ連邦議会の選挙では投票できない。一方、アメリカの黒人やラテン系市民は、大統領選挙および連邦議会選挙で投票できる。ヨーロッパ議会は見せかけだけだ。アメリカ連邦議会はそんなことはない」。
そのアメリカは冷戦以後もロシアのすでに幻想でしかない脅威に気を取られ過ぎて、ユーロ圏成立以後に形成されたヨーロッパにおけるドイツへの権力移行を見過ごすことになった。
ロシアはその見かけの強圧的な態度とは裏腹に、内部に抱える経済的な危機の克服に専念せざるを得ないという状況から、世界に対していかなる強圧的な実力行使をする余力をもはや持ちえない。
「ドイツ帝国」の興隆はどのようにして可能になったのか?
ドイツはどうやってこうした圧倒的なポジションを気付いたのだろうか。著者の説明はこうだ。
「ドイツはグローバリゼーションに対して特殊なやり方で適応しました。部品製造を部分的にユーロ圏の外の東ヨーロッパへ移転して、非常に安い労働力を利用したのです。
国内では競争的なディスインフレ政策を取り、給与総額を抑制しました。ドイツの平均給与はこの10年で4.2%低下したのですよ。
ドイツはこうして、中国――この国は給与水準が20倍も低く、この国との関係におけるドイツの貿易赤字はフランスのそれと同程度で2000万ユーロ前後です――に対してではなく、社会文化的要因故に賃金抑制策等考えられないユーロ圏の他の国々に対して、競争上有利な立場を獲得しました」。
「最近のドイツのパワーは、かつて共産主義だった国々の住民を資本主義の中の労働力とすることで形成された。これはおそらくドイツ人自身も十分に自覚していないことで、その点に、もしかすると彼らの真の脆さがあるかもしれない。
つまり、ドイツ経済のダイナミズムは単にドイツだけのものではないということだ。ライン川の向こうの我らが隣人たちの成功は、部分的に、かつての共産主義諸国がたいへん教育熱心だったという事実に由来している。共産主義諸国が崩壊後に残したのは、時代遅れになった産業システムだけではなく、教育レベルの高い住民たちであったのだ
いずれにせよ、ドイツはロシアに取って代わって東ヨーロッパを支配する国となったのであり、そのことから力を得るのに成功した」。
つまり冷戦後ドイツは東ヨーロッパを低コストで高品質の労働力市場として活用し、同時に自国の労働者の賃金の上昇を抑制し、ユーロ圏諸国に工業製品を洪水のように輸出し、結果として、ヨーロッパの経済的な盟主としての地位を獲得し、同時にこの経済力を背景にEUにおける政治的な支配力を着々と強力なものにしていったということだ。
そして今やヨーロッパに対する「ドイツ帝国」の版図は著者によれば次のような広大な形を成すに至ったのだ。
「ドイツ圏:ベネルクス、オーストリア、チェコ、スロベニア、クロアチア
自主的隷属:フランス
ロシア嫌いの衛星国:ポーランド、スウエーデン、フィンランド、バルト三国
事実上の被支配:その他のEU諸国
離脱途上:イギリス
併合途上:ウクライナ」
ウクライナ危機をどう理解するか?
ドイツのヨーロッパにおける圧倒的なパワーの形成という情勢分析のもとで、ウクライナ危機はどのように理解できるだろうか。
「ウクライナ危機がどのように決着するかは分かっていない。しかし、ウクライナ危機以後に身を置いてみる努力が必要だ。もっとも興味深いのは『西側』の勝利が生み出すものを想像してみることである。そうすると、われわれは驚くべき事態に立ち至る。
もしロシアが崩れたら、あるいは譲歩しただけでも、ウクライナまで拡がるドイツシステムとアメリカとの間の人口と産業の上での力の不均衡が拡大して、おそらく西洋世界の重心の大きな変更に、そしてアメリカシステムの崩壊に行き着くだろう。アメリカが最も恐れなければいけないのは今日、ロシアの崩壊なのである」。
さらに注目すべきはドイツが急速に中国に接近していることだ。メルケル首相が繰り返し中国訪問を実行したにもかかわらず、今年になってはじめて日本への訪問をしたということが、ドイツの中国への接近を何よりも良く物語る。
80年前に遡ると、ドイツの中国接近は初めてのことではないことに気付かされる。
「果たしてワシントンの連中は覚えているだろうか。1930年代のドイツが、長い間、中国との同盟か日本との同盟かで迷い、ヒトラーは蒋介石に軍備を与え彼の軍隊を育成し始めたことがあったということを。NATOの東ヨーロッパへの拡大は結局ブレジンスキーの悪夢のバージョンBを実現する可能性がある。つまり、アメリカに依存しない形でのユーラシア大陸の再統一である」。
アメリカのパワーの弱体化とドイツの興隆は世界に新しい緊張を強いることが予想される。
「従ってこれからの20年間は、東西の紛争とは全く異なるものに直面しなければならないのだ。ドイツシステムの擡頭は、アメリカとドイツの間に紛争が起こることを示唆している。これは力と支配の関係に基づく内在的なロジックである。私の考えでは、未来に平和的な協調関係を創造するのは非現実的だ」。
「アメリカのパワーの後退は本当に憂慮されるほどになってきています。イラク第二の都市モスルがジハード勢力(イスラム国の前身、ISIS)に奪われたのち、ワシントンは衝撃から立ち直れていません。世界の安定性はしたがって、アメリカのパワーだけに依存するわけにはいかないのです。
ここで私は、意外だと思われそうな仮説を呈示します。ヨーロッパは不安定化し、硬直すると同時に冒険的になっています。
中国はおそらく経済成長の瓦解と大きな危機の寸前に居ます。ロシアは一つの大きな現状維持勢力です。アメリカとロシアとの新たなパートナーシップこそ、我々人類が『世界的無秩序』の中に沈没するという、現実となる可能性が日々増大する事態を回避するための鍵だろうと思います」。
ギリシャ問題の真因は?
こうした理解の上に立つと、ギリシャ危機も違った景色で現れる。
「ユーロのせいで、スペイン、フランス、イタリアその他のEU諸国は平価切下げを構造的に妨げられ、ユーロ圏はドイツからの輸出だけが一方的に伸びる空間になりました。こうしてユーロ創設以来、ドイツとそのパートナー国々との間の貿易不均衡が顕著化してきたのです。
よく吹聴されていることに反して、ヨーロッパのリアルな問題は、ユーロ圏内部の貿易赤字です。貿易赤字を遠因とする現象に過ぎない歳出超過予算ではないのです」。
「『財政のゴールデン・ルール』と呼ばれている概念は、人間活動のうちの一つの要素をいわば、『歴史の外/問題の外』に置いてしまおうとするもので、本質的に病的だといわなければなりません。それなのに、フランスの指導者たちはこの病理を助長し、励まし、ドイツの権威主義的文化をそれがもともと持っている危険な傾斜の方へ後押ししたのです」。
ギリシャのみならず財政危機に見舞われている南欧諸国も含めて、危機の原因はドイツの独り勝ちともいうべき貿易不均衡なのであって、EU諸国がユーロ・システムを導入した時点からその要因を抱えざるを得なかったのだ、と言うことになる。
筆者の解決策はユーロ・システムの解体に他ならない。
日本は何をなすべきか?
以上のような国際情勢の分析に立って、さてそれでは日本はどのようにこの大きな変化に対応していけばよいのだろうか?
ドイツ経済界は現在大きなイノベーションの実現に官民一体となって取り組んでいる。インダストリー4.0がまさしくそれだ。
ドイツが主導するインダストリー4.0は、いわゆるIoTのプラットフォームである、標準化したカンバンにより世界中の製造業が繋がるという、開かれたカンバン・システムを目指している。
日本も遅ればせながらIoTのコンソーシアムを民官学の連携で立ち上げてドイツに遅れ時とばかり走り始めたところだ。
しかし日本は独自のプラットホームをゼロベースでしかも先行するドイツに回周遅れで創造するのではなく、むしろドイツと協働して世界標準創りに参加すればいい。まさしくIoTの進化を目指すという局面での日独同盟の復活だ。
もちろん戦前のファッシズムの再来ではない。むしろ世界標準のプラットフォームを創造することで世界の産業界に効率化の基盤を提供することになる。つまりは日独だけでなく世界中の知を積極的に受け入れて、いかなる国も差別することなくこの成果を開放することで、世界中の産業効率化に貢献することになるわけだ。
少なくともこの日独同盟によってアメリカ主導のネット社会にくさびを打ち込み、アメリカ、ロシア、中国などの覇権国家に対抗することによって、よりフラットな世界システムの構築に大きな足掛かりを創ることになるに違いない。
安全保障関連法案の衆院通過に思う
憲法第9条の全文
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
憲法第9条の全文を素直に読めば、集団的自衛権や海外派兵は憲法違反に該当することは疑いをはさむ余地はない。
国際紛争を解決する手段として戦略を持たないのであるから、自衛隊を海外に派兵した時点で、自衛隊そのものは憲法に違反する存在になることが明白だ。
そもそも日本の現時点での喫緊の安全保障上の最重要課題は以下の二つしかない。
1.地震、津波、台風などの自然災害への備えが十分ではない
2.食料の自給率が40%を割っていること
自然災害への対応
東日本大震災を契機として日本全体の火山活動が活発になっている。同時に首都直下型地震、東海地震、南海地震のリスクも高まっていると推測されている。
例えば首都直下型大地震が発生したときの被害状況は考えるだけでもおぞましい惨状が目に浮かぶ。死者1.1万人、倒壊火災家屋85万軒、被災者数1000万人、被害総額112兆円が予想されている。
M8クラスの東海メガ地震でも、死者1万人、倒壊火災家屋30万軒、被害総額30兆円が想定されている。
また東海巨大地震は南海メガ地震を誘発する可能性が高く、この場合の被害はそれこそ計り知れない。
歴史をたどると1707年には駿河湾を震源とするM8クラスの宝永大地震が発生し、しかも直後に富士山が噴火し、降灰による被害も重なった。
1770年代には岩木山、浅間山が大噴火し降灰とそれによる悪天候は農産物に壊滅的な打撃を与え、天明の大飢饉につながった。
大地震と大噴火はそれこそ地続きの自然災害として連動しているように見える。
このような地震、津波、噴火などの自然災害に対する、予知も予防も未だに十分とはいえる状況にはない。せめて災害後の救援活動や復旧活動がスムーズに
展開されるための準備が計画的になされる必要がある。
こうした救援活動、復旧活動の中核を担うのが自衛隊である。人を殺すのではなく人を救うことのプロフェッショナルとしての価値こそ自衛隊の存在価値なのだ。
このための技術を設備的にもソフト的にも磨きをかけることに、ヒト・もの・金を集中的に投下することが今もっとも求められているのだ。
自衛隊が人を活かすプロフェッショナルとしての技術習得に専念すれば、世界中から尊敬を集め、その支援を乞われる機会も増加し、世界中に安心、安全を届ける存在として平和国家日本への信頼を確実なものにしていくはずだ。
食料自給率が40%を割り込んでいる
低い食料自給率を改善することも日本の安全保障上の最重要課題だ。つまり食料供給量の60%が輸入によって賄われているということだ。
自給率の高い順に見ていくと、コメの自給率は96%、野菜が80%、魚介類が62%の3品目だけが突出して高く、他の作物は軒並み30%以下の低水準にある。
例えば麺やパンの原料である小麦は9%の自給率でしかない。また和風食材の中心に位置する醤油、味噌、豆腐、納豆などの原料となる大豆の自給率は26%に甘んじている。油脂などは圧倒的に低い3%とほとんどが輸入品だ。そしてカロリーの素である畜産物の自給率も17%でしかない。しかも和牛や和豚の飼料となるトウモロコシもそのほとんどが輸入品で賄われている状況だ。
つまり日本の自給率は圧倒的に高いコメとその他の農産物に二極分解されている極めてゆがんだ構造になっていることが問題として浮かび上がってくる。
日本の農政がコメを中心とした政策展開に終始し、他の食料を海外特にアメリカに依存するという大方針に従って展開されてきた結果が、このようにゆがんだ農業構造を作り出してしまったのだ。
そして消費者のコメ離れとか消費カロリーの減少はこめの需要を傾向的に減退させてきたので、減反政策が昨今の農政の重要課題になってしまっている。
そして結果的に、食料自給率が40%を割ってしまっているのに、休耕田や耕作放棄地が100万haにも達する農地の惨状が引き起こされてしまったのだ。
自給率を上げるのはきわめて単純なことだ。これらの休耕田や耕作放棄地を畑に変えて、1950年代から作付けされなくなった小麦や大豆そして飼料用のトウモロコシを植えればいいのだ。同時に水田を放牧地に換えて牛や豚を飼えばいいのだ。
またこうした畑作物や畜産物を加工する中小の加工場を起業して、地産地消の循環体系を作ればいいということだ。
こうして自給率は改善に向かうことになるはずだ。自給率が上がれば輸入が減り、国内生産額が増加し、GDPは1を超える乗数で増大に貢献することになる。
今こそ、安保法制を変えて海外派兵や同盟国防衛のような張り子の虎のような「抑止力」の火遊びに夢中になるよりも、もっと大事な本当にこの国の安全を保障する重要施策に全力をあげて立ち向かうべき時なのだ。
革新的なIoTはなぜ日本では絶望的なのか?
日経新聞の「経済教室」に「IoTの可能性と課題」と題して東京大学教授の坂村健氏と法政大学教授の西岡靖之氏が寄稿している。
IoTとは、坂村氏の定義によれば「コンピューターが組み込まれたモノ同士がネットワーク連携して社会や生活を支援する、という考え方だ」。(日経新聞2015.07.09朝刊)
IoTを巡っては現在二つの潮流が注目を集めている。ドイツが中心になって進める『インダストリー4.0』と米国中心の『インダストリアル・インターネット・コンソーシアム』だ。
坂村氏はIoTの革新性はそのオープン性にあると看破している。
「インダストリー4.0が目指すのは、標準化したカンバンによりドイツ、さらには世界中の製造業すべてがつながれるという系列に閉じないカンバン・システムを目指している。
インダストリアル・インターネット・コンソーシアムも、米AT&T、シスコシステムズ、ゼネラル・エレクトリック(GE)、IBM、インテル、独ボッシュといった欧米の大企業が組んで実用化をめざす普及機関である。自社製品に閉じたシステムでなく、広くオープンに予防保全や運転効率化の枠組みを確立しようとしているところに意義がある」。(同)
坂村氏は自社系列や自社製品に閉じられた世界ではなく、あらゆるモノをオープンに繋いで標準化や効率化をめざすのがIoTの特徴とされている。
そして坂村氏は日本はこのオープン・システムの開発において決定的な弱みを持っていることを危惧されている。自社や系列内で有効性を発揮する閉じたシステムは得意とするが、インターネットのようなオープンなシステムの開発では遅れを取っているからだ。
「研究段階が終わり、社会への出口を見つける段階になると、技術以外の要素が問題になる。そのとき、オープンな情報システム構築に不得手なギャランティー志向であることが、日本のIoTにとって大きな足かせとなる。意識レベルからこの問題を解決しなければ、技術的に十分可能であっても、オープンなシステムは構築できない。」。(同)
面白いことに西村氏も同様の懸念を指摘している。
「現時点では課題も多い。その筆頭が標準化の問題である。『モノとモノ』、『コトとコト』がつながるためには、企業を超えた共通のルールや決め事が必要となり、それぞれに関する標準化が要求される。日本の多くの製造業は、これまで蓄積してきた膨大な技術やノウハウが社外流出することによる競争力喪失を懸念して、標準化やつながる仕組みにはおおむね閉鎖的であった。セキュリティーに関する課題も、多くが解決されずに残されている」。(日経新聞2015.07.10朝刊)
こうした中で6月に国内で産学が連携する形で、企業を超えてものづくりが相互につながるための仕組みを構築する動きが現れた。6月に発足した『インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ(IVI)』がそれだ。
「『ゆるやかな標準』というコンセプトのもとで、競争領域と協調領域の境界を、企業の垣根を越えて再定義する。協調領域においては大胆にオープン化し、相互に連携するためのリファレンス(参照)モデルを構築する。トヨタ自動車、日産自動車、三菱重工業、川崎重工業、IHI、パナソニック、日立製作所、三菱電機、富士通、NECなどが、日本発のつながる工場の仕組みをつくり、広く海外にも参加を呼び掛けていく」(同)という。
この動きに期待したいところだが、製造業だけでIoTを考えようとしているところで、すでに部品製造から、組み立て、販売まで一気通貫のシステムを構想しているドイツの「インダストリー3.0」に後れを取っている。
日本でもサービス業はすでにGDPの70%を担い、従業員の50%を雇用している。この分野でのIoTの展開こそが決定的に重要であるはずだからだ。
筆者の経験でも、消費財分野でメーカーから卸店までのトレースは可能だが、小売業まで、更にその先の消費者一人ひとりまでの商品のトレースは現状では絶望的だ。
我が国のIoTを世界に先駆けた真に革新的なものにするには、例えば消費財メーカーから消費者までの商品のトレースをオープン・システムで可能にすることをIoTのビジョンに掲げるような構想力が必要とされているわけだ。
アップルがコンテンツに接近.ソニーはどうする?
アップルは6月30日音楽をストリーミング方式で配信する定額聞き放題サービス、「アップル・ミュージック」の提供を始めた。先行する英スポティファイなどと同規模の3千万曲をそろえ、日本を含む100ヶ国以上でこのサービスを展開する。
アップルはこの新サービス提供を契機にコンテンツ制作サイドとの連携を緊密にしていくための打ち手を展開している。
「アップルは個別曲・アルバムのダウンロード販売では7割だった音楽会社の取り分をさらに数%上乗せした。ダウンロード販売についても利益配分の上乗せを検討している。昨年買収した米ビーツ・エレクトロニクスの人脈をコンテンツ獲得に生かし、ビーツ出身の専門家の力を借りて利用者の好みに合った曲を推薦する手法も確立した」。(日経新聞2015.7.1朝刊)
音楽や映像の配信サービスを手掛けるIT企業はすでに、コンテンツ業界への急接近を始めている。
「米動画配信大手ネットフリックスは8月に人気俳優ブラッド・ピット氏企画の戦争映画の制作に入る。今年はコンテンツ制作・獲得に30億ドル(約3700億円)以上を投じる見通しだ。同社は今秋にサービスを始める日本でも独自コンテンツにこだわる。男女の共同生活を描いたフジテレビジョンの人気番組『テラスハウス』の新シリーズなどを先行配信する。
米アマゾン・ドット・コムも自前の制作スタジオを運営し、昨年はコンテンツ獲得に約13億ドルを投じた。今年から映画祭での買い付けを始め、劇場公開から数カ月後には自社サービス上で独占配信する計画だ」。(同)
アップルの音楽、映像配信サービスであるi-tuneはi-podとセットで登場し、一時は音楽、映像配信サービスの領域で独占的な地位を築いた。しかし配信サービスの他社参入や端末の多様化によってi-tuneの先行的地位は揺らぎ始めた。そして最近の楽曲の定額聞き放題サービスへのIT業界からの競争的な参入がアップルの地位を大きく揺るがした。
この状況でアップルは新サービスへの遅ればせの意参入とともに、コンテンツ制作業界との融合を実現して、単に配信するだけでなく、創造分野への参画を果たして、圧倒的な規模のユーザーとの直接的なコミュニケーション力を駆使して、コンテンツ制作により魅力的な創造性を付与し、創造的なアーティストを囲い込む戦略の実現に踏み出したわけだ。
ところでアップルのこの動きを音楽、映画製作を事業分野の一つとするソニーが指をくわえて見過ごすことがあってはならない。ソニーはアップルに先駆けてコンテンツ制作に身を置いて、そのビジネスノウハウを磨いてきたはずだ。
それに加えてソニーはアップルが持たない映像、音響ビジネスに魅力的なコンピテンスを持っている。そしてソニーの音響、映像技術は当然コンテンツ制作と融合して、競争優位の価値創造を実現しているはずだ。
ソニーがコンテンツ配信サービスに本格参入して、その優れたノン狂、映像技術に裏付けられたコンテンツ制作と融合することで、アップルを超える価値創造を果たすことが可能になる。
そのとき同時にソニー制作のコンテンツが、ソニー製のテレビやスマホなどの端末でなくては実現できない臨場感を持ったひときわ質の高い映像や楽曲を経験する仕掛けを内蔵していたら、ソニーは圧倒的な競争優位に立つはずだ。
折りしもソニーは公募増資などで4400億円の資金調達に踏み切ったが、その使途は画像センサーもさることながら、こうした壮大なビジョンの実現に向けて投下することも一考に値する。
社外役員が代表取締役に辞任を迫った
「東洋ゴム工業の免震ゴムの性能データ改ざん問題で、信木明会長と山本卓司社長に加え、リスク管理担当の久世哲也専務執行役員も引責辞任する方向になった。代表取締役3人全員が退任するのは異例の事態。改ざんの放置につながった経営判断の甘さを重く見た社外の取締役や監査役が厳しい対応を迫ったためだ。『外圧』が社内の自浄能力の欠如を浮き彫りにした」。(日経新聞2015.6.19朝刊)
社外役員によってガバナンスが正常に機能したことが評価できる。
しかし、13年の夏に社内で不祥事が認識されたにもかかわらず、出荷停止の対応が始まったのは今年の2月。この間にも不良品の納品が続いた。
「データ改ざんは2013年夏に免震ゴムを製造した子会社が把握し、14年5月には信木社長(当時)ら東洋ゴム経営陣にも報告が上がった。調査を経て9月の社内会議でいったん出荷停止の準備に入ることを決めたが、すぐにデータを補正すれば出荷を継続できると判断を変更した。
出荷停止を決めたのは今年2月で、問題物件は154棟に達した。『緊迫感に欠けた楽観的な認識に基づく対応がなされた』。社外調査チームは4月に作成した中間報告書でこう批判した。建物の安全性に直結する製品を供給している意識が決定的に欠けていた」。(同)
もう少し早く社外役員によるガバナンスが機能していれば、顧客のリスクを拡大せずにすみ、結果として損失も抑制できた。
リスクを認識した時点で素早く、リスクの拡大を防ぎ、リスクをなくすための対応を経営陣に迫ることが、社外役員に求められるということだ。
更にこの事例で大事なことは、リスクの拡大を早急に防ぐということもさることながら、リスクに対する鈍感さを質すことだ。この鈍感さは、企業文化が抱える大いなる欠陥といえる。
従って大切なことは起こってしまったリスクに素早く対応して、リスクの拡大を防ぐだけでなく、こうしたリスクに対する不感症を革める根本的な治癒策を経営陣に求めることだ。
とすれば、今回の代表取締役の辞任は問題解決の始まりにすぎず、不良品の出荷を見過ごすような企業風土の欠陥の根本原因を解明し、之を除去することを経営陣に迫り、その素早い実行を見届けることを、社外役員が責務として努めなければならないということだ。
そして社外役員にとって究極の使命は、こうした企業文化の改革をリードする経営トップを選任することだ。
はたしてこれまでこうしたリスク不感症の企業文化にどっぷり漬かってきた社内の人材が、自己否定の改革をリードすることができるだろうか。この際思い切って企業文化の破壊と創造に取り組む人材を社外に求めるべきか。
こうした決定的に重要な問いに答えて最適な解を模索することが社外役員に求められている。東洋ゴムの社外役員は当分眠れない夜が続くことになる。
「マイナス成長でも最高益」は実力なのか?
2015.6.7付日経新聞で、「マイナス成長でも最高益」のコラムが一面を飾っている。その論旨はこうだ。
「日本企業にとって2015年3月期は歴史的な一年になった。実質国内総生産(GDP)の伸びがマイナスにもかかわらず、上場企業の経常利益が7年ぶりに最高を更新したからだ。その原動力は各社が地道に育ててきた海外事業にある。
海外事業の拡大の一方で見逃せないのが、企業が利益への意識を高めてきたことだ。売上高経常利益率は今期6.7%と連結決算が本格化した2000年代以降で最高になる。
ただ前期は円安が利益をかさ上げした面も大きい。自動車や電機、機械の主要22社を対象に円安が営業利益をどれだけ押し上げたかを集計すると1兆円弱に上り、増益分に匹敵する」。
煎じ詰めれば、企業が利益志向に意識を切り替え、まじめに利益追求に励んだことに加えて、海外事業の拡大と円安効果が企業の利益水準を押し上げたということになる。
しかし海外事業の拡大は14年度に一気に実現したわけではない。国内市場の飽和とグローバル化の進展が円高局面の継続に背中を押されて、海外での現地生産の展開を促した。
その基盤の上で、円安が円換算での売上高と利益を押し上げたことが企業業績の拡大を実現したということだ。
具体的には14年度において前年対比で約20%の円安だったので、輸出と海外事業の業績は量的な拡大なしでも円評価で約20%の膨張をしたことになる。つまり企業は業績改善の努力をなんら行わなくとも、海外取引で20%の増収増益のアドバンテージを得ることができたというわけだ。
とすれば円安が現状の水準を大きく更新しないとすれば、15年度の企業業績はこれ以上の改善は期待できないと見るべきだ。
むしろ円安は輸入品の価格を押し上げて、企業のコスト構造にダメッジを与え、さらに消費財の価格を押し上げて、消費支出の拡大に水を差し、企業業績は停滞局面に移行し、経済規模は縮退することになると見るべきだ。
このような状況で経済の拡大を目指すとすれば、個別企業はそれぞれの企業努力によって、新しい需要を創出したり、拡大することが求められる。まさにイノベーションによる需要創造が本格的に必要とされているということだ。
これに関連して、2015.6.8付日経新聞の「経済教室」における慶応義塾大学の池尾教授の論考が参考になる。
池尾氏の指摘は次のようだ。
「日本の現状にあった成長戦略を組み立てるには、人口問題に正面から焦点を当てることが必要だ。そうした観点から翁邦雄・京大教授は近著で、後期高齢者の健康維持(健康寿命延伸)のための対策を集中的に講じるという成長戦略を提案している。高齢者が健康であり続ければ、減少する労働力を介護にとられて、他の用途に投入できなくなるという問題の軽減につながる。
それだけでなく、健康寿命の延伸に関しては、医療技術の革新や新薬、介護ロボットの開発といったイノベーションが不可欠であり、そうしたイノベーションの成功は膨大な需要の創出につながる可能性がある。大きな需要が持続的に見込めるのであれば、設備投資も誘発される」。
世界的に見て前人未到の高齢化社会に突入した日本にあっては、医療、介護、健康分野での先行的なイノベーションがグローバルにも大きな需要を創出し、拡大する大きなチャンスが拓けていると見るべきなのだ。
ハーバード大学教授のマイケル・ポーター氏が日経ビジネスの記者のインタビューに答え、トランプ大統領に対しての高評価と期待を語っている。
「マイケル・ポーター教授が語るサステナブル経営」(日経ビジネスオンライン)
ポーター教授はトランプ大統領の登場を二つの意味で歓迎している。
一つはトランプ大統領が経済の成長を目標に置いているという点だ。大統領選で敗れたクリントン氏は成長よりも再配分に重点を置いていた。
二つ目にはトランプ大統領が社会的な課題の解決を提案しているということだ。これまでの20年間政治は雇用の拡大が進まないというような、平均的な市民が経済成長の恩恵を受けていないという社会問題を何一つ解決することはできなかった。
CSVの重要性
記者はポーター教授に次の問いかけを行っている。
「ポーター教授は、企業がCSV(Creating Shared Value=共通価値の創造)に取り組むことの重要性を提唱しています。昨年発表した米国経済に関する論文では、米国の問題は繁栄の恩恵を社会と共有できていないことだと指摘しています。ブレグジットやトランプ大統領誕生の背景を考えると、企業はこれまで以上に社会との『共通価値の創造』を重視する必要性に迫られるのではないでしょうか」。
ポーター教授は次のように答えている。
「まさにその通りです。既に多くの企業は、利益の一部を寄付したり、単にCSR(企業の社会的責任)活動に取り組んだりという状況から、CSVへと移行してきました。つまり、事業そのものを通じて、社会によりよい影響を及ぼそうという方向に動いています。ブレグジットやトランプ大統領の誕生によって、企業は社会課題の解決に、より積極的に取り組む必要性を認識するでしょう。その意味で、現在の状況は共通価値の創造を企業の経営戦略に組み込む流れを、これまで以上に加速するはずです。
CSVというのは、博愛の精神を指す考え方ではありません。企業が競争上、ライバルとは異なる方法で優位に立つための戦略です。まさに、そのムーブメントが今、本当に加速し始めています。
社会に与える影響について配慮せよという、企業に対する市民の要求は、急速に強まっています。そのため、すべてのステークホルダーに対して配慮しなければならないと考える企業は、ますます増えています。
エネルギー効率を改善し、健康に寄与する商品を作り、従業員が会社の中で成長できる機会を提供することなどは、そもそも、企業が持続的に成長し、より成功を収めるために不可欠なことだと理解されてきました。
共通価値の創造というコンセプトは、資本主義が持つ究極の力を引き出すものです。企業が得た利益を社会に再分配するという発想ではなく、社会課題を解決し、社会のニーズに応えること自体が、企業を競争上、より優位にする。そうしたコンセプトを企業戦略に組み込むことが、資本主義の真の力を引き出すことにつながるのです。
そのことを、世界をリードするグローバルカンパニーの多くが理解している。スイスのネスレなどは、その典型でしょう。米国のウォルマート・ストアーズでさえ、最近は大きく変わりました」。
企業が全てのステークホルダーに対して配慮しなければ企業活動を継続的に実現できない状況がすでに出現しているということなのだ。
これこそまさに資本主義を社会的および公共的観点から改造して、資本主義が引き起こし、その究極のすがたであるグローバリゼーションの果てに生み出した極端な貧富の差や中産階級の没落や南北問題、さらには地球環境の持続性の危機などの諸矛盾を乗り越えようとする修正資本主義の立場だ。
メキシコ工場建設はCVSに適うか
このような観点で現在トランプ大統領がフォードやトヨタを名差しで非難した米国企業のメキシコでの工場建設の問題を考えて見よう。
企業は製造工場を米国につくるか、メキシコにつくるかの意思決定を迫られたときに、その判断基準としてどちらの立地が自社にとって利益を最大化するかという視点を用いるはずだ。
この利益至上主義が結果として米国の生産拠点の減少と雇用の減少を結果したわけだ。しかしその裏で米国民は米国産の製品と同等の品質のメキシコ産の製品を従来の米国産の製品より安価に購入することが可能になる。
そればかりか翻ってメキシコに目を移せば工場誘致によって雇用が生まれ、同時に工場を支えるパートナー企業の増産効果でここでも雇用が相乗効果的に生まれ、結果として賃金の上昇も期待できることになる。米国で仕事を奪われる市民以外のステークホルダーが満足することになるように思われる。
メキシコ工場建設はメキシコの社会問題を解決しない
しかし良く考えると重大な問題が取り残される。メキシコから米国へ輸出される製品価格は労働者の所得水準の米国労働者との格差を是正することはないし、また工場が生み出す環境破壊の解決をもたらすこともない。ましてや地域のインフラ整備などに寄与する水準でもない。
極端に言えばメキシコの市民や地域の抱える社会問題を是正することには貢献することはないということだ。つまりメキシコ進出は米国の労働者の雇用を奪うばかりかメキシコ社会やメキシコ市民というステークホルダーにとっても決してプラスに働くことにはならないというわけだ。
メキシコ社会というステークホルダーに配慮するということ
メキシコの労働者に米国の労働者と同等の賃金、福利厚生を保証し、地域社会に対して米国と同等の法人税を支払い、米国土同様の基準での環境規制に従うことを前提にメキシコ工場の建設を行うことではじめてメキシコのステークホルダーに配慮することになるわけだ。
つまりグローバル化時代にすべてのステークホルダーに配慮するということは、自国のステークホルダーにのみ限定するのではなく関係するグローバルなステークホルダーすべてに配慮するということに他ならない。
この原則は「フェアトレード」の主張を取り入れて企業活動を実行することにつながる。グローバル化の果てに資本主義が行き詰まりの罠に陥らないためにはそこまでの奥行きを持ってCVSを語らなければならない時代に来ているという認識が問われているのだ。